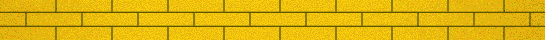
�Q�O�O�S�N�x�O�������[�~�������W
- �S���P�S���@�����擾
�@�P�@�w�Ђ͑i�O�x�Ђ̐��������{���@�B���i�b��]���ړI�ōw������_��������A���̍ہA�u�b�͂x�̑q�ɂɒu�����܂܂ɂ��Ă����A�w�̎w��������Γ]����ɒ��ڈ����n���v���Ƃ��x�ƍ��ӂ��āA��������ς����B���̌�A�w�͑i�O�`�Ђɍb�p����_������сA������ς܂ŏ��L�����w�ɗ��ۂ���Ƃ�������������B�Ƃ��낪�A�`�́A�����J��ɍ����Ăw�ɑ�����x�����Ȃ������ɂ�������炸�A�w�̏��i�Ǘ��E�����Ȃǂ�S������]�ƈ����x���đ�������ς��ꂽ�ƌ�M�����A�u�b�̏��L���͂`�Ɉړ]�����̂ŁA�Ȍ�͂`�̂��߂ɍb��a����A�b�̈��n���̕��@���ɂ��Ă͂`�̎w���ɏ]���悤�Ɂv�Ƃ����ʒm�����x�ɑ��đ��t�������B�����āA�`�́A����ɁA���̂悤�Ȏ���ɂ��ĉ����m��Ȃ��y�Ƃ̊ԂŁA�y�ɑ�����ٍ̕ςɑウ�čb�����t����Ƃ��������������A�u�b�̏��L���͂y�Ɉړ]�����̂ŁA�Ȍ�͂y�̂��߂ɍb��a����A�b�̈��n���̕��@���ɂ��Ă͂y�̎w���ɏ]���悤�Ɂv�Ƃ����ʒm�����x�ɑ��t�����i�����������n�����@�ɂ��āA�������y�͓��ӂ��Ă����j�B�b�͌��݂��x�̑q�ɂɕۊǂ���Ă���B�`���|�Y�����̂ŁA�`����̑��Q�̉����҂ł��Ȃ��w�́A�x�ɑ��čb�̈��n�������߁A�y�ɑ��čb�̏��L���̊m�F�𐿋������B�w�x�y�Ԃ̖@���W�͂ǂ��Ȃ邩�_����B
�@�Q�@�i�O�l���X��`�͑i�O�a�Ђ̐��������{���@�B���i�b��]���ړI�ōw������_��������A���̍ہA�u�b�͂a�̑q�ɂɒu�����܂܂ɂ��Ă����A�`�̎w��������Γ]����ɒ��ڈ����n���v���Ƃ��a�ƍ��ӂ��āA��������ς����B���̌�A�`�ɑ��ēq���Ɋ�Â�����L���Ă����b���A�㕨�ٍςƂ��čb�������n���悤�����������̂ŁA�`�͂�ނȂ��A�u�b�̏��L���͂b�Ɉړ]�����̂ŁA�Ȍ�͂b�̂��߂ɍb��a����A�b�̈��n���̕��@���ɂ��Ă͂b�̎w���ɏ]���悤�Ɂv�Ƃ����ʒm�����a�ɑ��đ��t�����B�����āA�b�́A����ɁA���̂悤�Ȏ���ɂ��ĉ����m��Ȃ��w�Ђ���тx�Ђɑ��āA�b�p����_������Ō��сA�w����тx���炻�ꂼ��������̂����B�b�w�E�b�x�̌_��́A�b�̖����������̕������b��L���ɑ㗝���Ăw�E�x�̒S���҂Ƃ̊ԂŒ����������̂ŁA�_�̓��t��������ƂȂ��Ă����݂̂Ȃ炸�A�u�b�̏��L���͂w�i�x�j�Ɉړ]�����̂ŁA�Ȍ�͂w�i�x�j�̂��߂ɍb��a����A�b�̈��n���̕��@���ɂ��Ă͂w�i�x�j�̎w���ɏ]���悤�Ɂv�Ƃ����X���̒ʒm�����i�����������n�����@�ɂ��āA�������w���x�����ӂ��Ă����j�A�����a�ɔz�B����āA�����ꂪ��ɂa�ɓ��B�������s���ł���B�b�������͏�ԂȂ̂ŁA�b����̑��Q�̉����҂ł��Ȃ��w�Ƃx�́A�b�̏��L��������ɋA������Ǝ咣���đ����Ă���B�Ȃ��A�`�͓q���Ɋւ��镉���ڂ�����̂ōb�̏��L�����咣���Ă��Ȃ��B�܂��A�a�́A���ҕs�m�m�𗝗R�ɍb�����������B�w�x�Ԃ̖@���W�͂ǂ��Ȃ邩�_����B
- �S���Q�P���@�����
�@�ȉ��́A�ŎO���������P�S�N�P�O���Q�Q�������P�W�O�S���R�S�ł̔���������A�����̊T�v�ƌ��R�̔��f���ꕔ�ύX�̂������������������̂ł���B�����ǂ�ňȉ��̖₢�ɓ�����B
�@(1)�@�w�́A�i�O�`��Ђɑ������S�ۂ��邽�߁A�i�O�a���L�̍b�s���Y�ƕ��s���Y���тɑi�O�b���L�̉��s���Y�̏�ɋɓx�z�P���R�O�O�O���~�̋����������L���Ă����B
�@(2)�@�x�́A�i�O�c��Ђɑ������S�ۂ��邽�߁A���y�ёi�O�d���L�̕s���Y�̏�ɋɓx�z�Q�X�O�O���~�̋����������L���Ă����B
�@(3)�@���s���Y��̂w�Ƃx�Ƃ̍�����́A���ʕύX�ɂ�蓯���ʂƂ���A�����W�N�V���P�W���A���̎|�̓o�L���o�R���ꂽ�B
�@(4)�@�b�A���A���ɂ���(1)�L�ڂ̂w�̍�����̎��s�Ƃ��ċ������J�n����A�����P�Q�N�T���Q�Q���A�z���������w�肳�ꂽ�B
�@�Ȃ��A�w�̒�o���������\�����ɂ́A�������Ƃ��āA�c�����T�V�X�T���X�O�V�O�~�y�т��̋��z�ɑ��镽���X�N�P���Q�W������x���ς݂܂ł̔N�P�S���̊����ɂ�鑹�Q���Ƃ̋L�ڂɉ����A���N�Q���P�V���̓����ٍϋ��P�P�R���Q�V�R�X�~�ɑ��铯�N�P���Q�W�����瓯�N�Q���P�V���܂łQ�P���Ԃ̔N�P�S���̊����ɂ��m�葹�Q���P�Ƃ��ĂX�P�Q�R�~�Ƃ��ׂ��Ƃ�����X�P�Q�~�A���N�P�P���P�W���̓����ٍϋ��W�P�X�P�~�ɑ��铯�N�P���Q�W�����瓯�N�P�P���P�W���܂łQ�X�T���Ԃ̔N�P�S���̊����ɂ��m�葹�Q���Q�Ƃ��ĂX�Q�U�~�Ƃ��ׂ��Ƃ�����X�Q�~�Ƃ̋L�ڂ�����Ă������A�w�̒�o�������v�Z���ɂ́A���ꂼ�ꐳ�����v�Z���ʂ��L�ڂ���Ă����B
�@(5)�@��L�z�������ɂ����āA���s�ٔ����́A�m�葹�Q���P�y�ѓ��Q�̋��z���w����o���������\�����ɋL�ڂ��ꂽ���z�ł���Ƃ��āA�w�̔�S�ۍ��z���W�S�W�W���P�U�U�T�~�Ƃ��A���̏�ŁA����z�y�ю葱��p�̊z���b�A���A���̊e�Œᔄ�p���z�ɉ����Ċ���t���A���ꂼ�ꊄ��t����ꂽ����z����葱��p�̊z���T�������s���Y���z�i�b�ɂ��Ă͂S�X�O���V�P�X�X�~�A���ɂ��Ă͂W�P�U���V�O�U�S�~�A���ɂ��Ă͂P�R�X�O���X�T�R�P�~�j�ɏ����Ăw�̏�L��S�ۍ��z�̕��S���b�A���A���ɕ����A�w�Ƃx�Ƃ̍�����������ʂł��鉳�ɂ��ẮA���̕s���Y���z���w�̔�S�ۍ��̂������̕��S�z�Ƃx�̔�S�ۍ��z�Ƃ̊����ɏ]���Ĉĕ����A�w�ɑ��ẮA�b�y�ѕ��̊e�s���Y���z�Ɖ��̕s���Y���z�̂����w�ւ̈ĕ��z�S�T�W���W�R�P�O�~�Ƃ̍��v�Q�R�S�O���T�O�S�O�~��z�����A�x�ɑ��Ă͉��̕s���Y���z�̂����x�ւ̈ĕ��z�R�T�V���W�V�T�S�~��z������|�̔z���\���쐬�����B
�@(6)�@�w�́A��L�z�������ɂ����āA�x�ւ̔z���z�̂����Q�O�P���X�P�O�S�~�ɂ��Ĕz���ًc�̐\�o�������B
�@�{���́A�w���x�ւ̔z���z�̂����ًc�ɌW���L���z���w�̔z���ɉ�����ׂ��ł���Ƃ���z���ًc�̑i���ł���B
�@�w�́A�����\�����̖����Ȍ�L�͂��̌�ɒ�o���ꂽ���v�Z���ɂ����Ē�������Ă���Ƃ��A�܂��A�{���ɂ����ẮA�܂��A���̕s���Y���z���w�Ƃx�̊e��S�ۍ��z�ɂ��ĕ����ׂ����̂ł���A���̏�ŁA�b�y�ѕ��̊e�s���Y���z�y�щ��̏�L�ĕ��z�ɏ����Ăw�̔�S�ۍ��z�̕��S���b�A���A���ɕ�����ׂ��ł���Ǝ咣�����B
�@���̓_�ɂ��A���R�́A�m�葹�Q���P�y�ѓ��Q�̌�L�́A���s�ٔ������v�Z�Ⴂ���������߂ɐ��������̂ł͂Ȃ��A�w�̌v�Z�Ⴂ�ɂ��A���ʓI�Ɉꕔ�����ƂȂ������̂ł����āA���s�ٔ����������Ȍ����ʼn߂������̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ�����A�z���\�̍X�������邱�Ƃ͋�����Ȃ��Ƃ��A����ɁA���̕s���Y���z���w�Ƃx�Ɉĕ�����ɓ����获�s�ٔ������̗p�����v�Z���@�ɂ��ẮA���s�ٔ������̗p���������͖��@�R�X�Q���P���̕����ɉ����A�w�̎咣���錩���ɂ����_������A�����̍��������r�������ʂɂ���Ĉ���̐��ł��鎷�s�ٔ����̌������̗p�������Ƃ���@�ƂȂ���̂Ƃ܂ŔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ��āA�w�̐��������p������P�R�����̌��_���x�����āA�w�̍T�i�����p�����B
���
�@���R�̔����Ƃw�̎咣�́A�ǂ̓_����̓I�ɈقȂ�̂��B
�@�㍐�R�́A���̎����ɂ��āA�ǂ̂悤�ȗ��R�ŁA�ǂ̂悤�Ȕ��f���������ƍl�����邩�B
- �T���P�X���@�����I������
�@�x1���p�ς݂ɂȂ����Ɩ��p�̐����@�B���H�ꉡ�̋n�ɕ��u���Ă������Ƃ���A�C�����Ďg������łx2��������������������A���ǂ͏C����������߂Ăx3�̓y�n�Ɏ̂Ă��B�x3���A���������@�B���A��^�S�~����ʂɓ�������Ă���w���L�̎R�тɎ̂Ă��B�ߗZ������̋������w���A�����Ǝ҂Ɍ��ς�������Ă�������Ƃ���A�@�B�Ɏg���Ă����댯�������R�ꂾ���Ă��ēy�낪��������Ă���A��́E�p��������10���~�A�y��̐��E����ւ�������100���~���̔�p��������Ƃ̂��Ƃ������B�����ŁA�����ŏ�������̂�������߂��w������������Ƃ���A�̂Ă�ꂽ�o�܂��킩�����B�w�́A�����ɂǂ̂悤�Ȑ��������邱�Ƃ��ł��邩�B
�i1998�N12��9���_�ˑ�w���@��ė��K��ɏo�肵�������j
�y����z
�y�|�C���g�z
�@�����I�������Ɋւ����{�I�ȗ������A����I�Ȕp�������Ƃ������p��Ŗ₤���̂ŁA�����̂Ȃ������i�����j��������ł͂Ȃ��B�e���̃Z���X�ŁA�o�����X�ǂ��L�������������ė~�����B�Ȃ��A���a45�N�@����137���p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���i�p���������@�j�Ƃ������ʖ@������A�����̋֎~��NJ��s�����̉��P���߂Ȃǂ��߂Ă͂��邪�i����������j�A���@�I�ȋK��͂Ȃ��A���̖��ł͌�������K�v�͂Ȃ����̂Ƃ���B
�@�E�����I�������̔퍐�K�i�|���̋@�B�̏��L���̏���
�@�@�E�x1�̕��u�̈Ӗ��|���L�������̈ӎv�̗L��
�@�@�E�x2�̐�L�擾�̈Ӗ��|���啨���̐���
�@�E�����I�������̓��e�Ɣ�p���S
�@�E�����I�������ƕs�@�s�אӔC
�y��z
�@��@�w�̎R�сi�̓y�n�́j���L���́A�����ɓ������ꂽ�{�������@�B�ɂ���ĖW�Q����Ă���B���L���Ȃǂ̕����̓��e�̎������W�����Ă���Ƃ����q�ϓI�Ȉ�@��Ԃ�����A�����镨���I����������������B���@�͂��ߖ@���ɂ͖����̋K��͂Ȃ��A���̐����⍪������e�̏ڍׂɂ��Ă͉��߂ɂ�邽�ߋc�_���������A���Ȃ��Ƃ���̓_�Ɋւ��ẮA����E�w������v���ĔF�߂�Ƃ���ł���B
�@��@����܂ň�ʓI�ɔF�߂��Ă���Ƃ���ł́A�����I�������̈�Ƃ��Ă̖W�Q�r���������̑�����ƂȂ�̂́A�u���ɖW�Q�������Ă��鎖�������̎x�z���Ɏ��߂Ă���ҁv�i��ȁ��L��266�Łj�ł���A�W�Q���̏��L�҂ł���B�Ƃ��낪�{���ł́A���̓_�ɖ�肪����B
�@(1) �x1���{���@�B���n�ɕ��u���Ă������Ƃ��Ă��A���ꂾ���ł͏��L�������̈ӎv���������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�x1�ɏ��L�������̈ӎv���Ȃ������Ƃ���ƁA�@�B�̏��L���͂x1�̉��ɂƂǂ܂�B�x2���@�B�啨���Ɛ����Ɍ�M���A���L�̈ӎv�������Ă��̐�L���J�n�����Ƃ��Ă��A���啨���i239���j�͐��藧���Ȃ��B�x3�ɂ��ẮA����������L�̈ӎv���Ȃ��i���邢�͋q�ϓI�Ȏx�z�̎�������Ȃ��j�B��������ƁA�x2�x3���@�B�̏��L�����擾�����Ɖ�����]�n�͂Ȃ��A�����I�������̑�����ɂȂ�̂́A�x1�݂̂ł���B�x1�ɏ��L�������̈ӎv���Ȃ��������Ƃ𗝗R�ɁA�x2�����������ӔC��Ƃ��咣�����邱�Ƃ́A���ӂ̔�Q�҂w�Ƃ̊W�Ō������p�Ƃ��ċ�����Ȃ��A�Ɖ�����]�n���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A�x2���x1�ɑ����āA���邢�͂x2�Ƌ��ɖW�Q�����ӔC�����ƂɂȂ낤�B
�@�w�̎R�я��L�����W�Q����Ă���̂́A�x2�E�x3�̍s�ׂ���Ă��邩��ł���A�ꍇ�ɂ���Ă͂x1�ɂ͂����鎖�Ԃ��������邱�Ƃɂ��Ă̗\���\���������A�̈ӂ͂��Ƃ��ߎ����Ȃ��Ƃ����邩������Ȃ��B�������A�����I�������̔����ɂ́A�N�Q�҂̌̈ӂ�ߎ���v�����A�q�ϓI�ɕ������N�Q����Ă��邾���ő����B����ɂ́A�s�R�͂̏ꍇ�ɕ����I���������������Ȃ��Ƃ̖T�_��W�J������̂����邪�i�唻��12�N11��19���W16��1881�Łj�A���Ȃ��Ƃ��{���͕s�R�͂����ɂȂ�P�[�X�ł͂Ȃ��̂ŁA���L�҂x1���퍐�ɂȂ邱�Ƃɂ͈٘_�͂Ȃ����낤�B
�@��肪��������ɂx1�����L�����������ӎv�\���������Ƃ��Ă��A�����ӔC��Ƃ�邽�߂̏��L�������͑��l���Q���邱�Ƃ�F���F�e����s�ׂł���A���Ȃ��Ƃ����̐ӔC���Ȃ���Q�҂w�Ƃ̊W�ł́A�������p�i1��3���j�Ƃ��ċ�����Ȃ����̂Ǝv����B
�@(2) �x1���@�B����u���Ă����̂����L�������̈ӎv�ł������Ƃ���ƁA�x2�����啨���ɂ�菊�L�����擾���A��q�̂悤�ɂx3�ɂ͏��L���擾���F�߂��Ȃ��̂ŁA���L�҂́A�ꉞ�x2�ł���B�x2���x3�̓y�n�ɋ@�B���̂Ă��s�ׂ́A�ʏ�A���炩�ɏ��L�������̈ӎv���������Ƃ݂��邪�A(1)�ŏq�ׂ��Ɠ��l�A���L���������咣���ď����`����Ƃ�邱�Ƃ͌����̗��p�Ƃ��ċ�����Ȃ��B���̏ꍇ�A�x1�̏��L�������ɂ��Ă��������p�Ƃ��A�w�ɑ���W�ł́A�x1�������ӔC���Ƃ��A�x1���x2�ƕ���ŏ����ӔC���i�s�^���A�ѐӔC���j�A�Ɖ�����]�n���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B
�@�y�Ǖ�z�@����ɁA���^�̒��Ŏ咣���ꂽ�悤�ɁA���������W�Q�҂ɏ��L�������邩�ۂ�����ɂ����ɁA�Ƃ�킯�x3�ɂ��ẮA���ړI�ȖW�Q�s�ׂ̌��ʂ��������Ă���̂ŁA�����ӔC�킹��]�n������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����c�_�̗]�n�͂��낤�B�]���͖W�Q���ɂ�����������L���Ă��Ȃ��Ɗ�{�I�ɂ͐ӔC�킹�邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƍl�����Ă������i�s�@�苒�����̏��������̑�����̋c�_�j�A�p�����Ƃ������L��������������ɂ��ē����c�_���ł��邩�Ƃ����^��ł���A�����Ƃ��ȑ��ʂ����B�����A�W�Q�r���������̗v�����A���ɂ��̔p�����ɂ��W�Q����Ă��錻��ł��邱�Ƃ��炷��ƁA�x3�̏����ӔC�́A�����I�ɂ͉ߋ��̖W�Q�s���̂���ɂ��Ă���ɂ������A�s�@�s�ׂɊ�Â����Q���������Ƃ̌����I�ȋ�ʂ����ɂ����Ȃ�B��ʓI�Ȗ���Ƃ��Č���������̂́A�Ȃ������̍������悤�Ɏv����B
�@�O�@�x1�x2�̂����ꂩ���P�ƂŁA���邢�͗��҂�����ŖW�Q�����ӔC���Ƃ��āA���̓��e�͂ǂ��������̂��B����E�������́A������̔�p�ŖW�Q�����s�ׂ𐿋��ł���Ƃ���i�s�א��������B�����ɂ����ƐN�Q�̔F������i�ɍs���C���s�א����������������̂悤�ł���j�B����ɑ��āA�L�͐��́A�����I�������̓��e�͖W�Q�����s�ׂ̔E�i�F�j�e�ɂƂǂ܂�Ƃ���i�E�e���������j�B���̐��ł́A�������҂���p�S���A�̈ӂ܂��͉ߎ��̂��錴���s�҂ɕs�@�s�ׂɂ�鑹�Q���������߂邱�ƂɂȂ�B����ɁA�����ܒ����āA�퍐�Ɍ̈ӁE�ߎ��Ȃǂ̐ӔC������ꍇ�ɂ͍s�א������i���������p���S�j�A�Ȃ���ΔE�e�������i�������Ҕ�p���S�j�Ƃ���l�����i�ӔC���j�ق��A���܂��܂ȍl����������B�����̐��́A�@�N�Q�҂ɕs�@�s�ׂ̗v���i�̈ӁE�ߎ��A717���̓y�n�H�앨�����r�j�Ȃǂ������Ȃ��ꍇ�ɁA�N�Q�҂Ɣ�Q�҂ɂǂ̂悤�ɏ�����p��z�����邩�A�A�ŏI�I�ɐN�Q�҂��O�҂ɔ�p�S������Ƃ��Ă��A��Q�҂����������p���o�o����K�v�����邩�ɂ��āA��̓I�ȈႢ���o��B�{���ɂ��Č����A�x1�����L�҂ŁA�N�Q�ɂ��ߎ����Ȃ��ꍇ�A�Ȃ������ӔC�����ǂ��������ɂȂ�B
�@�����I�������́A�{������ׂ������A��������������̂ł���A�W�Q���̏��L�҂��{�����S���Ă�����ׂ���p����ӔC�ł͂Ȃ�����A�̈ӁE�ߎ�����ɂ����ɔF�߂���̂ł���B�{���ł́A���Ȃ��Ƃ��@�B�̉�́E�p����p10���~�́A�@�B�̏��L�҂ł���Ζ{�����R�ɕ��S���ׂ���p�ł��邩��A���ߎ��̏��L�҂ɕ��S�����Ă��悢���낤�B���̌���ł͔���E�������Ɠ��|�́i�C���j�s�א��������Ɏ^���ł���B�������A���������y��̉�p100���~�ɂ��Ă܂ŁA�܂����������_���ōm��ł��邩�͋c�_�̗]�n�����낤�B������������p�������o�����ҁi�x1�܂��͂x2�A�ꍇ�ɂ���Ăx1�x2�����ӔC�̉\�������邱�Ƃ͑O�q�̂Ƃ���j�Ɣp�����ɉ��̊W���Ȃ���Q�҂��ׂ�A�p�����̌��̏��L�҂ɁA���ꂪ������Ə�������錋�ʂɂ��Ă܂ŏd���ӔC��F�߂Ă��悢�悤�ɂ��v����B����͔p���������@�̍l�����Ƃ����a������B��ʉ�����ƁA����Ώ��L�҂ł��邱�ƂɌ��т��Ă���댯�͈̔͂ł́A�̈ӁE�ߎ����Ȃ��Ă������҂Ƃ��Ĕ�p�S���ׂ����A�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�l�@�̈ӂ܂��͉ߎ��ɂ���ď��L����N�Q�����҂́A�s�@�s�ׂɊ�Â����Q�����`�����i709���j���Ƃ��٘_���Ȃ��B���̐������ƕ����I�������Ƃ͗v���E���ʂ��قɂ��鐧�x�ł��邩��A���҂͕���������i����̐������������j�B�x1�`�x3�Ɍ̈ӂ�ߎ������邱�ƁA���Q���������Ă��邱�ƁA���Q�ƌ̈ӁE�ߎ�����s�ׂ̊Ԃɑ������ʊW�����邱�Ƃ𗧏ł���i�x1�̉ߎ�����ʊW�͔����ł���B�x2�ɂ͖��K�̌̈ӂ��F������ߎ������肻���ł��邪�A�x2�ɂ��Ă����ʊW���ے肳���]�n������B���̎R�т��S�~�̂ďꂾ�Ƃx3������������Ƃɂ�ނȂ��������A�x3�ɂ͉ߎ����Ȃ��ꍇ���A����߂ċH�ł͂��邪���肦�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��j�A�w�́A�x1�E�x2�ɑ��镨���I�������Ɠ����ɐӔC�Njy���ł��悤�B�����s�@�s�ׂɂ��A����߂Ċɂ₩�ȋq�ϓI�֘A��������v���Ƃ���Ɖ�����A��̔p�����̏������߂���֘A���͑��݂���̂ŁA�x���719��1���O�i�ŕs�^���A�ѐӔC�����ƂɂȂ�B�����܂Ŋ֘A���������g���Ȃ��������̂��Ă��i���Ƃ��A�O�c�B�������̂悤�Ȏ�ϓI�֘A�������j�A�x��̊e�s�@�s�ׂɂ���Ĉ�̑��Q���w�ɐ����Ă���A�����ꂪ�ǂꂾ���̊�^�������̂��s���Ȃ̂ŁA�s�@�s�ׂ̋����Ƃ��āA���Q�҂̓���ł��Ȃ��ꍇ�Ƃ݂āA719��1����i�œ������s�^���A�ѐӔC��Njy�ł���悤�Ɏv����i�����O�i�Ƃ̈Ⴂ�́A�x��̖ƐӁE���ӂ̔����������_�ɂ���j�B
�@�Ō�ɁA�w�Ƃ̊W�ŐӔC�S����҂̊Ԃł́A���L�҂̕��S���ׂ��댯�A�̈ӁE�ߎ����@�s�ׂ̒��x�Ȃǂ��l�����āA���S�̍ŏI�I���S�������邱�ƂɂȂ�B�����炭�x2�̍ŏI�I�ȕ��S���ł��d�����̂ƂȂ낤�B
- �����[�~�Ƃ̑R���_��̖��
�@�`�́A�b�����Ƃ����n�����̖{���y�n�����L���Ă����B�w�́A1956�N3��5���ɁA�����̓y�n���`�̑㗝�l�Ə̂���`�̓����̍Ȃa���甃���Ĉ��n�����A�Ȍ��̂Ƃ��Č��݂Ɏ���܂Ő�L���p�����Ă��邪�A�ړ]�o�L�葱�͍s���Ă��Ȃ������B�`���a�ɖ{���y�n���p�̑㗝�������^�����������w�ւ̔��p��m���ĒǔF�����Ƃ����������F�߂��Ȃ��B
�@���̌�A�b�y�n�ɂ��ẮA1967�N12��10���ɁA�`�́A�`��������̏o���ҁ��I�[�i�[�ła����\������߂�x1�ЂƂ̊ԂŁA�x1�Ђ����ҁA�`���g�����ҁA�ɓx�z��1000���~�Ƃ��鍪����ݒ�_���������A����̐ݒ�o�L���s�����B�`�E�x1�ԂɌ����ɔ�S�ۍ����������Ă������ǂ����͕s���ł��邪�A���̍�����ݒ�_�`�E�x1�̒ʖd���U�\���ł���Ƃ����؋��͂Ȃ��B
�@���y�n�ɂ��ẮA1975�N4��2���ɁA�`�́A�x2�ɔ��p���A�ړ]�o�L���s�����B
�@���y�n�ɂ��ẮA1977�N11��5���ɁA�`�́A�x1�ɔ��p���A�ړ]�o�L���s�����B
�@1998�N���A�{���y�n�̋ߕӂɃ��]�[�g���J�����v�悳�ꂽ���Ƃ��@���ɁA�{���y�n�̋A�����߂��鑈�������݉������B�w�͂`�E�a�ƎO�҂ł̘b���������������B�������A1956�N�����̔��p�W���ނ͎U�킵�A���̌o�ܓ��ɂ��Ă��W�҂̋L���͂��łɞB���ɂȂ��Ă����B�܂��A1990�N���̎��_�ł`�a�͂��łɓ����W���������Ă��āA����Ȍ�A�x1�Ђ̊����͂��ׂĂa�����L���Ă���B�w�ƍ��ӂłw�ɑ��Ĉ��̐ӔC�������Ă����`�́A�u�b�n�ɂ��Ăw�̎����ɂ�鏊�L���擾��F�߂邱�Ƃə傩�łȂ����A�b�n�̒���₷�łɔ��p�ς̉��n�E���n�ɂ��ẮA�����ɂ͂ǂ����悤���Ȃ��v�Ƃ����ԓx���̂������A�a�͂w�̎擾�����̎咣�𑈂����B
�@�����ŁA�w�́A�Ƃ肠�����A�b�n�ɂ��Ă̂݁A�`��ɁA1956�N3��5�����N�Z�_�Ƃ���20�N�Ԑ�L���p�����擾���������������A�Ǝ咣���āA�ړ]�o�L�葱�����̑i�����N���A�`�����킸�ɂw�̏��i���m�肵���B�����ŁA�w�́A���i�����Ɋ�Â���2000�N8��1���ɍb�n�̏��L���ړ]�o�L���s�������A�x1�̍�����̓o�L�͎c�����B
�@�w�́A����ɁA�x1�ɑ��čb�n��̂x1�̍�����ݒ�o�L�̖����ƕ��n�̏��L���ړ]�o�L���A�x2�ɑ��ĉ��n�̏��L���ړ]�o�L���A���ꂼ�ꋁ�߂������A�\���낤���B
�����[�~�ٔ����`�[���̔�����
����16�N7��14���������n�@
�����٘_�I��������16�N7��14��
���@�@�@�@�@�@�@�@��
��@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@1. �퍐Y1�́A�����ɑ��A�b�y�n�̍�����̓o�L�̖����葱��������B
�@2. �퍐Y2�́A�����ɑ��A���y�n�ɂ��āA���L���ړ]�o�L�葱��������B
�@3. �퍐Y1�́A�����ɑ��A���y�n�ɂ��āA���L���ړ]�o�L�葱��������B
���@���@�y�@�с@���@�R
���@����
�@�啶�ɓ��|�B
���@���_�Ɋւ��锻�f
1. �b�n�Ɋւ��鑈�_
�@������X�͒�s���Y�̎����擾�҂ł��邩��A397���́u���ҋy�r����ݒ�ҁv�ɂ�����Ȃ��ȏ�擾�����̌��������̂܂܂��Ă͂܂�AX�͍�����̕��S�̂Ȃ����L�����擾����Ǝ咣����B����ɑ��A�퍐�͍�������ݒ肳��Ȃ���40�N�߂����������u����X�̑ԓx�͍�����̑��݂�e�F�������̂Ƃ݂�ׂ��ł��邩��AX�͍�����̕��S�t�̓y�n�b���擾�����ɂƂǂ܂�Ǝ咣����B�����ŖړI���̐�L��S������Ȃ������Ƃ���������̓��ꐫ�ɂ��݂�ƁA����҂���݂�Ό���I�Ȏ������f�̎�i�ɂ��������Ő�L�҂���݂�ΊO�`�㍪����̑��݂�F������̂�����ł���B�������A�{���̎��Ăł�X�̐�L��������ɐ�s���Ă���_�ɂ��݂�ɁA�m����Y1�͎������f���e�Ղł͂Ȃ��������Ƃ͔ے�ł��Ȃ����̖̂{�����Ă���͖W�Q�r������������Ȃǂ��Ė{���Ɏ������f���s�\�ł�����������̓I�Ȏ�����炩�łȂ��̂ł���B���������āAX��Y1�ɑ��ĐϋɓI�ɍ�����̑��݂�e�F�������̓��i�̎���̖�������A�P�ɒ����Ԃ̌o�߂Ƃ�������݂̂�������X��������̑��݂�e�F�����Ƃ݂�ׂ��ł͂Ȃ��B�܂��A�퍐�̒�����R�@����Ɩ{�����Ăł͏�ʂ��قȂ�̂ł����āA�����������X��������̑��݂�e�F�����Ɖ�����ׂ��ł͂Ȃ��B
�@�����X�͍�����̕��S�̖����b�n�̏��L�����擾����Ɖ�����̂������ł���B
2. ���n�Ɋւ��鑈�_
�@�����́AY2��X�̎��������ɂ��A���p�擾�ɂ����铖���҂Ɠ��l�̗���ɗ����Ă���ƌ����A177���́u��O�ҁv�ɂ����炸�A����������X�͓o�L�Ȃ�����Y2�Ɏ����ɂ�鏊�L���̎擾��R�ł���Ǝ咣����B����ɑ��퍐�́AX�̎������p���̎������咣����B�m���ɔ퍐�̎咣�ɂ���悤�ɂ����錠�������̌����̖@���̎�|��F�߂����Ⴊ�ߋ��ɑ��݂���B�������A���������������x�͎�����Ԃ̑��d�Ƃ����Ƃ���ɂ��̎�Ⴊ������Ă���̂ł��邩�玞�����p�������������̌����ɂ����点��̂͑Ó��łȂ��B�܂��A�������1��2���̐M�`���̌����̈�ތ^�Ƃ��Ă����F�߂����̂ł���B�Ƃ���A�M�`���㌠�������ȑO�ɍs�g���ׂ��ł��������Ƃ��K�v�ł���Ɖ�����̂������ł���Ƃ���A�P�ӂŐ�L���n�߂��҂��������p���Ȃ��ׂ��Ȃ̂́A���҂���L�҂̏��L����ے肵�Ă������_�ł���B����ȑO�Ŏ������p����ƌ����Ă��A�P�Ӑ�L�҂͎��Ȃ̌���������Ǝv���Ă���̂ł��邩��A���p��v������͍̂��ł���B
�@�{���ł�X�̐�L��186��1������P�ӂƐ��肳���B�����āA�P�ӂ����L�ߎ��Ƃ�����������̎҂̉��p������������ׂ��Ƃ͓��ꂢ���Ȃ��B
�@���������āA�{���ł͔퍐�̎咣����悤�ɓ��@���̓K�p������ʂƔF�߂邱�Ƃ͂ł����AX�͉��n�̎����擾�����p�ł���B
3. ���n�Ɋւ��鑈�_
�@������1977�N��Y1���n�̈ړ]�o�L���s�������_���N�Z�_�Ƃ��āA20�N�Ԃ̍Ď����擾���咣����B����ɑ��A�퍐�͕���15�N10��31�����������a36�N7��20���������̗p�������R��j���������Ƃ���A�ēx�̎����擾��F�ߎ����I�Ɏ����̋N�Z�_�����炷���ƂɂȂ鏺�a36�N������ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ���B�������A����15�N�����̎��ĂƖ{���̎��Ăł͏�ʂ��قȂ�̂ł���B����15�N�����̎��Ăł́A�����擾�҂͍Ď����擾�O�ɓo�L���Ȃ��Ċm��I�ɏ��L�����擾���Ă���B�������͂��̂悤�Ȏ��Ă̓��ꐫ�ɂ��݁A�����擾�҂͊m��I�ɏ��L�����擾���Ă���̂ł��邩��A����҂Ƃ̊W�ɂ����Ă���ƋN�Z�_���قɂ���ʌ̏��L���̎����擾���咣�ł���Ƃ��邱�Ƃ́A�������p���҂ɂ�鎞�����Ԃ̋N�Z�_�̔C�ӂ̑I���������Ȃ��Ƃ��锻��i�ňꔻ��35�E7�E27���W14�E10�E1871�Łj�̎�|�ɔ����邵�A����̏��ł����L���̎擾�����̔��˓I���ʂƂ���397���ɂ�����Ȃ����ƂɂȂ�Ƃ��āA�ēx�̎擾�������咣���A���p���邱�Ƃ͋����Ȃ��Ɖ��������̂Ǝv����B�Ƃ���AX���Ď����擾�܂łɓo�L������������̉��p�����Ă��Ȃ��{�����Ă͕���15�N�����̎˒��O�ł���B�ނ���A�{�����Ă͕��n�Ɋւ��镔���ł́A�ēx�̎����擾��F�߂����a36�N�����̎��ĂƏ�L�̓_�ŋ��ʂ��Ă���A�������P����X�̍ēx�̎����擾�̐�����F�߂�Ɖ�����̂������ł���B
�@���������āAX��1999�N�ɕ��y�n�������擾����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ٔ����ٔ����@�@�S�{�Ϗ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ٔ����@�@�t������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�є��a
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H���G��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ǍK�T
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�ؗS��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R�݂Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�c����
- �U���X���@���̃p�u���V�e�B�̌����H
�@�w1�́A�����ȓ��{�뉀�̏��L�҂Ŕq�ϗ�������Ē�������Ă���B���̍ہA�뉀�̓�������ɂ́A�u�{�뉀�̎B�e�͂������������v�Ƃ����\�����\���Ă����B�w2�́A�|�\���u���Y�v�����L���A�|���d�����Y���g���ĂP�X�e�[�W50���~�O��̉��V���[���s���Ă���B������A�w2�����Y��A��Ăw1�̒뉀��K�ꂽ�Ƃ���A��X�����킹���|�X�^�[�����̔��Ǝ҂x���A�w1�w2�̋����邱�ƂȂ��A���w�i�ɂ��낢�ł��鑾�Y�̎ʐ^���B�e�����B���̎ʐ^�����܂�ɗǂ��ł��Ă����̂ŁA�x�́A�{���|�X�^�[�Ƃ��Ĕ���o���A�傫�ȗ��v�Ă���B
�@�w�炪�A�x�ɖ{���|�X�^�[�̔̔��̍��~�߂ƁA�̔��������ɂ��đ��Q���������߂��B
�@�{���ƃM�����b�v���[�T�[�����̈Ⴂ�ɗ��ӂ��āA�w��̐������ǂ����f����ׂ�����_���Ȃ����B
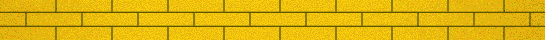
![]()
![]()