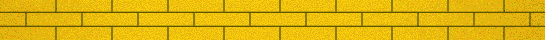
俀侽侽係擭搙屻婜徏壀僛儈専摙栤戣廤
- 侾侽寧俇擔偺栤戣乮挿暥乯偲専摙帠崁丒曗懌僐儊儞僩
丂仸搒崌偱嶍彍偟傑偟偨丅
-
亂庢傝忋偘偨敾椺偵偮偄偰偺専摙帠崁亃
丂侾丂暯惉俆擭敾寛偱嵟崅嵸偑傕偭傁傜嬧峴庢堷栺掕彂偺柶愑忦崁偺岠椡偺傒傪埖偄丄柉朄係俈俉忦偺揔梡傪栤戣偵偟側偐偭偨偺偼側偤偐丅
丂俀丂暯惉俆擭敾寛偵懳偡傞斸敾揰傪嫇偘傛丅
丂俁丂暯惉俆擭敾寛偱栤戣偵側偭偨柶愑忦崁偼丄徚旓幰宊栺朄巤峴屻偼丄摨朄偲偺娭學偱岠椡偑栤戣偵側傞偐丅傑偨丄嬧峴嬈奅偼丄嬥梈惂搙挷嵏夛偵偍偗傞揹巕帒嬥堏摦朄惂偺怰媍傪庴偗偰丄暯惉俇擭係寧偵僇乕僪婯掕帋埬偺巟暐柶愑忦崁乮侾侽忦俀崁乯偵偮偒壓婰偺傛偆側夵惓傪峴偭偨丅
丂乽摉峴偑丄僇乕僪偺揹帴揑婰榐偵傛偭偰丄巟暐婡傑偨偼怳崬婡偺憖嶌偺嵺偵巊梡偝傟偨僇乕僪傪摉峴偑岎晅偟偨傕偺偲偟偰張棟偟丄擖椡偝傟偨埫徹偲撏弌偺埫徹偲偺堦抳傪妋擣偟偰梐嬥偺暐栠偟傪偟偨偆偊偼丄僇乕僪傑偨偼埫徹偵偮偒婾憿丄曄憿丄搻梡偦偺懠偺帠屘偑偁偭偰傕丄摉峴偍傛傃採実愭偼愑擟傪晧偄傑偣傫丅偨偩偟丄偙偺暐栠偟偑婾憿僇乕僪偵傛傞傕偺偱偁傝丄僇乕僪偍傛傃埫徹偺娗棟偵偮偄偰梐嬥幰偺愑偵婣偡傋偒帠桼偑側偐偭偨偙偲傪摉峴偑妋擣偱偒偨応崌偺摉峴偺愑擟偵偮偄偰偼丄偙偺偐偓傝偱偼偁傝傑偣傫乿丅
丂乮乽僷僜僐儞摍偺抂枛婡傪巊梡偟偨埶棅偵傕偲偯偔怳崬丒怳懼庢堷偵娭偡傞婯掕乲帋埬乴俁忦侾崁傕摨庯巪乯丅
丂夵惓屻偺柶愑忦崁偼徚旓幰宊栺朄忋栤戣偑側偄偐丅
丂係丂暯惉俆擭敾寛偑柉廤搊嵹偱偼側偄乮怴敾椺偲偼昡壙偝傟偰偄側偄乯偺偼側偤偐丅
丂俆丂夁幐憡嶦偵傛偭偰嬧峴偑徚旓婑戸忋偺梐嬥曉娨嵚柋傪堦晹柶愑偝傟傞偲偄偆愢偼丄偳偆偄偆儊僇僯僘儉乮朄揑峔惉乯偵傛傞偺偐丅妋掕妟偺嬥慘嵚柋偼晄壜峈椡偡傜柶愑帠桼偲偱偒側偄偙偲偲惍崌惈偑偁傞偐丅
丂俇丂暯惉侾俆擭敾寛偱丄嬧峴偑柶愑忦崁傪庡挘偟側偐偭偨偺偼偳偆偟偰偐丅
丂俈丂暯惉侾俆擭敾寛偑柉廤搊嵹偝傟偰敾椺偲偟偰堄媊傪桳偡傞偺偼偳偆偄偆揰偐丅
丂俉丂揹巕徚旓幰宊栺朄俁忦乮俀侽侽侾擭乯偼偙偺庬偺朄棩栤戣偵塭嬁傪媦傏偡偐丅
丂俋丂巜栦乮嬤枹棃揑偵偼俢俶俙忣曬乯偵傛傞梐嬥幰偺摿掕偑媄弍揑偵壜擻偱偡偱偵堦晹嬥梈婡娭偱偼偦傟偑巊梡偝傟偩偟偰偄傞丅偙偺傛偆側忬嫷偱丄廬棃宆偺係寘偺埫徹斣崋曽幃傪巊梡偟懕偗傞偙偲偼丄僔僗僥儉忋偺埨慡懳嶔晄旛偺夁幐偑嬧峴偵偁傞偲偼尵偊側偄偐丅
亂帠椺栤戣亃
丂倃姅幃夛幮偑倄嬧峴偵桳偡傞晛捠梐嬥岥嵗偐傜丄僉儍僢僔儏僇乕僪傪巊偭偰俆侽侽枩墌偑堷偒弌偝傟丄梐嬥巆崅偼侾侽侽侽墌偵側偭偨丅師偺応崌丄倃偼倄偵懳偟偰丄俆侽侽枩墌偺暐栠偟傪惪媮偱偒傞偐丅側偍丄倄嬧峴偼丄岥嵗奐愝偺嵺偵丄忋婰僇乕僪婯掕帋埬偲摨條偺柶愑忦崁傪娷傓嬧峴庢堷栺掕彂傪倃幮偵岎晅偟偰偄偨傕偺偲偡傞丅
丂(1) 倄嬧峴偺屭媞僨乕僞偑壗幰偐偵傛偭偰僴僢僉儞僌偝傟偰埫徹斣崋僨乕僞偑搻傑傟丄婾憿偝傟偨僇乕僪偲埫徹斣崋傪梡偄偰堷偒弌偟偑側偝傟偨応崌丅
丂(2) 倄嬧峴偺屭媞僨乕僞傪丄倄嬧峴偑僔僗僥儉愝寁傪埶棅偟偨俙幮偺俽俤偑搻傫偱丄婾憿僇乕僪傪梡偄偰堷偒弌偟傪偟偨応崌丅
丂(3) 倄嬧峴偑彂棷偱憲晅偟偨僉儍僢僔儏僇乕僪偑梄憲搑拞偱搻傑傟丄倃幮偑埫徹斣崋偲偟偰偄偨戙昞揹榖斣崋傪梡偄偰堷偒弌偟偑側偝傟偨応崌丅
丂(4) 倄嬧峴偑晛捠梄曋偱憲晅偟偨僉儍僢僔儏僇乕僪偑倃幮偺梄曋庴偗偐傜搻傑傟丄倃幮偑埫徹斣崋偲偟偰偄偨戙昞揹榖斣崋傪梡偄偰堷偒弌偟偑側偝傟偨応崌丅
丂(5) 倃幮偺廬嬈堳俛偑擖弌嬥偟偰偄傞偲偙傠傪搻傒尒偨俠偑丄埫徹斣崋傪悇棟偟丄俛偐傜搻傫偩僉儍僢僔儏僇乕僪傪巊偭偰丄堷偒弌偟傪偟偨応崌丅
丂(6) 倃幮偺廬嬈堳俛偑栭娫俠俢婡偱擖弌嬥傪偟偰偄偨偲偙傠丄嫮搻俢偑俛傪恘暔偱嫼偟偰僉儍僢僔儏僇乕僪傪扗偄丄埫徹斣崋傪暦偒弌偟偰丄堷偒弌偟傪偟偨応崌丅
-
亂庢傝忋偘偨敾椺偵偮偄偰偺妋擣帠崁丒専摙帠崁亃
丂丒倃侾偼傑偭偲偆側掞摉尃庢摼幰偐丅
丂丒倃侾偲倃俀偲偺慽徸偑暪崌偝傟偨宱堒丅
丂丒杮審偱壖偵倃俀偑傑偭偲偆側強桳尃庢摼幰偱偁偭偨偲偡傟偽丄倃侾偺惪媮偵塭嬁偼惗偠側偐偭偨偐丅
丂丒杮審偱倃侾偺惪媮偑婞媝偝傟偨寢壥丄倃侾偑屻弴埵掞摉尃偺幚峴傪怽偟棫偰傟偽偳偆偄偆寢壥偵側傞偐丅
丂丒杮審偱俙偑柍帒椡忬懺偱偁偭偨応崌偵偼丄倃侾偵偼懠偵嵦傞曽朄偼側偐偭偨偐丅
亂墳梡揑側専摙栤戣亃
丂倄偼丄俙偵俁侽侽侽枩墌傪戄偟晅偗丄俙強桳偺帪壙俀侽侽侽枩墌偺杮審峛晄摦嶻偲帪壙侾俆侽侽枩墌偺壋晄摦嶻偵倄偺偨傔偺嫟摨掞摉尃偺愝掕傪庴偗丄偦傟偧傟掞摉尃愝掕搊婰傪偟偨丅偦偺屻丄峛晄摦嶻偵偮偄偰偼倃侾偑丄壋晄摦嶻偵偮偄偰偼倃俀偑丄偦傟偧傟俙偵懳偡傞戄嬥嵚尃傪旐扴曐嵚尃偲偡傞壖搊婰扴曐尃傪庢摼偟偨丅倄偑俙偵懳偡傞戄晅嵚尃偺徚柵帪岠傪拞抐偡傞偙偲偺側偄傑傑丄俆擭偺彜帠徚柵帪岠婜娫偑宱夁偟偨丅偦偺屻丄倃侾偼丄壖搊婰扴曐尃偺巹揑幚峴偺庤懕傪峴偄丄強桳尃庢摼偺杮搊婰傪宱偨偑丄倃俀偼枹偩幚峴偵帄偭偰偄側偄丅偙偺応崌丄倃侾偍傛傃倃俀偼丄倄偺俙偵懳偡傞嵚尃偺徚柵帪岠傪庡挘偡傞偙偲偑偱偒傞偐丅
丂仸岥摢偱捛壛偟偨偝傜側傞墳梡栤戣
丂丂丒倃侾偑壖搊婰扴曐尃偺巹揑幚峴傪峴偭偨偺偑丄倄偺旐扴曐嵚尃偺帪岠姰惉帪揰傛傝慜偐屻偐偱寢榑偵塭嬁偑偱側偄偐丅偲傝傢偗丄巹揑幚峴帪偵愭弴埵掞摉尃幰倄偺旐扴曐嵚尃妟傪峊彍偟偰惔嶼嬥妟傪掕傔偨倃侾偑屻偵旐扴曐嵚尃偺帪岠庢摼傪墖梡偡傞偺偼丄帺傜偺愭峴峴堊偲柕弬偟怣媊懃堘斀偲側傜側偄偐丅
丂丒倃傜偺庢摼偟偨尃棙偑丄壖搊婰扴曐尃偱偼側偔丄忳搉扴曐尃偩偭偨偲偡傞偲偳偆偐丅忳搉扴曐偺朄揑峔惉偵傛偭偰堘偄偑惗偠側偄偐丅
-
亂庢傝忋偘偨敾寛偵娭偡傞妋擣帠崁亃
丂侾丂杮審宊栺偵偮偄偰庁抧庁壠朄偑扨弮偵揔梡偝傟傞偲偡傞偲偳偆側傞偐丅
丂俀丂攋婞帺敾偲攋婞嵎栠偼偳偙偑堘偆偐丅
丂俁丂崌堄夝彍偺応崌偱傕揮庁恖偵懳峈偱偒傞応崌偼偳傫側応崌偐丅
丂係丂捓戄庁宊栺傪捓庁恖偺捓椏晄暐偄偺嵚柋晄棜峴傪棟桼偵夝彍偡傞応崌丄捓戄恖偼丄揔朄側揮庁恖偵懳偟偰丄帺傜偵揮戄椏傪巟暐偊偲惪媮偱偒傞偐丅偦偺傛偆側峴摦傪嵦傞偙偲側偔夝彍尃傪桳岠偵峴巊偟偨応崌丄捓戄恖偼揮庁恖偵懳偟偰丄栚揑晄摦嶻偐傜偺戅嫀傪媮傔傞偙偲偑偱偒傞偐丅
亂墳梡揑側専摙栤戣亃
丂倃偼2000擭4寧偵俙偺強桳偡傞杮審搚抧丒寶暔乮帪壙侾壄墌乯偵偮偒掞摉尃偺愝掕傪庴偗偰俙偵5000枩墌傪梈帒偟偨丅偦偺屻2002擭4寧1擔偵丄俙偺暿偺嵚尃幰俛偼丄俙偵懳偟偰3000枩墌偺戄嬥嵚尃傪桳偟偰偄偨偲偙傠丄俙偑棙懅偺巟暐偄傪懾傜偣偨偺偱丄俙偐傜杮審寶暔傪寧妟捓椏10枩墌丄揮戄帺桼丄婜娫3擭娫偲偄偆摿栺晅偱庁傝庴偗乮捓椏偼俛偺俙偵懳偡傞棙懅嵚尃偲憡嶦偡傞巪偺摿栺傕偁偭偨乯丄捓庁寶暔傪摨擔倄偵揮戄偟丄堷偒搉偟偨丅揮戄庁宊栺偼丄婜娫3擭娫丄捓椏寧妟100枩墌偱偁偭偨丅
丂倃偼丄柉朄395忦扐彂偵傛傞嵓奞揑捓戄庁偺夝彍惪媮偺慽偊傪婲偙偡偙偲傕峫偊偨偑丄偦偺摴偼嵦傜偢丄2004擭2寧丄杮審搚抧丒寶暔偵偮偄偰掞摉尃偺幚峴傪怽棫偰丄2004擭8寧偵帺傜攦偄庴偗丄強桳尃堏揮搊婰傪峴偭偨丅
丂倃偼丄捈偪偵俛偵懳偟偰丄杮審捓戄庁宊栺偺峏怴嫅愨偺堄巚昞帵傪峴偭偨乮庁抧庁壠朄27忦1崁偍傛傃抁婜捓戄庁偺応崌偵偼庁抧庁壠朄28忦偺峏怴嫅愨丒夝栺偺惓摉帠桼偑娚傗偐偵擣傔傜傟傞偲偡傞嵟敾徍榓39擭6寧19擔柉廤18姫5崋795暸傪嶲徠乯丅2005擭4寧偵丄倃偼丄倄偵懳偟偰丄強桳尃偵婎偯偔杮審寶暔偺柧搉偟傪惪媮偡傞偙偲偑偱偒傞偐丅
- 柉朄724忦屻抜偺婜娫惂尷丂専摙壽戣
亂慜採栤戣亃
丂侾丂彍愃婜娫偼偳偆掕媊偝傟傞偐丅
丂俀丂彍愃婜娫偲徚柵帪岠偼偳偺揰偑堎側傞偐丅
丂俁丂偁傞婜娫惂尷婯掕傪丄徚柵帪岠婜娫偐彍愃婜娫偺偄偢傟偐偲偡傞怳傝暘偗偺婎弨偼壗偐丅
亂杮審慽徸偵偮偄偰亃
丂侾丂杮審慽徸偼丄徍榓27擭偵梊杊愙庬帠屘偑敪惗偟偰偐傜22擭屻偵採婲偝傟偰偄傞偑丄偙偺傛偆偵旕忢偵挿婜偵傢偨偭偰慽偊偑採婲偝傟側偐偭偨棟桼偼偳偆偄偆傕偺偩偭偨偺偐丅
丂俀丂彍愃婜娫偺惈奿傪丄乽朄揑埨掕惈偺尒抧傪戞堦媊揑偵廳梫帇偟丄旐奞幰懁偺擣幆偄偐傫傪栤傢偢丄堦掕偺帪偺宱夁偵傛偭偰朄棩娭學傪妋掕偝偣傞偨傔丄惪媮尃偺懚懕婜娫傪夋堦揑偵掕傔傞傕偺乿偩偲峫偊傞偲丄柍擻椡幰偵朄掕戙棟恖偑偄側偐偭偨偨傔尃棙峴巊乮帪岠拞抐慬抲傪嵦傞偙偲乯偑偱偒側偐偭偨偐偳偆偐偼丄婜娫偺恑峴偵塭嬁偟側偄偺偱偼側偄偐丅
丂俁丂儗僕儏儊俈暸偼丄乽杮帠椺偼丄丒丒丒抶敪揑懝奞丒宲懕揑懝奞偲傒偰張棟偡傞偙偲偑壜擻側帠埬偱偁偭偨乿偲偟偰偄傞偑丄朄掛堄尒傪丄偦偺傛偆偵棟夝偡傞偙偲偼壜擻偐丅壖偵偙傟偑晄壜擻偱偁偭偨偲偡傞偲丄嵟嶰彫敾暯惉侾俇擭係寧俀俈擔柉廤俆俉姫係崋侾侽俁俀暸偺拀朙恛攛帠審敾寛傗嵟擇彫敾暯惉侾俇擭侾侽寧侾俆擔嵸帪侾俁俈俁崋係暸偺悈枔昦帠審敾寛乮屻弎偵娭學晹暘傪敳悎乯偲偺娭學偼偳偆側傞偐丅
丂係丂壨崌怢堦嵸敾姱偺斀懳堄尒偵傛傟偽丄杮審偱偼丄晝曣偺懝奞攨彏惪媮傕擣傔傜傟傞偙偲偵側傞偺偐丅
乽戞係丂暯惉侾俁擭乮庴乯戞侾侾俈俀崋忋崘戙棟恖搒抸峅傎偐偺忋崘庴棟怽棫偰棟桼戞俆偵偮偄偰
侾丂旐忋崘恖傜偺忋崘恖傜偵懳偡傞惪媮乮慜婰戞俀偱敾帵偟偨偲偙傠偵傛傝婞媝偝傟傞傋偒晹暘傪彍偔丅乯偵偮偄偰偼丄崙壠攨彏朄係忦丄柉朄俈俀係忦屻抜強掕偺彍愃婜娫偺揔梡偺桳柍偑栤戣偲側傞偲偙傠丄尨怰偼丄偦偺揔梡傪斲掕偟偨丅
丂忋崘恖傜偺榑巪偼丄尨怰偺忋婰敾抐偼丄忋婰奺婯掕偺夝庍揔梡傪岆偭偨傕偺偱偁傝丄朄椷偵堘斀偡傞巪傪庡挘偡傞傕偺偱偁傞丅
俀丂偦偙偱丄埲壓丄偙偺揰偵偮偄偰専摙偡傞丅
乮侾乯柉朄俈俀係忦屻抜強掕偺彍愃婜娫偼丄乽晄朄峴堊僲帪儓儕擇廫擭乿偲婯掕偝傟偰偍傝丄壛奞峴堊偑峴傢傟偨帪偵懝奞偑敪惗偡傞晄朄峴堊偺応崌偵偼丄壛奞峴堊偺帪偑偦偺婲嶼揰偲側傞偲峫偊傜傟傞丅偟偐偟丄恎懱偵拁愊偡傞暔幙偑尨場偱恖偺寬峃偑奞偝傟傞偙偲偵傛傞懝奞傗丄堦掕偺愽暁婜娫偑宱夁偟偨屻偵徢忬偑尰傟傞幘昦偵傛傞懝奞偺傛偆偵丄摉奩晄朄峴堊偵傛傝敪惗偡傞懝奞偺惈幙忋丄壛奞峴堊偑廔椆偟偰偐傜憡摉偺婜娫偑宱夁偟偨屻偵懝奞偑敪惗偡傞応崌偵偼丄摉奩懝奞偺慡晹枖偼堦晹偑敪惗偟偨帪偑彍愃婜娫偺婲嶼揰偲側傞偲夝偡傞偺偑憡摉偱偁傞丅偙偺傛偆側応崌偵懝奞偺敪惗傪懸偨偢偵彍愃婜娫偑恑峴偡傞偙偲傪擣傔傞偙偲偼丄旐奞幰偵偲偭偰挊偟偔崜偱偁傞偩偗偱側偔丄壛奞幰偲偟偰傕丄帺屓偺峴堊偵傛傝惗偠摼傞懝奞偺惈幙偐傜傒偰丄憡摉偺婜娫偑宱夁偟偨屻偵懝奞偑敪惗偟丄旐奞幰偐傜懝奞攨彏偺惪媮傪庴偗傞偙偲偑偁傞偙偲傪梊婜偡傋偒偱偁傞偲峫偊傜傟傞偐傜偱偁傞丅尨怰偺敾抐偼丄埲忋偺庯巪傪偄偆傕偺偲偟偰丄惀擣偡傞偙偲偑偱偒傞丅榑巪偼嵦梡偡傞偙偲偑偱偒側偄丅
乮俀乯忋婰尒夝偵棫偭偰杮審傪傒傞偲丄杮審姵幰偺偦傟偧傟偑悈枔榩廃曈抧堟偐傜懠偺抧堟傊揮嫃偟偨帪揰偑奺帺偵偮偄偰偺壛奞峴堊偺廔椆偟偨帪偱偁傞偑丄悈枔昦姵幰偺拞偵偼丄愽暁婜娫偺偁傞偄傢備傞抶敪惈悈枔昦偑懚嵼偡傞偙偲丄抶敪惈悈枔昦偺姵幰偵偍偄偰偼丄悈枔榩枖偼偦偺廃曈奀堟偺嫑夘椶偺愛庢傪拞巭偟偰偐傜係擭埲撪偵悈枔昦偺徢忬偑媞娤揑偵尰傟傞偙偲側偳丄尨怰偺擣掕偟偨帠幚娭學偺壓偱偼丄忋婰揮嫃偐傜抶偔偲傕係擭傪宱夁偟偨帪揰偑杮審偵偍偗傞彍愃婜娫偺婲嶼揰偲側傞偲偟偨尨怰偺敾抐傕丄惀擣偟摼傞傕偺偲偄偆偙偲偑偱偒傞丅偙偺揰偵娭偡傞忋崘恖傜偺榑巪傕嵦梡偡傞偙偲偑偱偒側偄丅乿
亂墳梡揑側専摙栤戣亃
丂壓婰偺婰弎偼丄拞崙恖嫮惂楢峴丒嫮惂楯摥帠審偵娭偡傞暉壀崅敾暯惉侾俇擭俆寧俀係擔偺擣掕晹暘偐傜偺堦晹堷梡偱偁傞乮堦晹廋惓傪巤偟丄撉傒傗偡偔傕偟偰偁傞乯丅偙傟傜偺擣掕傪慜採偵偡傞偲偒丄旐奞幰偱偁傞尨崘偑暯惉侾俀擭乮俀侽侽侽擭乯俆寧侾侽擔偵採婲偟偨崙摍偵懳偡傞懝奞攨彏惪媮偼丄彍愃婜娫偺宱夁偵傛傝婞媝偝傟傞偙偲偵側傞偐丄偦傟偲傕擣梕偝傟傞偙偲偵側傞偐丅
乽乮俆乯杮審偵偍偗傞摿抜偺帠忣偲偟偰偺峫椂梫慺偺桳柍
丂慜婰擣掕敾抐媦傃揔媂宖婰偟偨徹嫆偵傛傟偽丄師偺偲偍傝擣掕敾抐偝傟傞丅
傾丂旐奞偺恟戝惈偲峴堊懺條偺埆幙惈亅媬嵪偺昁梫惈亅
乮傾乯杮審偼丄暯壐側曢傜偟傪偟偰偄傞拞崙恖傪丄朶椡傗媆悝傪梡偄偰壠懓偺傕偲偐傜愗傝棧偟丄揋崙偵嫮惂揑偵楢峴偟偨忋丄嫮惂揑偵楯摥偵廬帠偝偣偨恟偩偟偔恖椣偵傕偲傞晄朄峴堊偱偁傞丅
乮僀乯杮審慽徸偲捈愙偺娭學偼側偄偑丄嫮惂揑偵楢峴偝傟偨忋丄嫮惂揑偵楯摥偵廬帠偝偣傜傟偨偲偄偆堄枴偱偼摨條偺嫬嬾偵偁偭偨俥乮尨崘偺堦恖乯偼丄嫮惂楯摥偵懴偊寭偹偰丄廔愴捈慜丄崜姦偺杒奀摴嶳拞偵摝朣偟丄偦偺屻愴憟偑廔寢偟偨偙偲傕抦傜偢丄摨嶳拞偱侾俁擭娫傕偺摝朣惗妶傪夁偛偟偨丅摨恖偵戙昞偝傟傞偲偍傝丄堏擖偝傟偨拞崙恖楯摥幰偼丄擔杮恖偵挊偟偔堌晐偟丄嫲晐偟偰偄偨丅
乮僂乯堦怰尨崘傜傕摨偠偔拞崙偐傜堏擖偝傟偰偒偨丅搫煒偱偼揹棳傪捠偟偨揝忦栐偱埻傑傟偨嬫堟偱丄摝朣偟傛偆偲偡傞偲廵偱寕偨傟傞摍丄桝憲搑拞偺忬嫷偼丄嬌傔偰弒楏側傕偺偱偁偭偨丅偦偺嫲晐偼揷愳丄嶰抮偺奺帠嬈強偵摓拝屻傕慛柧側婰壇偲偟偰徚偊側偐偭偨偱偁傠偆偙偲偼憐憸偵擄偔側偄丅
乮僄乯壛偊偰丄堦怰尨崘傜偼丄俤乮尨崘偺堦恖乯偑岺帠梡嬶偱墸傝偮偗傜傟偰戝戁崪傪崪愜偝偣傜傟偨偙偲偱戙昞偝傟傞偲偍傝丄揷愳峼嬈強傗嶰抮峼嬈強偵偍偄偰傕丄朶椡偲朶尵偵傛傝楆廬揑忬懺偱楯摥偵廬帠偝偣傜傟偨丅
僀丂彍愃婜娫撪偵尃棙峴巊偡傞偙偲偺崲擄惈
乮傾乯婣崙慜
倎丂堦怰尨崘傜偲堦怰旐崘夛幮偲偺娫偱偼宊栺偑寢偽傟偰偄側偐偭偨丅
倐丂堦怰尨崘傜偼丄堦掕婜娫傪揷愳峼嬈強傗嶰抮峼嬈強偱夁偛偟偨偙偲偐傜丄嶰堜傗嶰抮偺柤慜傪妎偊偰偄傞偑丄惓幃偵偼丄帺暘偑壗偲偄偆朄恖偱摥偐偝傟偨偺偐傕惓妋偵嫵偊傜傟偰偄側偄丅
們丂擔杮偵忋棨屻偼偦偺傑傑捈愙帠嬈応偵桝憲偝傟丄埲屻奜弌偑嬛偠傜傟偰偄偨偺偱丄応強偵偮偄偰傕惓妋側婰壇偼側偄丅
倓丂晄朄峴堊偺廔椆帪乮侾俋係俆擭乮徍榓俀侽擭乯俉寧俀係擔乯偐傜摨擭侾侾寧俀俀擔丄帠嬈応傪弌敪偟丄摨寧俀係擔丄屘嫿傊婣傞傋偔慏偵忔慏偡傞傑偱偵偼栺俁儢寧偺婜娫偑偁傞偑丄傾偺彅帠忣傪姩埬偡傞偲丄偦偺娫偵忋婰晄朄峴堊偵婎偯偔惪媮尃傪峴巊偟摼傞忬懺偵偼側偐偭偨偟丄偦偺偨傔偺弨旛偲偟偰丄壛奞幰柤傪挷傋偨傝丄攚宨帠忣傪挷嵏偟偨傝偡傞偙偲傕帠幚忋晄壜擻偱偁偭偨丅
乮僀乯婣崙屻
倎丂堦怰尨崘傜偼丄偦偺傛偆側忬懺偺拞丄偲傞傕偺傕偲傝偁偊偢丄偁傢偨偩偟偔婣崙偟偨丅
倐丂摉帪丄拞崙偱偼婛偵撪愴偑婲偙傝巒傔偰偄偨丅堦怰尨崘傜偼丄偄偢傟傕戝棨偵廧傫偱偍傝丄拞壺恖柉嫟榓崙偺崙柉偲側偭偨偑丄擔杮偼丄摨崙傪彸擣偣偢丄椉崙偼崙岎偑搑愨偟偨丅
們丂侾俋俈俀擭乮徍榓係俈擭乯俋寧俀俋擔丄擔拞嫟摨惡柧傊偺彁柤偵傛傝丄傛偆傗偔椉崙偺崙岎偼夞暅偟偨偑丄偦偺屻傕丄拞壺恖柉嫟榓崙偱偼丄侾俋俉俇擭乮徍榓俇侾擭乯俀寧侾擔偵岞柉弌崙擖崙娗棟朄偑巤峴偝傟傞傑偱丄巹帠偵傛傞弌崙偑擣傔傜傟偢丄偦偺屻傕丄帺桼側搉峲偼帠幚忋崲擄側忬懺偑懕偄偨丅
倓丂偟偨偑偭偰丄堦怰尨崘傜偼丄媞娤揑偵傒偰丄彮側偔偲傕侾俋俉俇擭俀寧侾擔慜傑偱偼丄偦偺尃棙傪峴巊偡傞偙偲偑尰幚栤戣偲偟偰帠幚忋崲擄偱偁偭偨丅
僂丂徹嫆偲偺娭學摍
乮傾乯倎乲侾乴侾俋係係擭師姱夛媍寛掕偺幚巤嵶栚偱偁傞壺恖楯柋幰撪抧堏擖庤懕偼丄拞崙恖偑廇嬈抧偵摓拝偟偨帪偵偼丄帠嬈庡偼丄娗妽偺崙柉怑嬈巜摫強偵丄弌恎抧丄巵柤丄擭楊傪婰嵹偟偨柤曤傪採弌偡傞偙偲傪媊柋晅偗偰偄偨丅
乲俀乴傑偨丄婣崙偡傞帪偵偼丄傗偼傝柤曤傪嶌惉偟丄壓慏抧丄梊掕擔摍傪挕晎導丄撪柋徣丄岤惗徣媦傃戝搶垷徣偵曬崘偡傋偒偙偲偲偝傟偰偄偨丅
乲俁乴偦偟偰丄堦怰旐崘夛幮偲旐峊慽恖崙偼丄廔愴偺帪揰偱偼丄偄偢傟傕丄堦怰尨崘傜偑堦怰旐崘夛幮偱摥偄偨偙偲傪徹偡傞柤曤傪曐娗偟偰偄偨丅
倐丂堦怰尨崘傜偵偼屬梡宊栺彂摍偼岎晅偝傟偰偄側偄偐傜丄忋婰柤曤偼丄堦怰尨崘傜偑擔杮偵嫮惂楢峴偝傟丄堦怰旐崘夛幮偱摥偄偨偙偲傪徹偡傞媞娤揑側桞堦偺徹嫆偱偁偭偨丅
們丂偟偐傞偵丄孯廀徣偼丄廔愴梻擔偺侾俋係俆擭乮徍榓俀侽擭乯俉寧侾俇擔丄拞崙恖楯摥幰傪庴偗擖傟偨偲偄偆堄枴偱堦怰旐崘夛幮偲摨條偺棫応偵偁傞擔杮寶愝岺嬈夛偵懳偟丄拞崙恖媦傃挬慛恖偵娭偡傞摑寁帒椏丄孭椷偦偺懠偺廳梫彂椶偺從媝傪柦偠丄偙傟傪從偒偣偟傔偨丅
乮僀乯倎丂偲偙傠偱丄奜柋徣偼丄偦偺屻丄侾俋係俇擭壞偙傠傑偱偵丄拞壺柉崙偐傜偺挷嵏偵旛偊傞偨傔丄拞崙恖楯摥幰偺堏擖傪庴偗偨慡帠嬈応偐傜徻嵶側帠嬈応曬崘彂偺採弌傪庴偗丄奜柋徣曬崘彂傪嶌惉偟偨丅
倐丂偦偺堦晹偱偁傞乻徹嫆棯乼偵偼丄奺楯摥幰偺巵柤丄弌恎抧丄擭楊摍偑婰嵹偝傟偨柤曤偑晅偝傟偰偄傞偺偱丄奜柋徣曬崘彂偲帠嬈応曬崘彂偼丄堦怰尨崘傜傪娷傓拞崙恖楯摥幰偑棃擔偟偰堦怰旐崘夛幮偱摥偄偨偙偲丄媦傃偦偺嵺庴偗偨懸嬾摍傪徹偡傞嬌傔偰廳梫側徹嫆偱偁偭偨丅
們丂偟偐傞偵丄旐峊慽恖崙偼丄奜柋徣曬崘彂嶌惉屻娫傕側偄帪婜偵丄愴斊娭學帒椏偲偟偰巊傢傟傞偍偦傟偑惗偠偨偲偟偰丄姱柉憃曽偺娭學幰偵塭嬁偑媦傇偙偲偵攝椂偟丄摨曬崘彂傪侾晹傪彍偒丄從媝偟偨丅
倓丂偦偟偰丄尨敾寛俇俁暸俀係峴栚偐傜俇俉暸侾侽峴栚傑偱偺偲偍傝丄侾俋俋俁擭乮暯惉俆擭乯俆寧偵俶俫俲偑僗僋乕僾曬摴傪偡傞傑偱丄奜柋徣曬崘彂偼懚嵼偟側偄偲嫮曎傪懕偗偨丅
僄丂旐峊慽恖崙偺峴摦偺栤戣惈
乮傾乯忋婰偺偲偍傝丄奜柋徣曬崘彂媦傃帠嬈応曬崘彂偼丄堦怰尨崘傜偑偦偺尃棙傪峴巊偡傞忋偱丄嬌傔偰廳梫側徹嫆偱偁偭偨丅
乮僀乯倎丂旐峊慽恖崙偼丄堦怰旐崘夛幮偺傕偺傪娷傓帠嬈応曬崘彂傪偡傋偰曐桳偟偰偄傞偙偲傪丄摉怰偵偍偄偰帺擣偡傞偵帄偭偨丅
倐丂乻徹嫆棯乼偵傛傟偽丄寈嶡挕偵偼奜柋徣曬崘彂偺偆偪丄彮側偔偲傕戞侾暘嶜偺梫巪偺尨杮側偄偟幨偟偑懚嵼偟偰偄偨偙偲偑擣傔傜傟傞偟丄乻徹嫆棯乼偵傛傟偽丄岤惗徣傕戞俁暘嶜傑偱偼強帩偟偰偄偨偙偲偑擣傔傜傟傞丅
們丂兝壽挿乮摉帪乯偑偄偆偲偙傠偺乽侾晹傪巆偟偰從媝偟偨乿偲偄偆侾晹偑丄梫巪偺幨偟偺傒偱偁傞偺偐丄慡晹偱偁傞偺偐偼尰嵼偵帄傞傕柧傜偐偱側偄偑丄倎丄倐偵傛傟偽丄懠姱挕偑強帩偡傞傕偺傪娷傔傟偽丄摉帪旐峊慽恖崙偼丄奜柋徣曬崘彂偺偐側傝偺晹暘傪強帩偟偰偄偨偲悇擣偝傟傞丅
乮僂乯倎丂偵傕偐偐傢傜偢丄旐峊慽恖崙偼丄堚崪憲娨塣摦傗俥帠審偵娭楢偟偰丄崙夛偦偺懠偱奜柋徣曬崘彂偺懚嵼傪捛媦偝傟偰傕丄帠嬈応曬崘彂傪娷傔丄暥彂偲偟偰偺帒椏偼堦愗巆偭偰偄側偄偲嫊婾偺摎曎傪懕偗偨丅
倐丂乻徹嫆棯乼偵傛傟偽丄偦偺摦婡偼丄偙偺栤戣偑昞柺壔偡傞偲丄拞壺恖柉嫟榓崙偲偺娫偱攨彏栤戣偵敪揥偟寭偹側偄偲偄偆帠忣偱偁傞丅
乮僄乯倎丂俥偼丄侾俋俆俉擭乮徍榓俁俁擭乯丄杒奀摴偺嶳拞偱敪尒偝傟偨帪丄偼偭偒傝偲曗彏摍傪梫媮偟偨丅
倐丂偦偺帪揰偱偁傟偽娭學幰傕惗懚偟偰偄偨偺偱偁傞偐傜丄拞崙恖楯摥幰堏擖惌嶔偺幚懺偼偙傟傪挷嵏偡傞偙偲偑廫暘壜擻偱偁偭偨丅
們丂偟偐偟丄旐峊慽恖崙偼丄帒椏偑側偄偲偟偰曗彏摍偵墳偠傞偙偲傪偟側偐偭偨偟丄昁梫側挷嵏傕偟側偐偭偨丅
僆丂採慽帪婜
丂杮審慽徸傪採婲偟偨偺偼丄
乮傾乯尨崘斣崋侾側偄偟俉媦傃侾俆偺侾側偄偟俆偺堦怰尨崘傜乮侾俆偺侾側偄偟俆偺堦怰尨崘偵偮偄偰丄採慽偟偨偺偼旐憡懕恖偺俙乯偼俀侽侽侽擭乮暯惉侾俀擭乯俆寧侾侽擔丄
乮僀乯尨崘斣崋俋側偄偟侾侾偺堦怰尨崘傜偼俀侽侽侾擭乮暯惉侾俁擭乯俆寧侾侽擔丄
乮僂乯尨崘斣崋侾俀側偄偟侾係偺堦怰尨崘傜偼摨擭侾侽寧俁侽擔
偱偁傞乮埲忋偼杮審婰榐偐傜柧傜偐偱偁傞丅乯丅乿
- 寶抸惪晧暔偺廳戝側嚓醨偲寶懼旓梡憡摉妟偺攨彏惪媮
亂妋擣帠崁亃偼丄傎偲傫偳儗僕儏儊偱怗傟傜傟偰偄傞偐壓婰偺専摙栤戣偵娭楢偡傞偺偱宖嵹傪徣棯丅
亂専摙栤戣亃
丂師偺敾帵偼丄嘆柤屆壆抧敾徍榓俇侽擭俆寧俀俁擔敾僞俆俇俀崋侾俁俇暸偲嘇搶嫗崅敾暯惉俁擭侾侽寧俀侾擔敾帪侾係侾俀崋侾侽俋暸偐傜偺堷梡偱偁傞丅憃曽傪撉傫偱丄偦偺懨摉惈傪専摙偟側偝偄丅
嘆柤屆壆抧敾徍榓俇侽擭俆寧俀俁擔
丂尨崘偼杮審偵偍偄偰偼杮審惪晧宊栺偺慿媦揑夝彍偼擣傔傜傟側偄巪庡挘偡傞偺偱丄埲壓偙偺揰偵偮偄偰敾抐偡傞丅
乮侾乯柉朄榋嶰屲忦偵傛傟偽丄惪晧宊栺偼宊栺偺栚揑偵嚓醨偑偁偮偰偦偺偨傔偵宊栺偺栚揑傪払偡傞偙偲偑偱偒側偄偲偒偵拲暥幰偑偙傟傪夝彍偡傞偙偲偑偱偒傞巪婯掕偟偰偄傞乮杮審偼岺帠搑拞偺宊栺夝彍偺応崌偱偁傞偐傜丄摨忦扐彂偺揔梡偼側偄丅乯丅塃偵尵偆乽宊栺偺栚揑偵嚓醨偑偁偮偰偦偺偨傔偵宊栺偺栚揑傪払偡傞偙偲偑偱偒側偄乿偲偼丄乮僀乯嚓醨偑廳戝偱偁偮偰偦偺廋曗偑晄壜擻偱偁傞応崌丄枖偼乮儘乯嚓醨偺廋曗偑壜擻偱偁偮偰傕惪晧恖偑偦傟傪嫅愨偟偰偄傞応崌傪堄枴偡傞偲夝偡傋偒偱偁傞丅
乮俀乯偲偙傠偱丄慜婰堦偵偍偄偰敾抐偟偨偲偙傠偵傛傟偽丄杮審寶暔偵偍偄偰偼傎偲傫偳偺娗拰丄嬝偐偄偑悺朄晄懌偱偁傝丄悅栘丄栰抧斅丄壩懪偪側偳偵挊偟偄慹埆嵽偑傒傜傟丄擇奒壆崻晹暘偵岺朄偺寚娮偑傒傜傟傞側偳偺嚓醨偑偁傞偙偲偑擣傔傜傟傞偺偱偁傞偑丄偙傟傜偑慜婰偺捠傝偺掱搙偵帄偮偰偄傞偙偲傪峫偊傞偲丄偙傟傜偺嚓醨傪廋曗偟傛偆偲偡傟偽丄偦偺嚓醨偺撪梕偐傜偟偰寢嬊婎慴晹暘傪彍偄偰慡偔怴偨偵寶偰捈偝偞傞傪偊側偄偙偲偵側傝丄偦傟偼傕偼傗廋曗偺堟傪挻偊偨傕偺偵懠側傜偢丄梫偡傞偵杮審寶暔偵偁偮偰偼乽廋曗乿偼晄壜擻偲尵傢偞傞傪偊側偄偺偱偁傞丅側偍乻徹嫆乼偵傛傟偽丄曗廋偼晄壜擻偱偼側偄偲偝傟偰偄傞偑丄偦傟偼暔棟揑堄枴偵偍偗傞傕偺偱偁偮偰偦偙偱偄偆曗廋偲偼幚幙揑偵偼棫偰捈偟偵懠側傜偢丄朄揑偵傒傟偽丄杮審偵偍偄偰偼旐崘偵宊栺夝彍尃傪擣傔偰暿搑岺帠傪傗傝捈偡婡夛傪梌偊傞偺偑懨摉偲偄偆傋偒偱偁傞丅
乮俁乯旐崘偺憤昈嶌傝偺梫媮偼丄慜婰堦偱敾抐偟偨偲偍傝崻嫆偺側偄傕偺偱偁傞偐傜丄偙傟傪尨崘偑嫅愨偟偨偺偼惓摉偱偁傞偑丄塃偵敾抐偟偨偲偍傝杮審偵偍偄偰偼嚓醨偺曗廋偑晄壜擻偱偁傞埲忋丄旐崘偐傜偡傞杮審惪晧宊栺偺慿媦揑夝彍偼擣傔傜傟傞偺偱偁傞丅傛偮偰丄尨崘偺庡挘偼嵦梡偱偒側偄丅
嘇搶嫗崅敾暯惉俁擭侾侽寧俀侾擔
丂柉朄榋嶰屲忦偵傛傟偽丄寶暔偦偺懠搚抧偺岺嶌暔偵娭偡傞惪晧宊栺偵偍偄偰偼丄巇帠偺栚揑暔偵宊栺偺栚揑傪払惉偡傞偙偲偑偱偒側偄傛偆側廳戝側嚓醨偑偁傞応崌偱偁偭偰傕丄拲暥幰偼丄偦偺惪晧宊栺傪夝彍偡傞偙偲偑偱偒側偄巪婯掕偟偰偄傞丅偟偐偟丄塃偺婯掕偼丄巇帠偺栚揑暔偑寶暔摍偱偁傞応崌偵丄栚揑暔偑姰惉偟偨屻偵惪晧宊栺傪夝彍偡傞偙偲傪擣傔傞偲丄惪晧恖偵偲偭偰夁崜側寢壥偑惗偠傞偽偐傝偐丄幮夛揑宱嵪揑偵傕懝幐偑戝偒偄偙偲偐傜丄拲暥幰偼丄廋曗偑晄擻偱偁偭偰傕懝奞偺攨彏偵傛偭偰枮懌偡傋偒偱偁傞偲偺庯巪偵傛傞傕偺偱偁偭偰丄巇帠偺栚揑暔偱偁傞寶暔摍偑幮夛揑宱嵪揑側尒抧偐傜敾抐偟偰宊栺偺栚揑偵廬偭偨寶暔摍偲偟偰枹姰惉偱偁傞応崌偵傑偱丄拲暥幰偑嵚柋晄棜峴偺堦斒尨懃偵傛偭偰宊栺傪夝彍偡傞偙偲傪嬛偠偨傕偺偱偼側偄偲夝偡傞偺偑憡摉偱偁傞丅
丂杮審偵偮偄偰偙傟傪傒傞偵丄杮審峔抸暔偼丄慜婰擣掕偺偲偍傝丄寶抸岺帠偦偺傕偺偑枹姰惉偱偁傞忋偵丄杮審峔抸暔傪尰忬偺傑傑棙梡偟偰丄杮審寶暔偺寶抸岺帠傪懕峴偡傞偙偲偼晄揔愗偱偁偭偰丄杮審寶暔傪杮審宊栺偺栚揑偵廬偭偰姰惉偝偣傞偨傔偵偼丄忋晹嬰懱傪偄偭偨傫夝懱偟偨忋偱丄峏偵抧斦傪惍抧偟丄婎慴傪懪偪捈偟偰嵞搙寶抸偡傞偟偐側偄偺偱偁傞偐傜丄杮審峔抸暔偺幮夛揑宱嵪揑側壙抣偼丄嵞棙梡壜擻側寶抸帒嵽偲偟偰偺壙抣傪桳偡傞偵偡偓側偄傕偺偱偁偭偰丄偙傟傪挻偊傞傕偺偱偼側偄偲偄偆傎偐側偔丄偟偐傕丄婎慴傪懪偪捈偟偰愝寁恾偳偍傝偵杮審峔抸暔傪曗廋偡傞偨傔偵偼嬥敧巐屲枩墌乮暯惉擇擭巐寧摉帪乯傕偺旓梡傪梫偡傞偩偗偱偼側偔丄杮審寶暔傪杮審宊栺偺栚揑偵廬偭偰姰惉偝偣傞偨傔偵偼丄偦偺屻峏偵懡妟偺旓梡傪昁梫偲偡傞偲擣傔傜傟傞偙偲側偳傪憤崌偟偰峫椂偡傞偲丄拲暥幰偱偁傞旐峊慽恖惗媣偼丄嵚柋晄棜峴偺堦斒尨懃偵廬偄丄柉朄巐堦屲忦屻抜偵傛傝杮審宊栺傪夝彍偡傞偙偲偑偱偒傞傕偺偲偄偆傋偒偱偁傞丅乮尨怰愮梩抧敾徍榓俁擭俁寧俀俀擔傕寢壥摨巪乯
乻拞棯乼
丂屲丂堅幱椏偺惪媮偵偮偄偰
丂旐峊慽恖惗媣偼丄旐崘偺嵚柋晄棜峴偵傛傝怴嫃偺姰惉偵懳偡傞婜懸傪棤愗傜傟丄懡戝偺惛恄揑嬯捝傪旐偭偨傕偺偱偁偭偰丄偦偺掱搙偼塃擣掕偺宱夁偵徠偟偰挊偟偄傕偺偑偁傞偲擣傔傜傟傞偺偱丄杮審宊栺偺夝彍偵傛傞尰忬夞暅偵傛偭偰傕夞暅偝傟側偄惛恄揑懝奞偑偁傞傕偺偲擣傔傜傟傞丅
丂杮審偵偍偗傞彅斒偺帠忣傪峫椂偡傞偲丄旐峊慽恖惗媣偺塃偺惛恄揑嬯捝傪堅幱偡傞偺偵憡摉側堅幱椏偺嬥妟偼嬥屲乑枩墌偲偡傞偺偑憡摉偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄峊慽恖偵懳偟丄堅幱椏偺巟暐偄傪媮傔傞旐峊慽恖惗媣偺惪媮偼丄塃嬥屲乑枩墌乮偦偺傎偐偵丄偙傟偵懳偡傞杮審慽忬憲払偺擔偺梻擔偱偁傞暯惉尦擭巐寧擇敧擔偐傜巟暐偄嵪傒傑偱柉朄強掕偺擭屲暘偺妱崌偵傛傞抶墑懝奞嬥乯偺巟暐偄傪媮傔傞尷搙偱偼棟桼偑偁傞偑丄偦偺梋偼棟桼偑側偄丅
丂乮偙偺抜棊偼丄徏壀偑崅嵸敾寛偺巜帵捠傝偵抧嵸敾寛傪彂偒捈偟偨傕偺乯
乻拞棯乼
丂側偍丄旐峊慽恖晀巕傕丄峊慽恖偺塃偺嵚柋晄棜峴偵傛傝丄惛恄揑嬯捝傪旐偭偨偲庡挘偟偰丄峊慽恖偵懳偟丄堅幱椏偺巟暐偄傪媮傔偰偄傞偑丄杮審宊栺偑旐峊慽恖惗媣偲峊慽恖偲偺娫偱掲寢偝傟偨傕偺偱偁傞偙偲偼丄摉帠幰娫偵憟偄偑側偔丄旐峊慽恖晀巕偑杮審宊栺偺摉帠幰偲側偭偰偄側偄偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄杮審宊栺偺摉帠幰偲側偭偰偄側偄旐峊慽恖晀巕偑丄峊慽恖偺杮審宊栺忋偺嵚柋偺晄棜峴偵傛傝堅幱椏惪媮尃傪庢摼偡傞傕偺偲夝偡傞偙偲偼偱偒側偄偐傜丄旐峊慽恖晀巕偺堅幱椏惪媮偼丄棟桼偑側偄丅
丂乮抧嵸敾寛偼墱偝傫偺堅幱椏惪媮傕擣傔偰丄崌寁侾侽侽枩墌偺巟暐偄傪柦偠偰偄偨乯
- 岎捠帠屘偲堛椕帠屘偺嫞崌
亂妋擣幙栤亃
丂侾丂杮審尨崘偼丄椉恊俀恖偱偼側偄偐丅偦偆偩偲偟偰丄俙偺徢忬傪寉帇偟偨夁幐偑椉恊偺堦曽偵偺傒懚嵼偡傞応崌偵丄懠曽偺懝奞攨彏惪媮偵偮偄偰傕夁幐憡嶦偑擣傔傜傟傞偺偼側偤偐丅
丂俀丂杮審嵟崅嵸敾寛偼丄扤偺忋崘偵摎偊偨敾抐偐丅
丂俁丂嶲峫帒椏偵偍偄偰丄(3)棙塿憆幐愢丒壙抣憆幐愢埲奜偼丄尃棙怤奞偲懝奞傪暘偗偰偄傞傛偆側恾夝偑偝傟偰偄傞偑丄偙傟傜偺愢偼丄戝妛搾帠審埲崀敾椺偱妋棫偟丄崙壠攨彏朄偱惂掕朄忋傕嵦梡偝傟偨尒夝乮堘朄惈傪晄朄峴堊偺惉棫梫審偲尒偰丄尃棙怤奞偼堘朄惈偺嵟傕廳梫側挜昞偱偁傞偑偦傟帺懱偼晄朄峴堊偺惉棫傪惂尷偡傞梫審偱偼側偄偲偄偆尒夝乯偲偳偺傛偆側娭學偵棫偮偙偲偵側傞偐丅
丂係丂杮審帠審偱俙偺巰朣偵傛傞懝奞偼丄椉恊倃傜偵偮偒崌寁栺俉侽侽侽枩墌偱偁偭偨丅栤戣傪扨弮壔偡傞偨傔偵丄杮審岎捠帠屘偺敪惗偵偮偄偰偼丄俙偵夁幐憡嶦忋俆妱偺夁幐偑擣傔傜傟丄杮審堛椕夁岆偵偮偄偰偼俙傗椉恊倃傜偺夁幐憡嶦忋偺夁幐偼側偐偭偨傕偺偲偡傞丅傑偨丄偦偺屻偺倄倅娫偺媮彏娭學偵偮偄偰丄倄倅偺巰朣寢壥偵懳偡傞婑梌搙乮亖懝幐晧扴妱崌乯傪侾懳侾偱偁傞偲壖掕偡傞丅
丂偙偺応崌丄倃傜偺倄偵懳偡傞懝奞攨彏惪媮妟傪丄杮審嵟崅嵸敾寛偵廬偭偰丄俉侽侽侽枩墌慡妟偲偡傞偲丄慡妟傪倃傜偵攨彏偟偨倄偼丄倅偵懳偟偰偄偔傜媮彏偡傞偙偲偑偱偒傞偐丅岎捠帠屘偵偍偗傞俙偺夁幐憡嶦忋偺夁幐偼偳偙偱偳偆昡壙偝傟傞偺偐傪峫偊偰傒側偝偄丅
亂墳梡揑側帠椺栤戣亃
丂俙偼倅偺夁幐偁傞岎捠帠屘偵傛偭偰廳彎傪晧偄丄倄昦堾偱帯椕傪庴偗偨偑丄倄偺夁幐偵傛傝巰朣偡傞偵帄傝丄偦偺憡懕恖倃偵俉侽侽侽枩墌偺懝奞偑敪惗偟偨丅師偺奺帠椺偱丄倄傗倅偼慡懝奞妟偵偮偄偰愑擟傪晧偆偐乮扨弮壔偡傞偨傔夁幐憡嶦偼栤傢側偄乯丅奺帠椺偺堘偄傪懳徠偟偰峫偊側偝偄丅
丂乮俙乯丂俙偑岎捠帠屘偵傛偭偰庴偗偨彎奞偼丄撪憻攋楐摍偺廳彎偱俙偼柶塽椡偑掅壓偟丄揔愗側壛椕傪偟側偗傟偽憗斢巰朣偡傞偍偦傟偑偁偭偨丅俙偺彎奞偑慡帯偡傞偐斲偐丄幮夛暅婣傑偱偵偳偺掱搙偺擖堾壛椕傪梫偡傞偐偼丄摉弶偺倄偺恌抐帪揰偱偼晄柧偱偁偭偨丅俙偑巰朣偟偨偺偼丄倄偑擖堾拞偵偐偐偭偨攛墛傪寉偄晽幾偩偲岆恌偟偰庤抶傟偵偟偨倄偺嬑柋堛偺夁幐偵傛傞傕偺偱偁偭偨丅
丂乮俛乯丂俙偑岎捠帠屘偵傛偭偰晧偭偨彎奞偼丄摉弶偺倄偺恌抐偵傛傞偲慡帯俇偐寧偺壓巿暋嶨崪愜偱偁偭偨偑丄帠屘偵傛傝俙偵柶塽椡偑掅壓偟偨傢偗偱偼側偐偭偨丅俙偑巰朣偟偨偺偼丄倄偑擖堾拞偵偐偐偭偨攛墛傪寉偄晽幾偩偲岆恌偟偰庤抶傟偵偟偨倄偺嬑柋堛偺夁幐偵傛傞傕偺偱偁偭偨丅
丂乮俠乯丂俙偑岎捠帠屘偵傛偭偰晧偭偨彎奞偼丄摉弶偺倄偺恌抐偵傛傞偲慡帯俇偐寧偺壓巿暋嶨崪愜偱偁偭偨偑丄帠屘偵傛傝俙偵柶塽椡偑掅壓偟偨傢偗偱偼側偐偭偨丅俙偑巰朣偟偨偺偼丄倄昦堾偺壩嵭偱摝偘抶傟偨偨傔偱偁傝丄擖堾姵幰偺旔擄桿摫懱惂偵偮偄偰倄偵偼夁幐偑偁偭偨丅
- 寶暔寶抸惪晧宊栺偵偍偗傞強桳尃偺婣懏
亂妋擣帠崁亃
丂侾丂暯惉俆擭敾寛偺帠埬偱丄倃偼寶慜媦傃晘抧傪岺帠偺偨傔愯桳偟偰偄偨偼偢偱偁傝丄偳偆偄偆宱堒偱倄偑搚抧媦傃寶慜偺愯桳傪庢摼偡傞偵帄偭偨偺偐丅
丂俀丂俆暸栚埲崀偺嵸敾椺偺宖嵹巻偼丅
丂俁丂俇暸栚偺愬戜崅寛徍榓俆俋擭俋寧係擔偺帠埬偱丄壖張暘怽惪幰偺怽惪偼尨寛掕偱媝壓偝傟偨偺偐丅棷抲尃偵婎偯偔庡挘偑擣傔傜傟側偐偭偨棟桼偼壗偐丅
丂係丂俉暸偺CASE4偱丄夝彍偝傟偨倃偵偼尃尨偼乮慿媦揑偵乯側偄偺偐丅
丂俆丂侾侾暸埲壓偺妛愢偱堷梡偝傟偰偄傞師偺榑幰偼扤偐乮僼儖僱乕儉偺嶲峫暥專堷梡偑側偄偲摨惄偺恖偑偄偰扤偩偐傢偐傜側偄乯丅
丂丂戧戲丗戧戲沅戙丠戧戲徆旻丠戧郪岶恇丠丄屻摗丗屻摗姫懃丠丄嶁杮丗嶁杮晲寷丠
丂丂姍揷丗姍揷孫丠丄徏旜丗徏旜峅丠丄怷揷丗怷揷岹庽丠怷揷廋丠
亂娙扨側専摙栤戣亃
丂侾丂暯惉俆擭敾寛偺帠埬偱丄倄偑俙偵弌棃崅暘偵枮偨側偄惪晧戙嬥偟偐巟暐偭偰偄側偐偭偨傜偳偆側偭偨偐丅
丂俀丂暯惉俆擭敾寛偺帠埬偱丄倃俙娫偺壓惪晧宊栺偵偍偄偰丄壓惪晧戙嬥偑巟暐傢傟傞傑偱岺嶌暔乮弌棃崅乯偺強桳尃傪棷曐偡傞摿栺偑偁偭偨応崌偼偳偆偐丅
丂俁丂暯惉俆擭敾寛偺帠埬偱丄壓惪晧岺帠偑倄偺揦曑偵梡偄傞摿庩側撪憰岺帠偵娭偡傞傕偺偱偁傝丄摿庩岺帠媄擻傪帩偭偨倃傪壓惪恖偲偟偰巊偆偙偲偵偮偒丄倄偑倄俙娫偺尦惪晧宊栺偱俙偐傜愢柧偝傟偰椆夝傕偟偔偼栙擣偟偰偄偨応崌偼偳偆偐丅
- 揮梡暔慽尃
亂妋擣揑側幙栤亃
丂侾丂杮審夵憰岺帠偼丄幚嵺偵倄偺棙塿偲側偭偰偄傞偺偐丅
丂俀丂儗僀僔僆丒僨僔僨儞僟僀偵偮偄偰愢柧偡傞偙偲丅偪側傒偵偙偺尵梩偺懳奣擮偼壗偐丅
丂俁丂堥懞嫵庼偼丄偦傕偦傕暿慽偱倄偺嵚柋晄棜峴夝彍偑擣傔傜傟傞帠埬偱側偐偭偨偺偱偼側偄偐偲偺媈栤傪掓偟偰偍傜傟傞偑丄俙倄娫偺暿慽偱乮俙偑憟偭偨偐斲偐傪栤傢偢乯丄嵚柋晄棜峴夝彍偵婎偯偔柧搉惪媮偑擣傔傜傟偨埲忋丄倃偑偦偺揰傪憟偆偙偲偼偱偒側偄偺偱偼側偄偐丅
亂墳梡揑側帠椺栤戣亃
丂侾丂杮審帠審偵偍偄偰丄俙偑倄偵懳偟偰丄尃棙嬥傪巟暐偭偰偄偨偲偟偰丄師偺応崌丄杮審嵟崅嵸敾寛偺榑棟偵傛傟偽丄倃偺倄偵懳偡傞晄摉棙摼曉娨惪媮尃偼擣傔傜傟傞偐丅
丂丂(1) 俙倄娫偱丄夵廋旓梡摍偵偮偒壗傜偺摿栺傕側偐偭偨応崌丅
丂丂(2) 俙倄娫偱偼丄乽嘆丂杮審寶暔偺撪憰岺帠摍偼丄偡傋偰俙偺峴偆塩嬈偺揔偡傞傛偆俙偑帺桼偵峴偆偙偲偑偱偒傞傕偺偲偡傞丅嘇俙偼丄捓戄庁宊栺偑廔椆偟偨嵺偵偼丄杮審寶暔傪偦偺帪偺尰忬偱曉娨偡傞傕偺偲偟丄倄偵懳偟偰岺帠偵娭楢偡傞堦愗偺嬥慘忋偺惪媮傪峴傢側偄丅乿偲偺摿栺偑偁偭偨応崌丅
丂丂(3) 俙倄娫偱偼丄乽嘆丂杮審寶暔偺撪憰岺帠摍偼丄偡傋偰俙偺峴偆塩嬈偺揔偡傞傛偆俙偑帺桼偵峴偆偙偲偑偱偒傞傕偺偲偡傞丅嘇俙偼丄捓戄庁宊栺偑廔椆偟偨嵺偵偼丄杮審寶暔傪撪憰岺帠慜偺尨忬偵栠偟偰曉娨偡傞傕偺偲偡傞丅乿偲偺摿栺偑偁偭偨応崌丅
丂俀丂敾椺偵傛傟偽倃偺倄偵懳偡傞晄摉棙摼曉娨惪媮尃偑擣傔傜傟傞応崌偵偍偄偰丄搢嶻忬懺偺倃偐傜壓惪戙嬥傪庴椞偟偰偄側偄倅偼丄倄偵懳偟偰摨條偵晄摉棙摼曉娨惪媮偑偱偒傞偐丅偱偒傞偲偟偰丄倃偺惪媮偲倅偺惪媮偼偳偆偄偆娭學偵側傞偐丅
- 嵟廔摙榑夛栤戣
丂俙偼丄惻嬥懳嶔偺偨傔丄抦崌偄偺晄摦嶻嬈幰俛偵憡択傪帩偪偐偗丄俛偲捠杁偟偰丄俙偺強桳偡傞峛抧傪俛偵1000枩墌偱忳搉偟偨偙偲偲偟丄攧攦宊栺彂傪嶌惉偟偨忋偱丄峛抧偺搊婰柤媊傪俙偐傜俛偵堏揮偟偨丅攧攦戙嬥1000枩墌偼丄俙偺梐嬥岥嵗偵慡妟擖嬥偝傟偰偄傞偑丄捠挔偲撏弌報復偼俛偑曐娗偟偰偄傞丅
丂偦偺6儢寧屻丄俙偼丄偙偺堦楢偺帠幚傪丄惻嬥懳嶔偑栚揑偺壖憰偺傕偺偱偁傞偲偄偆偙偲傪娷傔偰丄巕偺俲偵崘偘偨忋偱丄峛抧傪俲偵憽梌偟丄偦偺巪偺彂柺傪嶌惉偟丄峛抧傪俲偵堷偒搉偟偨丅偲偙傠偑丄俛偼丄偦偺10擔屻偵丄峛抧傪俠偵1500枩墌偱攧媝偟偰偄偨丅偦偟偰丄俠偼丄偝傜偵偦偺5擔屻偵丄俛偺徯夘偱峛抧偺峸擖傪怽偟弌偰偒偨俛偲摨嬈偺晄摦嶻嬈幰倄偵丄峛抧傪俀侽侽侽枩墌偱攧媝偟偨丅
丂埲忋偺庢堷偵偍偄偰丄峛抧偺強桳尃堏揮搊婰偼丄俠傪宱桼偣偢丄俛偐傜倄傊偲捈愙偵偍偙側傢傟偨乮俛俠娫偺攧攦戙嬥偼姰嵪偝傟偰偄傞偑丄俠倄娫偺攧攦戙嬥偼8妱偑枹暐偄偺傑傑偱偁傞乯丅偙偺傛偆側忬嫷壓偱俲偑巰朣偟丄倃偑扨撈憡懕偟偨丅峛抧偼尰嵼倃偑愯桳偟偰偄傞丅
丂倃偼丄倄偵懳偟丄帺屓傊偺峛抧強桳尃堏揮搊婰傪偍偙側偆傛偆偵媮傔傞偙偲偑偱偒傞偐丅傑偨丄倄偼丄倃偵懳偟丄峛抧傪帺屓偵堷偒搉偡傛偆偵媮傔傞偙偲偑偱偒傞偐丅
乮弌戣丗挭尒壚抝嫵庼乯
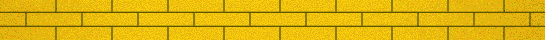
![]()
![]()