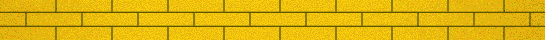
2006年度前期松岡ゼミ検討問題集
- 4月12日 不動産物権変動における対抗問題
2006年3月15日、Xは、Aとの間で、A所有の別荘である甲建物とその敷地の乙土地を5000万円で売買する契約を結び、契約締結時に500万円の手付金を支払い、甲建物の鍵の引渡しを受けた。XA間の売買契約の約定では、1か月後に2000万円の中間金を支払い、2か月後に残代金2500万円の支払と引換に移転登記手続を行うと定められていた。
ところが、売買契約締結の20日後に、Yが乙土地の一部に建築資材を置き、甲建物を取り壊し始めた。Xは直ちにAに状況説明を求めるようとしたが、Aは所在不明で、連絡が取れない。そこで、弁護士と相談し、Yを相手に、甲建物の取り壊し工事の停止と乙土地への立ち入りを禁じる仮処分を打つと共に、Aを相手に、甲・乙両不動産につき、処分禁止の仮処分を打って(民事保全法23条以下)、処分禁止の登記と登記請求権保全の仮登記を行った(民事保全法53条、不動産登記法111条・105条~108条)。
この基本設例を前提に、次の小問を考えなさい。
(1) Aは、XのほかにZに対しても、3月10日に、甲・乙不動産を売却する契約を結んでいたことが判明した。XがYに対して、乙土地からの建築資材の撤去と甲建物の取り壊しによる損害賠償を求めたところ、Yは、XとZのいずれが所有者か確定していないので応じられないと主張した。XのYに対する請求は認められるか。
(2) Aは、XのほかにZに対しても、3月10日に、甲・乙不動産を売却する契約を結んでいたことが判明した。XがYに対して、乙土地からの建築資材の撤去と甲建物の取り壊しによる損害賠償を求めたところ、Yは、甲建物の取り壊し工事は、所有者となったZから依頼されたものであり、Xに対する不法行為や不法占拠にはならない、と主張した。XのYに対する請求は認められるか。
- 4月19日 先取特権
次の事例において、XのYに対する請求は認められるだろうか。
平成16年4月4日、空調装置等の設計・施工等を目的とするX会社は、訴外A会社に対し、空調用機械器具甲を代金1000万円で売却し、同日、これらをAに引き渡した。Aは、同年4月11日ころ、甲をY会社に1200万円で転売して引き渡した。
しかし、Aは、平成16年8月8日、**地裁において破産宣告を受けたため、Xは、同月14日、甲の売買先取特権の物上代位権に基づき、AがYに対して有する甲の転売代金債権1200万円のうち1000万円について、債権差押および転付命令の申立てを行い、同日、同命令が発せられ、その正本は、同月21日、Aに、同月22日、Yに送達された。
他方、Yは、Aに対し、すでに弁済期の到来した別の空調用部品乙の売掛代金債権1400万円を有していたので、同債権を自働債権とし、AのYに対する甲の売買代金債権を受働債権として対当額で相殺する旨の意思表示し、その旨の内容証明郵便が、Aには同月31日に、Xには同年9月1日にそれぞれ送達された。
そこで、Xは、Xの取得した本件債権差押・転付命令の送達の後にされたYの相殺はXに対抗することはできないとし、Yに対して、本件差押・転付命令に係る1000万円と遅延損害金の支払いを求めた。
参考判例:最三判平成13年3月13日民集55巻2号363頁(抵当権者が物上代位に基づく賃料債権の差押えをした後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない)
- 5月17日 取消し
2005年12月20日、Xは、高校生の娘Aのために、語学学校Yに対して、2006年1月から1年間の英語研修プログラムを申込み、30万円を支払った。30万円の費用は、主としてレッスンの受講を希望するAが、貯めていた小遣いで負担し、Xが不足分5万円を負担した。契約に際しては、Aは同席せず、Yの窓口事務担当者BがXに説明したところによれば、毎週1回のべ30回のレッスンは、基本的には火曜日夕方5時から1時間で、外国人教師が実践的な英会話を教えるが、2週間以上前に申し込めば、追加の費用を支払うことなく、受講生の都合で、合計3回まで、同じ月の範囲内で日時の変更ができる、ということであった。
しかし、2006年2月2日に、3月末に計画された家族旅行の関係で、Aが2週分の期日変更の申込みをおこなったところ、Yは、3月には期日変更の申込みが多く、外国人教師の都合がつかないから、応じられないと回答した。Xが、それでは契約違反ではないかと追及したところ、Yの責任者Cは、レッスン期日の変更を定めた契約書第12条1項に、「ただし、教師の手配に都合がつかない場合には、変更ができない場合があります。この場合、受講者は、1回につき追加料金3000円を支払うことにより、翌月以降に代替授業を受けることができます」という規定があることを示して、Yには無償で代替授業をおこなう義務はない、と主張した。
XがAに聞いたところ、Yの雇っている外国人教師には、日本語がほとんどできず、セクハラもどきの下品な話題をおこなう好い加減な者もいて、Yの教育システム自体が信用できない、とのことであった。
2006年5月17日現在、Xは、AにYでのレッスンを受けさせるのをやめたいと考えているが、契約書第20条には、「受講者の都合で契約期間の途中でレッスンを受けるのをおやめになった場合には、いったんお支払いいただいた受講料は、いっさい返金いたしません」とあり、このことは、たしかに契約時にBからも説明を受け、Xも了解していた。
XもしくはAは、この場合、どうすれば良いか。
- 5月24日 取得時効と登記
Aは、甲乙という地続きの本件土地2筆を所有していた。Xは、1956年3月5日に、これらの土地をAの代理人と称するAの内縁の妻Bから買い受けて引渡しを受け、以後一体として現在に至るまで占有を継続しているが、移転登記手続は行っていなかった。後に判明したところでは、AがBに本件土地売却の代理権を授与した事実もXへの売却を知って追認したという事実も認められない。
その後、甲土地については、1967年12月10日に、Aは、Aが実質上の出資者=オーナーでBが代表取締役を務めるY社との間で、Y社を債権者、A自身を債務者、極度額を1000万円とする根抵当権設定契約を締結し、根抵当権の設定登記を行った。AY間に現実に被担保債権が発生していたかどうかは不明であるが、この根抵当権設定契約がAYの通謀虚偽表示であるという証拠はない。
1977年11月5日、Aは、Yに、乙土地を売却し、移転登記を行った。
1998年頃、本件土地の近辺にリゾート村開発が計画されたことを機縁に、本件土地の帰属をめぐる争いが顕在化したので、XとABの三者は、話し合いの機会を持った。しかし、1956年当時の売却関係書類は散逸し、その経緯等についても関係者の記憶はすでに曖昧になっていた。また、1990年頃の時点でABはすでに内縁関係を解消していて、それ以後、Y社の株式はすべてBが所有している。Xと懇意でXに対して一定の責任を感じていたAは、「甲土地についてXの時効による所有権取得を認めることに吝かでないが、甲土地の抵当権やすでに売却済の乙土地については、自分だけではどうしようもない」という態度を採ったが、BはXの取得時効の主張を争った。
そこで、2000年7月7日、Xは、とりあえず、甲土地についてのみ、Aを相手に、1956年3月5日を起算点として20年間占有を継続し取得時効が完成した、と主張して、移転登記手続請求の訴えを提起した。Aが争わなかったため、この訴訟は、同月28日、Xの勝訴が確定した。そこで、Xは、勝訴判決に基づいて同年8月1日に甲土地の所有権移転登記を行ったが、Yの根抵当権の登記は残った。
Xは、さらに、Yに対して甲土地上のYの根抵当権設定登記の抹消と乙土地の所有権移転登記を求めたいが、可能だろうか。
[2004年の潮見ゼミとの対抗討論会の問題(松岡出題)から一部を簡略化して流用]
- 6月14日 抵当権侵害
2005年4月4日、Xは、Aに5000万円を期間1年、利息年利5%、遅延損害金年利14%の約定で貸し付け、この債権を担保するため、A所有の甲マンションの305号室の区分所有権と敷地の持分権(以下あわせて甲上の権利という)の上に共同抵当権の設定を受け、同日、設定登記を備えた。
ところが、弁済期限である2006年4月4日になってもAは弁済をせず、Xが調べてみると、Aは数か月前から行方不明になっていた。また、甲上の権利は、2006年1月10日付売買を原因として、Yに移転登記がなされていた。さらに、305号室には、現在、多数の外国人Zらが寝泊まりし、中には病人がいるようであった。Zらは、ほとんど日本語が話せず、かろうじて、ZらがYから305号室の使用を許諾されているらしいことが聞き出せたにすぎなかった。
甲マンションは、それなりのグレードのマンションで、305号室は、時価8000万円程度と評価されている。現在のところYやZらと他の住人との間で目立ったトラブルは発生していないが、言葉の通じない外国人が多数出入りすることには、近隣住民から甲マンションの管理を委託されたB社に苦情が寄せられている。
Xが執行関係に詳しい顧問弁護士Cに相談したところ、このままでは、抵当権の実行としての競売を申し立てても、はたして売却ができるかどうか難しいとの話であった。
さて、Xは、どのような対応策を講じることができるだろうか。
- 6月28日 譲渡担保の対外的効力
動産譲渡担保がSからG1とG2に二重に設定された場合、判例のような所有権的構成(権利移転的構成)に従うとすると、後から譲渡担保設定契約を結んで融資をした債権者G2は、先に譲渡担保の実行手続を行って、目的物の現実の占有を取得しても、第一の譲渡担保権者G1に負けることになるか。
参考となる解説として、昨年度同志社大学の司法研究科(ロースクール)未修者クラスで配付した補足解説を配りました。
- 7月 5日 民法94条2項の類推適用
次の文章は、大阪高判昭和59年11月20日判時1141号85頁の判決文からの抜粋である。この事件について、どう判断すべきかを検討しなさい。
原審が確定した事実関係によれば、(一)Xは、昭和41年3月12日、訴外Aから本件土地を買受け、同人から所有権移転登記手続をなすに必要な一切の書類を受領しながら、右登記手続をしないでいた、(二)ところが、昭和42年8月24日付で本件土地についてAから訴外B(Xの前記売買における代理人)に所有権移転登記がなされているが、登記原因とされた昭和42年8月ころに両者間に売買が行われた形跡はない、(三)その直後の同月26日付でBから訴外Cに売買を原因とする所有権移転登記がなされた、(四)昭和46年1・2月ころ、Xは、訴外D土砂積出事業共同企業体との間で本件土地を含む土地につき採土契約を結ぶに際し、右企業体側から、本件土地がC名義になつている旨の事実を示して釈明を求められ、遅くともそのころ本件土地が第三者名義となつていることを知つた、(五)しかしその後もXが右登記を放置していたところ、Yらは前記C名義の登記が実体に合わないことを知らず本件土地を取得した(なお、本件土地のうち第一審判決添付別紙目録1ないし3の土地については、昭和51年3月1日付でCから訴外Eに、同年4月13日付でEよりY1に、同4の土地については、同月16日付で持分各3分の1につきCから承継前原審控訴人F及び訴外Gに、同年8月24日付で残3分の1につきCから訴外Hに、さらに同年10月9日付でHからY1に、同年11月8日付でGの持分3分の1につきGから上告人Y2に、いずれも売買を原因として所有権移転登記が経由されている。)、というのである。
そして、原審は、本件について民法94条2項を類推適用するためには、不動産の買受人が所有権移転登記に必要な書類を受取つていながら移転登記をせずに放置したり、第三者名義に登記されたことを知つた後もその回復の措置をとらなかつたことのみではなお足りず、少なくともXが実体上の権利関係に反する虚偽の登記を作り出し、または作り出されたことにつき密接な行為をしたことを要するものと解すべきところ、本件には、この点を是認するに足りる証拠はないとして、民法94条2項の類推適用がある旨のYらの抗弁を排斥し、また、右事実関係から、Xが、Yらは本件土地の所有権を取得していないと主張することは、禁反言ないしは権利外観法理に照らして許されないものとは解されないとして、Yらの右抗弁を排斥している。
解説のおりには、下記の判決文の続きを配付しました。
しかしながら、真実の権利者が、不実の登記の存在を知りながら、相当の期間これを放置したときは、その登記を信頼して利害関係を持つに至る第三者の出現が予測できるはずのものであるから、真実の権利者において当該不実の登記を是正する手段を講ずべきものであり、これを怠つた者が、登記を信頼して取引関係に立つた第三者よりも厚く保護されるべき理由はないから、少なくとも禁反言もしくは権利外観法理により、真実の権利者は登記を信頼した善意の第三者に対抗することはできないと解するのが相当である。これと異なる見解のもとに上告人らの抗弁を排斥した原審の判断は、禁反言もしくは権利外観法理の適用を誤つた違法があるといわざるを得ず、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすこと明らかであるから、論旨は理由がある。
そして、原審の適法に確定した事実関係によれば、Xは、本件土地を買受けてから10年余、しかも第三者の不実の登記の存在を知つてから5年余に亘つてこれを放置していたものであつて、その放置期間は極めて長期間であり、他方Yらはその後に右不実の登記ないしはさらに第三者を経由した登記を信頼して本件土地を買受けたものであるから、真実の権利者たるXは、禁反言もしくは権利外観法理により、善意の第三者たるYらに対抗できないものというべきであり、Xの本訴請求は理由がないから、Xの請求を認容した第一審判決に対するYらの控訴を棄却した原判決を破棄し、右第一審判決を取消したうえ、Xの本訴請求を棄却すべきである。
【参考文献:本件評釈】
- 高畑順子・法と政治37巻1号181頁1986年3月
小池信行・登記研究464号6頁1986年9月
松岡久和・龍谷法学18巻4号97~107頁1986年3月
上井長久・判例評論320(判例時報1160)39~43頁1985年10月
田中学・東洋法学27巻2号89~100頁1986年3月
藤村和夫・法律時報57巻12号138~141頁1985年11月
内田勝一・季刊・民事法研究13(判例タイムズ581)103~108頁1986年3月25日
- 7月12日 山本敬三ゼミとの対抗ディベート
1.ケース
(1) X信託は、2004年5月21日、Yら3社(Y1ホールディングス・Y2信託・Y3銀行)との間で、Yグループ(Y1ら並びにYのその他の子会社及び関連会社の総称)からX信託グループ(X信託並びにX信託の子会社及び関連会社の総称)に対するY1信託の法人資金業務等を除く業務に関する営業、これを構成する一定の資産・負債及びこれに関連する一定の資産・負債(以下「本件対象営業等」という)の移転等からなる事業再編と両グループの業務提携(以下「本件協働事業化」という)に関して合意をし、その合意内容を記載した書面を作成した(以下、この合意を「本件基本合意」、その合意書面を「本件基本合意書」という)。
- 本件基本合意書8条1項は、「各当事者は、事業・会計・法務等に関する検討、関係当局の確認状況又は調査の結果等を踏まえ、誠実に協議の上、2004年7月末までを目途に協働事業化の詳細条件を規定する基本契約書を締結し、その後実務上可能な限り速やかに、協働事業化に関する最終契約書を締結する。」と定めている(以下、同条項に定める基本契約を「本件基本契約」という)。
- 本件基本合意書12条は、その見出しを「誠実協議」とし、その前段において、「各当事者は、本基本合意書に定めのない事項若しくは本基本合意書の条項について疑義が生じた場合、誠実にこれを協議するものとする。」と定め、その後段において、「各当事者は、直接又は間接を問わず、第三者に対し又は第三者との間で本基本合意書の目的と抵触しうる取引等にかかる情報提供・協議を行わないものとする。」と定めている。
- 本件基本合意書には、Y3社及びX信託が本件協働事業化に関する最終契約を締結すべき義務を負う旨を明確に定めた具体的な規定はない。また、本件基本合意書には、本件基本合意書に定める条項に違反した場合の制裁や違約罰についての定めはない。
(2) A監査法人は、2004年5月21日、Y1取締役会に対し、Y1の同年3月期決算が適正であるとの監査報告書を提出した。同監査報告書には、「営業報告書に記載されている後発事象は、次期以後の会社の財産又は損益の状態に重要な影響を及ぼすものである。」との記載がある。
Y1が作成した同月期営業報告書には、後発事象として、Y3社及びX信託は、Y1信託とX信託との経営統合により、「Yグループの信託・財産管理事業等を『協働事業』化することについて、2004年5月21日合意致しました。」との記載がある。
Y1は、2004年5月24日、同年3月期決算を公表した。Y1は、同決算期における決算として、Y1連結の当期純利益がマイナス4028億0600万円、Y1傘下銀行単体合算の当期純利益がマイナス3755億9300万円、Y3銀行単体の当期純利益がマイナス3402億6000万円、Y3銀行連結の自己資本比率が8.36パーセント(前年9月期比2.73パーセント減)、Y1傘下銀行単体合算の与信関連費用が1兆3115億6700万円、Y3銀行単体の与信関連費用が1兆1948億1600万円、Y3銀行単体の繰延税金資産(ネット)が将来の課税所得見積期間を5年間として1兆1739億円、自己資本のTierI(自己資本の基本的項目)を1兆7890億円と計上した。
(3) その後、X信託とYら3社は、本件基本合意にもとづき、同年7月末日までをめどとして本件協働事業化の詳細条件を定める基本契約の締結を目指して交渉を続けた。
Y1の担当者は、2004年6月5日ころ、X信託の担当者に対し、本件協働事業化のための作業の進行予定として、本件基本契約及びY1信託とX信託の合併契約書の締結日を同年7月22日、Y1信託とX信託との合併期日を同年9月21日にすることなどを内容とするスケジュール案を送付した。Yら3社及びX信託の担当者は、同年6月5日ころ当時、上記スケジュールを前提に本件協働事業化に向けての作業を進めていた。
X信託の担当者は、2004年6月下旬から7月上旬にかけて、同年9月末までに本件協働事業化を完了することを前提として、金融庁に対する各種認可・免許申請や登録、公告の準備等、本件協働事業化の実現のために必要な手続についてYら3社の担当者と協議を進め、その準備を行った。
2004年7月9日、第1回協働事業化推進委員会が開催され、X信託、Y1及びY3銀行、Y1信託の関係者らが参加するとともに、事務局として、X信託の担当者らが参加した。同委員会では、同日の議題を「[1]【確認事項】『協働事業化』のスキーム・スケジュールについて」、「[2]【確認事項】分割の範囲について」とし、本件基本合意時から変更・具体化した本件協働事業化のスキーム、スケジュールや分割の範囲等について上記事務局から報告があった。上記スキームでは、本件基本契約の締結日を同月22日と予定していた。同委員会では、第2回協働事業化推進委員会の開催日を同月21日とし、その議題を「『基本契約書』等諸契約の締結について」とすることにした。
同委員会の議事録には、Y1が「基本契約書へ盛り込む項目のうち、事務局でペンディングとなっている事項はあるのか。」と質問し、事務局が「P社(協働事業のために立ち上げる会社)への出資比率については最終決着していない。」と回答し、Y1が「7/22までに確定させるのか。」と質問し、事務局が「その予定」と回答した旨記載がある。また、同議事録には、X信託が「既に事務局レベルで打診中だが、〈略〉につき検討いただきたい。」と発言し、Y1が「バックグラウンドは理解できるが、技術的に難しい話であるのも事実。引続き個別に議論させていただきたい。」と発言した旨記載がある。
X信託の担当者は、2004年7月12日、Y1の担当者に対し、P社への出資比率につき、「標記の件は、各々50%の合弁(Y150%、X銀行50%)で宜しいでしょうか」との電子メールを送信し、同担当者は、同月13日午前7時55分、「その方向で結構です。よろしくお願いします。」という電子メールを返信した。
X信託は、2004年7月12日までに協働事業化のための準備として従業員の配置転換等を行い、同月13日、第三者割当増資金20億円をXの系列銀行に払い込んだ。
(4) Y1信託及びY3銀行の親会社であるY1のB社長は、2004年7月13日及び14日、X信託のC社長と面談し、口頭で本件協働事業化の白紙撤回を通告し、Yら3社は、同月14日及び16日、X信託に対し、書面で本件基本合意の解約を申し入れたが、X信託は、上記白紙撤回や解約の申入れを受け入れ難いとして了承しなかった。Yら3社は、上記面談に至るまで、X信託に対し、本件基本合意後の事情の変化等により、本件協働事業化の実現に影響を及ぼすような事情が発生したことを明らかにしたり、その打開策等について説明をしたことはなかったし、上記面談においても、本件協働事業化が実現できなくなったと判断するに至った原因ないし理由について具体的な根拠等を示して説明したり、その解決の可能性や方策等について、X信託と協議、交渉することもなかった。
X信託は、その後も、本件協働事業化の実現を強く望み、Yら3社に本件協働事業化に向けた協議の再開を申入れたり、Yら3社を債務者として、Yら3社が本件対象営業等の第三者への移転やY1信託の第三者との合併等、本件基本合意の目的と抵触し得る取引等に係る情報の提供や協議を第三者との間で行うことを禁止する旨の仮処分命令を申し立てるなどした。
(5) Y1は、2004年7月16日、Mグループとの間で、YグループとMグループとの経営統合に向けて協議を開始すること、同月31日までに基本合意書を締結すべく努力することについて合意した後、Mグループとの間で、経営統合に関する準備、作業を進めた。Y1は、Mグループとの間で、同年8月12日、経営統合に関する基本合意を締結し、同年9月10日、Y3銀行が発行する7000億円の株式をMグループが引き受けることを内容とする資本増強に関する協定書を締結した。Mグループは、同月17日、Y3銀行発行の株式を引き受け、7000億円を払い込んだ。
Y1とMグループ、Y1信託とM信託、Y3銀行とM銀行は、それぞれ、2005年2月18日に統合契約書を締結し、同年4月20日に合併契約書を締結した。各合併は、いずれも同年6月に開催された各社の株主総会において承認された。
(6) そこで、X信託は、Yら3社に対し、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償として、損害金2331億円の一部である1000億円の支払いを求めた。
2.参考資料
1)必読判例
最決平成16年8月30日民集58巻6号1763頁
東京地判平成18年2月13日判例タイムズ1202号212頁
2)必読文献
(1) 山本敬三『民法講義Ⅳ-1』(有斐閣・2005年)45~55頁
(2) 沖野眞已「判批:最決平成16年8月30日」『平成16年度重要判例解説(ジュリスト1291号)』(有斐閣・2005年)68頁
3)参考文献
(1) 山田剛志「判批:最決平成16年8月30日」判例時報1894号181頁(2005年)
(2) 中東正文編『UFJvs.住友信託vs.三菱東京M&Aのリーガルリスク』(日本評論社・2005年)
(3) 潮見佳男『債権総論Ⅰ』(信山社・第2版・2003年)543~564頁
(4) 高橋眞「契約締結上の過失論の現段階」ジュリスト1094号139頁(1996年)
(5) 池田清治『契約交渉の破棄とその責任』(有斐閣・1997年・初出1991~92年)、
(6) 横山美夏「不動産売買契約の『成立』と所有権の移転(1)(2)」早稲田法学65巻2号1頁・3号85頁(1990年)、とくに3号297頁以下
(7) 河上正二「『契約の成立』をめぐって-現代契約論への一考察(1)(2)」判例タイムズ655号11頁・657号14頁(1988年)
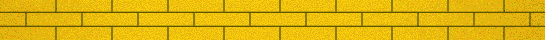
![]()