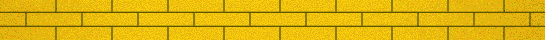
2008年度前期松岡ゼミ検討問題集
- 4月9日 代理権踰越による表見代理
Yは、注文を受けて機械部品を製造販売している町工場である。Yは、人手不足のため、商品の配達についてアルバイトのAを雇った。Aは機転の利く青年で、たいへん評判がよく、配達先から新たな注文を聞いてくることもしばしばあり、Yは重宝していた。その後、Yの従業員が1人辞めたことから、YはAに、集金業務まで信頼して任せるようになり、さらには、いちいち注文を伝達してもらってYが価格や納期を後で知らせることが不便なので、生産管理や原価・値引き限度などのデータを収めたパソコンをAに使わせて、得意先で直接注文を受けて価格や納期を決める受注業務の一部も託すようになった。
ところが、このように任される仕事の範囲が増えて責任も増したのに、Aのアルバイトの給料はあまり高くならなかったため、Aは不満を募らせていた。そうしたある日、Aが工場の正規従業員Bとの間でけんかをした際、Yの工場長は、明らかにBに非のあることを知りつつ、Bに辞められては困ることから、Aを叱責し、アルバイトの給料を減額すると言い出した。そこで、従来から不満を募らせていたAは、アルバイトを辞めた。しかし、YがパソコンのデータやYの領収書をきちんと回収しなかったので、「行きがけの駄賃」とばかりに、Aは、Xほかの得意先から、勝手に集金をするとともに、注文を受けてその前金の一部を受け取り、行方をくらませてしまった。
15日後、Xらが、納期が来てもYから商品の納入がないことを不審に思ってYに問い合わせたところ、以上の事情が判明した。
Xらは、まず、注文の商品を納入すべきこと、それが無理なら、契約は解除するので前金を返金し、損害賠償をせよとYに迫った。Yは、Aはすでに辞めており、Aの集金や受注・前金受領はAが勝手にやったことであること、今までAに前金まで受領させたことはなかったことなどを主張して、請求には応じられないと答えた。
Xの履行請求あるいは契約解除に伴う前金返還・損害賠償の請求は認められるか。
- 4月16日 不動産物権変動とその諸問題
今回は、問題と解答の両方を掲載します。
相続に関連する次の紛争のうち、判例によれば、Aが死亡したことを樹に不動産甲について所有権(もしくは持分権)を取得したXは、その権利取得を登記なくして事情を知らないYに対抗できるか。結論のみならず、その理由を簡単に説明せよ。
(1) Aの相続人はAの実子のBとXであったが、Bは相続を放棄した。ところが、Xが相続による甲の所有権取得の登記を行わないうちに、Bの債権者Yが、甲につきBに代位してAからB・Xへの共同相続の登記を行い、Bの1/2の共有持分権を差し押さえた。
答え:最判昭42年1月20日民集21巻1号16頁:939条の例外のない遡及効→放棄によりBは完全に無権利者で、Yが代位して行使できる権利はなく、共同相続登記は完全に無効。登記に公信力がない以上、Aは甲の所有権全部の相続による取得をYに対抗できる。放棄後に第三者が出現する可能性が少なく、放棄の有無は家裁で調査ができるし、遺産分割前に共同相続の登記を行うことは通常期待できない(本問では単独相続なのでこの論拠は妥当しにくいが、一般的には放棄後も共同相続になる可能性が高い)。
(2) Aの相続人はAの実子BとAの非嫡出子Xであったが、Bは自分だけがAの単独相続人であるかのように装って甲について相続による所有権取得の登記を行ったところ、Bの債権者Yが、B名義の甲を差し押さえた。
答え:百Ⅰ54事件。Xは甲につき1/3の共有持分権を有する(900条4号)。Bの単独相続の登記はXの持分権の実体を反映しない限度で無権利の登記であり、登記に公信力がない結果、Yが差し押さえられるのはBの持分2/3に限られ、Xは登記なくして相続による権利取得を主張できる。
学説は対立する(古典的には、我妻・舟橋両巨頭の共有の弾力性論による対抗問題構成もあったが少数説)。①相続は単純な無償取得ではなく、財産の清算・分配や遺族の生活保障を含む、②目的不動産が唯一財産だと相続人間の遺産分割でも調整は困難、③分割の有無や共同相続関係は調査可能、④分割前の登記は期待できないし、自己の相続持分のみの登記はできない、⑤対抗問題と構成すると悪意の第三者もが保護されてしまう、などにより、判例支持が通説。ただし、110条の活用や94条2項類推適用により、善意(無過失)の第三者を保護するべき場合があるとの指摘がなされている。
(3) XはAの相続人であるが、Aの生前、AからA所有の甲土地の死因贈与を受けた(死因贈与とは贈与者の死亡を不確定期限とする贈与契約である)。しかし、Aの死後、Xの兄でXと共同相続人の関係にあったBは、Xに無断で共同相続の登記を行い、1/2の持分権を事情を知らない親戚のYに譲渡して移転登記をしてしまった。Xは甲の所有権全部の取得を主張したい。
答え:死因贈与は遺贈と非常に近い。それどころか、死因贈与は遺贈と異なって契約なので、遺贈の場合でさえ登記を要するとする昭和39年判例との対比で、契約によって所有権を取得した者が登記しないと物権変動を対抗できないというのは、いっそう強く妥当する。ちなみに、最高裁には判例がないが、昭和13年判決は、「1 死因贈与による不動産の譲渡についても登記を必要とする。2.死因贈与による不動産受贈者に対し、贈与者の相続人から同不動産を譲受けた者は、受贈者の登記欠缺を主張する利益を有する第三者に該当する」としている。
また、Yは親族であるが事情を知らないし、家計(財布)を同じくする同居の夫婦・親子などの関係よりは独立した利益を有する他人に近い。相続関係に親族が事情を知りながら介入してくることすら良くある話で、まして善意のYは、背信的悪意者と言い難い。
(4) Aの相続人はAの実子のBとXであったが、遺産分割協議の結果、甲はXが取得することになった。しかし、Xが甲の所有権全部の相続による取得の登記を行う前に、Bの債権者Yが、甲につきBに代位してAからB・Xへの共同相続の登記を行い、Bの1/2の共有持分権を差し押さえた。
答え:百Ⅰ55事件:遺産分割は、分割時に新たな権利変動を生じるのと実質的に異ならないので、登記なくして権利取得を対抗できない。通説は判例を支持するが(①遺産分割の折衷的処理=移転主義への接近、②分割期限がなく第三者の出現可能性が高い(909条も第三者の利益に配慮)、③登記懈怠等)、悪意の取得者や、差押債権者には保護の必要性が乏しいとの有力な批判があり、これらの説は94条2項類推適用を主張する。
(5) Aの相続人はAの実子のBとXであったが、遺産分割協議の結果、甲はXが取得することになった。しかし、Xが甲の所有権全部の相続による取得の登記を行う前に、Bが遺産分割協議書を偽造して、甲を単独で相続したとの登記を行ったところ、Bの債権者Yが、B名義になった甲を差し押さえた。
答え:最終的な登記が可能であったのに懈怠したことを強調すると、登記なくしてまったく権利取得を主張できないとされる可能性もあるが、共有持分を超える部分はそもそも無権利だということに力点を置くと、1/2の持分の限度では登記なくして対抗できるということになろう。
Bの相続分はあくまで1/2であり、それを超える登記は無効、したがって、Xは少なくとも1/2の持分については、登記なくして対抗できる、という後者の結論になりそう。
これに関連して、同志社での講義後、Bは自ら遺産分割協議によって権利を失ったはずの甲について権利取得の登記をしているので、全体的に無権利者ではないのか、という質問をいただいた。たしかに無権利の法理を徹底する論理を採用すれば、そうなると思いうが、その論理では、取消後の詐欺者・強迫者から第三者が転得した場合や、遺産分割後に共同相続登記を前提にした持分を債権者が差し押さえた場合等について、対抗問題と構成する判例を理論的には説明しにくくなる。
(6) Aの相続人はAの実子のBとXであったが、Aは有効な自筆証書遺言で「甲はXに相続させる」旨を書き残して死亡した。ところが、Xが甲について所有権取得の登記を行なう前に、Bの債権者Yが、甲につきBに代位してAからB・Xへの共同相続の登記を行い、Bの1/2の共有持分権を差し押さえた。
答え:平成14年判決より前には直接の最高裁判例はなく、議論も少ない問題であった。平成14年判決は、最判昭和38年2月22日民集17巻1号235頁に従い、「相続させる遺言」の受益者は、これにより取得した特定不動産の所有権や共有持分を登記なくして、共同相続登記をして別の共同相続人の共有持分を差し押さえた債権者にも対抗できる、とした。
平成14年判決は、無権利の法理を採用し、登記なくして対抗できるとしたのである。しかし、この判決にも、遺贈は登記なくして対抗できないとした昭和39年判決と整合しないのではないかとの疑問が呈されている。単独申請でより容易に登記ができた「相続させる遺言」の名宛人が、それが困難であった受遺者より手厚く保護されるべき理由は十分ではないだろう。
学説には、昭和39年判決のような遺贈の場合の対抗問題構成自体に批判的な考え方も多かったので、平成14年判決がおかしいというより、昭和39年判決を再考すべきだとか、いずれの場合にも第三者の保護は、94条2項の類推適用や、真の権利者の帰責性を要しない32条1項後段の類推適用によるべきだという考え方が有力である(それにも限界があるのは今日の報告のとおり)
2 前問のような判例の解決は、どのような観点から正当化することができるか。また、これに対してはどのような批判があるか。
答え:(1) 正当化根拠 いろいろ考えられるが、私は次の点が最も重要だと思う。94条2項類推適用論の発達前に判例法の大部分はできた。すなわち、登記に公信力が認められないことから、無権利構成=登記不要説を採ると取引の安全を害しすぎるので、原則として登記必要説を採り、個別的に見て現実的な登記の可能性が乏しい場合には、遡及効を強調して無権利構成=登記不要とする修正無制限説になったと思われる。
(2) 批判として、取消しと登記や取得時効と登記の問題などとも共通する次の2点が重要。①遡及効を強調したり無視したりして理論的に一貫しない。②悪意の第三者まで保護されてしまう。たしかに②については、背信的悪意者排除論の拡張が考えられるが、それにも限界があり、無権利構成+94条2項類推適用論の方が妥当と批判される。
もっとも、177条の対抗問題自体、公信力説や法定制度論の一部のように、第三者に善意ないし善意無過失を一般的に要求して妥当性を確保する一方、公示の原則(対抗問題)と公信の原則(無権利の法理)を連続的に捉えることも可能である。登記必要説+悪意者排除説と、登記不要説+拡張された背信的悪意者排除説では、結論的にもあまり差がない。
- 4月23日 錯誤
1 Yは、友人甲山太郎が長年付き合っていた乙川花子と遂に結婚することを知り、太郎と結婚のお祝いについて相談して、太郎夫婦の入居予定の新居の玄関に掲げる大理石製の表札をプレゼントすることにした。Yは、Xに、「甲山太郎 花子」と彫る表札を5万円で注文した。ところが、結婚式の1週間前に、花子には深い仲の男友達がいたことが判明して、太郎と花子の結婚の話は、破談になってしまった。次の場合、Yは、できあがった表札(何の役にも立たないし、再生利用も困難であるとする)の受領を拒んで、Xから請求されている5万円を支払わないことができるか。
1) Yが、誰が使うかをXに告げることなく表札を注文した場合
2) Yが、贈り物用の包装をしてもらうようXに依頼して表札を注文した場合
3) Yが、友人の結婚式の贈り物だと告げて、Xに表札を注文した場合
2 個人商店を経営するYの店員Aは、X社にYの名前で(担当Aと明記していた)10グロス(120ダース=1440個)の商品甲をファックス注文した。XY間の取引では、従来から、支払いは商品の納品と引き換えという現金取引であった。
しかし、実はYが頼んだのは10ダースの商品甲の発注だったのに、聞き間違えたAが10グロスを発注してしまった。Xが納品期日に10グロスの甲を持参して代金の請求をしてきた場合、YはX社からの代金請求に応じなければならないか。
(2002年度民法第1部の試験問題の一部より改変)
- 5月7日 消滅時効 ── 模擬裁判風討論会
2つの教室に分かれて、原告班5名対被告班5名の議論を裁判官班5名が進行・整理したうえ即決の判決言い渡しを行うという模擬裁判風討論会を行います。
問題は次のとおり。
S株式会社は、平成10年4月1日、その設立直後に、系列の親会社であるY株式会社から、期間3年、利息年利3%の約定で3億円の融資を受けて、本件土
地甲を取得して所有権取得登記を行い、資材置き場等として使用する一方、Y社に対する債務を担保するため、甲土地にYのために本件抵当権を設定し、抵当権
の設定登記を行った。
Sは、その後、事業不振に陥り、Y社への借入金の返済が滞ったが、そもそもの設立の経緯とYの債権管理上のミスから、Yは、その返済を求めることがない
まま、現在に至っている。平成18年5月1日、Sは、Xから、期間1年、利息年利10%、遅延損害金20%、利息天引の約定で会社の運転資金3,000万
円を借り入れ、その債務の担保として、甲土地の所有権をXに移転し、Xに対して移転登記を行ったが、甲土地は、従来どおりSが資材置き場等として使用を継
続している。
平成19年5月1日にSは、Xに対する借入金を返済できず、事実上、倒産状態に陥った。Sには、甲土地以外にめぼしい財産はなく、甲土地は、現在、地価
の値下がりによって2億円程度と評価されている。Sの債務を調査したXは、同年10月1日、SのYに対する債務が消滅時効にかかっている可能性があること
を発見し、翌2日に、消滅時効を援用してYに対してYの抵当権設定登記の抹消登記を求めるよう、Sに迫ったが、Sは、同月10日に、Yとの密接な関係や設
立の経緯等があることから、その要請を断った。
平成20年5月7日、Xは、Yに対して、Yの抵当権設定登記の抹消を請求する訴えを提起した。Xの請求は認められるか。
(松岡久和=潮見佳男=山本敬三『民法総合・事例演習』(有斐閣、2006年)111頁以下(「Ⅲ-2 消滅時効」の問題(2)の一部を切り出して、別の問題として修正したもの)
班分け案は次のとおりで、今日のゼミで原告・被告・裁判官を割り振ります。
A 石濱貴文 坂本哲也 原田太輔 金光祐希 佐藤あゆみ:裁判官4(第4演習室)
B 尾崎文保 杉山晴香 深瀬恵美 泉 宏明 嶋田征五 :被告 4(同上)
C 小野 宙 武澤千斐呂 冨士田通子 射場一典 中宇地慧奈:原告 4(同上)
D 川田啓之 谷嶋葉子 長谷川貴也 笹井弘達 松尾光真 :被告 1(第1演習室)
E 小瀧優理 根木孝久 井上 優 叶原みどり 椋木雅人 :原告 1(同上)
F 近藤朋弥 畠中俊樹 大口 敬 中原美鶴 梁河裕亮 :裁判官1(同上)
- 模擬裁判風討論会の議論のポイント
原告の主張すべき骨子
請求の趣旨:所有権に基づく先順位抵当権設定登記の抹消登記請求。
(根拠付けその1)
1) 被告の抵当権の被担保債権は、すでに履行期から5年を経過して商事消滅時効にかかっている。
2) 原告は、抵当不動産の第三取得者であり、判例(最判昭和48年12月14日民集27巻11号1586頁)によれば時効援用権者であるから、消滅時効を援用する。
3) そうすると、被担保債権が時効消滅し、付従性によって抵当権も消滅していることになり、登記は無効で原告の所有権を妨害しているので、所有権に基づく物権的請求権に基づいて、その設定登記の抹消を求める。
(根拠付けその2)
1) については同じ。
2) について、消滅時効についてXに独自の時効援用権が認められないとしても、Sは独自の援用権者である。Sは、無資力状態にあるから、Sに対する貸金債権1,000万円余を被保全債権として、Sの責任財産を保全するため、SのYに対する時効援用権を代位行使する。
3) については、代位行使の結果、抵当権が消滅するので同じ構成となる。
※このほかに、譲渡担保権に基づく物権的請求権の行使という構成や、SのYに対する契約上の抵当権設定登記抹消登記請求権の代位行使という構成もありうる。
被告の主張すべき骨子
(根拠付けその1に対して)
2)について、譲渡担保権者Xの取得している権利について、近時は、形式に沿った所有権ではなく、実質にあわせて担保権として処遇すれば足りると解する学説が通説であり、判例もそのような担保権的構成に歩み寄っていると言われる。そうだとすれば、譲渡担保権者Xにとって、所有権の確保自体は、それほど重要なものではなく、第三取得者の有する利益とは異なる。Xの地位は、むしろ、担保の実質に即して、後順位の担保権者と同列に考えるべきであり、後順位抵当権者に独自の援用権を認めない判例(最判平成11年10月21日民集53巻7号1190頁)により、Xの請求は認められない。
(根拠付けその2に対して)
やはり2)について、Sは時効完成後、時効の援用の要請を拒んでおり、これは時効利益の放棄に当たるか、少なくとももはや信義則上時効を援用できない。これによってS自身が時効援用権を失っているか援用できなくなっており、Sの権利を代位行使するXにも、Sの有する以上の権利を認める必要はないので、Xは債権者代位権による時効の援用もできず、その請求は認められない。
争 点
1) Xに独自の時効援用権が認められるか。抵当不動産の譲渡担保権者は、第三取得者に近いのか、それとも後順位抵当権者に近いのか。また、それぞれが援用している最高裁判決が、独自の援用権について結論を異にしているのは、なぜか。
2) SがXに対して時効援用をしないと表明した行為は、Yに対する時効利益の放棄・援用権の放棄に当たるか。
- 5月14日 占有
今回は、占有に関連する総合的な整理問題です。
2006年5月15日、Xは自己所有の高級自家用車甲を盗まれ、直ちに被害届を警察に出した。その後に甲がどういう経緯をたどってYの元に至ったかの詳細は、警察の捜査でもいまだに不明であるが、2008年4月末に、Xは、甲が関係する別の犯罪事件の捜査の過程で警察から元の所有者として事情聴取を受け、甲の所在を知った。
警察から情報の提供や関係者からの聞き取り調査でXに現在わかっている事実は、次のとおりである。
①2007年12月末頃、A(偽名を使用していた者で正体不明)が代物弁済により甲を金融業者Z社に引渡した、とZが主張していること
②甲の登録名義は、XからZに甲の所有権が移転され、現在Zになっていること
③登録証やナンバープレートは、何人かが書類を巧妙に偽造して作成した偽物であったこと
④Y(自然人・Z社の従業員)が、2008年3月末日に、Zから300万円で購入して引渡しを受けたと主張しており、ZもYの主張を認めていること
⑤購入以後、Yが甲を2日の1度程度、現に使用していること
⑥登録証やナンバープレートが偽物であることにつき、ZやYは、権利取得当時知らなかったと主張していること
⑦甲の現在価格は350万円前後であること
⑧Yが、4月半ばに、甲を修理し30万円を自動車修理工場に支払ったこと(領収書あり)
⑨Yが、4月半ばに、修理済みの甲に時価20万円のナビを取り付けたこと(領収書あり)
⑩Yが、甲の返還請求をしたXに対して、自己の所有物であるとして、請求を拒絶したこと
⑪甲と同程度の中古車のレンタカー使用料は1日2万円相当であること
5月2日にXはY・Zと交渉する機会を持ったが、Yは上述のように返還を拒絶し、Zは話し合いにすら応じなかった。Y・Zの態度に不審を抱いたXは、5月5日に、Yの住所付近に駐車してあった甲に細工して甲を使用不能とした。Yは、警察に告訴すると息巻いている。5月14日現在、まだ訴訟提起には至っていない。
以上の事実に基づき、次の問題に答えなさい。
1 Xは、YまたはZに甲の返還を求めることができるか。
2 Xは、Yに使用料相当額の返還を求めることができるか。仮にできるとする場合、レンタカー使用料相当額を基準として、購入後返還までの間の日数を乗じたものとなるのか、実際に使用したと思われる日数を乗じたものとなるのか。あるいは基準額はレンタカー使用料相当額より低い額となるのか。
3 Yは、Xに対して甲に対する妨害排除を求めることができるか。
4 仮に甲の返還をしなければならないとなった場合、Yは、Xに対して、Zに支払った300万円、修理代30万円、ナビ代20万円の償還を求めることができるか。
5 Zは、Yとの売買契約を解除して(民法562条1項参照)、代金300万円の返還と引き換えに甲及び甲の使用利益の返還をYに求めることができるか。
- 5月21日 即時取得
印刷業者A社は、業績不振を打開するため、B銀行から工場の土地建物に抵当権を設定して5,000万円の融資を受け、本件高速特殊印刷機甲を購入した。ところが、その後も業績は向上せず、Bへの利息の返済や機材納入業者Xへの支払が滞りがちになった。2007年5月14日、Xから支払を強く求められたAは、Xとの間で、それまでの未払い買掛代金債務総額1,000万円を消費貸借の目的とすること、元本の返済期限を2008年5月14日、利息年利7%、遅延損害金年利14%とすることを合意した。同日、Aは、この債務と今後1年間の間にXとの取引により発生すると見込まれる買掛代金債務を担保するため、甲(時価3,500万円相当)の所有権をXに譲渡した。この契約に従って、Xは甲を引き続き無償でAに使用させた。甲へのネームプレート等の設置は行われていなかった。
2007年12月末に、Aのある得意先が倒産し、かなり多額の売掛代金債権が回収困難となったことから、Aの経営状態はますます悪化した。この時点でAのXに対する債務は、2,000万円前後であった。2008年2月10日、Aは、金融業者Yから、運転資金として1,500万円を期限5月10日、利息年利15%、遅延損害金年利21.9%の約定で借り受け、この債務の担保のため、甲をYに譲渡したが、Xとの契約の場合と同様、引き続き甲を使用して営業を続けていた。甲には、「Y社所有・住所・連絡先」を記したネームプレートが貼られた。
2008年5月10日、AがYに対する債務を弁済できなかったことから、翌11日、Yは、同社の従業員をA社に送って、担保権の私的実行であるとして甲を持ち去った。動転したA社の社長・従業員らは、Yに対して清算金の支払を求めることなく、甲の搬出を呆然と見送った。
2008年5月21日、Xが、甲を占有するYに対して、所有物返還請求を行ったところ、Yは、甲は、Yが甲の所有者Aに対する担保権の実行として引渡しを受けたものであり甲の所有権を承継取得している。仮にすでにXが甲の所有者となっていたとしても、占有者Aを所有者と過失なく信じて現実の引渡しを受けたものであり、即時取得により所有権を取得している、と主張した。Xは、Yはいわゆる名うての街金であり、Xの権利取得の状況を知っていただろうと確信していたが、弁護士と相談すると、ガードの堅いYの悪意や過失を立証することは非常に困難だと助言された。
判例の見解に立ったとき、XのYに対する訴訟は、勝訴できる見込みがあるか。
- 6月4日 物上代位
本日の第8回の物上代位は、報告のレジュメの分量22頁を考慮すると、報告と質疑で正確な判例・学説状況を理解するだけで、時間一杯になると想定されます。そこで、本日は練習問題の検討は行わず、次回の6月4日に松岡が新司法試験考査委員会議で東京出張し自習となる回に、物上代位の練習問題の検討と、最終回の山本敬三ゼミとの対抗討論会の立論者5名の選出をお願いしたいと思います。
《練習問題》
1992年3月2日(月)、Xは、Aがその所有している更地甲の上に賃貸用のオフィス・ビル乙を建設する資金として、利率年利8%、20年間で分割返済とする約定で50億円を融資し、甲に抵当権の設定を受け、登記を備えた。
他方、Yは、他のテナントと同様に、1992年6月1日(月)までにAに、建設協力金5,000万円を預託した。その契約によると、建設協力金のうち3,000万円は、完成する乙ビルの入居保証金に振り替え、残りの2,000万円は、無利息でそのままAがYから貸与を受け、2007年6月1日から毎年200万円ずつ分割して10年間で返済する、と定められた。
乙ビルは、1993年7月2日(金・大安)に竣工し、Aは、同日建設業者に残代金を支払って乙の引渡しを受けて所有権保存登記を行い、さらに、Xに追加共同抵当権を設定し、Xはこの登記も備えた。そして、翌7月3日、AはYと、賃料月額300万円、前月末日支払、入居保証金3,000万円(建設協力金の一部を振り替える)、期間20年の約定で乙の1階の一部について賃貸借契約を締結し、Aは直ちにYに当該部分を引き渡した。
2004年7月1日(木)、経営状態の悪化したAに懇請されて、Yは、期間1年、年利3%、元利一括返済の約定で、運転資金1,000万円をAに無担保で融資した。Aの経営は、これによって危機を脱した。
2005年頃からAの経営状態が再び悪化し、2007年6月1日の第1回建設協力金返還時期に、Aは200万円をYに返還することができなくなった。そこで、AとYが協議し、建設協力金・貸付金と保証金・賃料につき、下記のような特約を行った。
- Yは、第1回建設協力金と貸付金の返還を1年間猶予する。Aは、その対価として、80万円をYに支払う。
- Aが2008年6月1日までに2回分の建設協力金400万円と貸付金元本1,000万円を返済しないとき、または、Aに対して差押え、滞納処分、破産、会社更生、民事再生の申立てがなされたときは、Aは建設協力金2,000万円全額につき期限の利益を喪失する。
- ***(下記のとおり、ここが設問によって異なる)
2008年2月末、Aは事実上の倒産状態に陥り、以後、Xに対する返済(残債務約13億円)も、Yに対する返済もできなくなった。2008年5月15日、Xは、抵当権の物上代位に基づき、AのYに対する賃料債権を差し押さえ、Yに対して、以後直接Xに賃料を支払うよう求めた。現在時点は2008年6月4日とする。
問1 上記特約が次のようなものであった場合、Yは賃料債権の支払を拒めるか。拒めるとすればいつまで拒めるか。
「3 前項の規定によりAが期限の利益を喪失したときは、保証金返還請求権も弁済期が到来するものとし、XはAに対する合計6,000万円の反対債権と毎月の賃料300万円を、相殺の意思表示をその都度行うことなく、相殺することができる。」
問2 上記特約が次のようなものであった場合、Yは賃料債権の支払を拒めるか。拒めるとすればいつまで拒めるか。
「3 前項の規定によりAが期限の利益を喪失したときは、XがAに預託してある保証金3,000万円を順次Xの賃料債務に充当するものとし、充当が全部終了した後は、XはAに対する合計3,000万円の反対債権と毎月の賃料300万円を、相殺の意思表示をその都度行うことなく、相殺することができる。」
《解答の概要》
参考文献:基本 松岡久和=上原敏夫=甲斐哲彦「物上代位」鎌田ほか編『民事法Ⅱ』(日本評論社、2005年)63頁以下
より詳しくは、松岡久和「賃料債権に対する抵当権の物上代位と賃借人の相殺の優劣(1)~(3・完)」金法1594号60頁,1595号33頁,1596号66頁(各2000年)、及び
松岡久和「物上代位に関する最近の判例の転換(下)」みんけん544号(2002年)3頁以下
問1
最判平成13年3月13日民集55巻2号363頁によれば、反対債権の取得が抵当権設定登記より前か後かで、賃料債権に対する物上代位と法定相殺(および相殺予約等の特約による相殺)の優劣が決まる。この枠組みに沿って本問を検討すると、建設協力金返還債権の2,000万円は、抵当権設定登記以前に成立しており、Yは、これを反対債権とする相殺が、物上代位に優先することを主張できるから、賃料債権は発生すると同時に消滅し、2,000万円の限度で、賃料債権の支払を拒むことができる。
これに対して、元は建設協力金であった3,000万円については、入居保証金に振り替えられており、早くとも振替時以後に改めて発生したものである。学説には、敷金返還請求権は預託時に発生するとの考え方もあるが、最判昭和48年2月2日民集27巻1号80頁は、敷金返還債権は明渡時までには発生しないとするので、明渡し前には、まだ保証金返還債権は発生しておらず、そもそも相殺はできない。仮に、特約3によって、Xの差押え申立時に返還債権が発生して相殺が可能となったとしても、2004年に融資した1,000万円共々、抵当権設定登記時以降に発生したことは明らかであるから、YはXに相殺を対抗することができない。
問2
特約3後段の合意相殺は、少なくとも保証金部分を除く3,000万円については、問1と同様、抵当権設定登記以後になされているから、YはXに相殺による賃料債権の消滅をYには対抗できない。
悩ましいのは、特約前段の保証金債権3,000万円分の扱いである。形式的には、これも合意相殺の形式を採るから、上記平成13年判決により、YはXに相殺による賃料債権の消滅をYには対抗できない、とすることが考えられる。
しかし、他方で、敷金充当を物上代位に優先させた最判平成14年3月28日民集56巻3号689頁の説くところでは、合意が差押え前になされた本件の場合には、賃料債権の差押え前に敷金契約を締結するか否かは賃貸借契約当事者の自由であり、抵当権者は、そのような状態を甘受せざるをえない。この論理を推し進めると、賃貸目的物の明渡しは不可欠の要件ではないということになり、本件保証金が敷金と評価される範囲では、賃料債権は差引計算によりすでに消滅しているという主張が認められる可能性がある。
最高裁が、この2つの考え方のいずれを採るかは確実には予想できないと言わざるをえないため、Yとしては主張してみる価値があろう。
- 6月11日 譲渡担保(不動産&個別動産)
チェックポイント
本日のゼミのテーマ「譲渡担保」の報告は、「集合財産譲渡担保」を除いて、基本形である不動産と個別動産に限定してはいますが、それでもかなり分量が多く、コンパもセットされていることから、具体的問題の検討は時間的に無理だろうと思います。そこで、今回の報告に即して、とくに学習していただきたいチェックポイントを挙げておきたいと思います。また、参考文献リストにはないですが、私も、田井義信=岡本詔治=松岡久和=磯野英徳『新 物権・担保物権法〔第2版〕』(法律文化社、2005年)で譲渡担保について論じており、今日述べることは、おおむね同書に書いてありますので、適宜ご参照ください。
01 譲渡担保の定義は、所有権的構成(より正確には、所有権以外の財産権についても妥当するので、権利移転的構成)と担保(権)的構成で同じか。
02 譲渡担保と売渡担保の区別はどこにあるか。現在もその違いは意味があるか。
03 譲渡担保が用いられる理由を3点に整理しなさい。
04 (難易度が高い質問)判例は、譲渡担保につき、権利移転的構成を維持しているか。それとも、それを基本にしながら担保権的構成に歩み寄っていると見ることができるか。
05 学説の多くが、判例に反対して担保権的構成を主張するのは、なぜか。
06 担保権的構成を採るときには、実質は担保なのに法形式上は権利移転となることは、虚偽表示に当たらないのか。
07 譲渡担保は、質権に関する344条・345条・349条などの脱法行為として無効ではないか。脱法行為ではなく有効であるとするのは、どういう理由か。
08 不動産譲渡担保の効力の及ぶ範囲については、どういう条文を根拠に判断されるか。
09 譲渡担保の目的物である動産が転売された場合、譲渡担保権者は、転売代金債権にも物上代位により譲渡担保の効力が及ぶことを主張できるか。これを否定する考え方が理由とするのはどういう点か。
10 (不動産)譲渡担保によって担保される債権の範囲については、どういう条文を根拠に判断されるか。
11 動産につき譲渡担保を設定したが、引き続き目的物を占有・利用する者は、どういう権利に基づいて占有・利用ができるのか。仮にそれが譲渡担保権者=債権者に移転した目的物を賃借する契約であった場合、譲渡担保権者は、賃料不払により賃貸借契約だけを解除して、目的物の引渡しを請求することができるか。
12 (不動産)譲渡担保目的物を設定者が目的外使用したり、譲渡担保権者が弁済期前に他に処分した場合、責任追及の根拠は、権利移転的構成と担保権的構成で異なるか。
13 目的物の違法な処分が問題となる場面は、不動産と動産で同じか違うか。
14 不動産の譲渡担保において、登記名義を取得した譲渡担保権者が、目的不動産を第三者に譲渡することは、設定者との関係で常に違法な処分となるか。(ヒント)弁済期前の処分、弁済期到来後受戻権行使前の処分、受戻権行使後の処分で同じか。
15 不動産譲渡担保権者によって目的物が処分された場合、第三者と設定者がどのような関係に立つかについては、譲渡担保の法的構成によって違いが生じるのか。
16 第06問で譲渡担保が虚偽表示に当たらないとする見解では、そのような理由付けと、第三者保護のために民法94条2項の類推適用によることには、矛盾はないか。
17 判例の見解によると、第三者が設定者との関係で背信的悪意者であるか否かは、常に問題になるのか。
18 不動産の譲渡担保権者が倒産した場合、設定者は目的物を取り戻せるか。譲渡担保の法的構成によって答えに違いが生じるか。
19 譲渡担保目的物を第三者が故意に破壊した場合、損害賠償請求権を有するのは誰か。譲渡担保の法的構成によって答えに違いが生じるか。
20 ある動産をXに対して譲渡担保に供した債務者Aが、同一の動産をYに対しても譲渡担保に供した場合、XとYの関係はどうなるか。譲渡担保の法的構成によって答えに違いが生じるか。
21 ある動産をXに対して譲渡担保に供した債務者Aが、その債権者Yから差し押さえを受けた場合、Xはどういう権利主張ができるか。譲渡担保の法的構成によって答えに違いが生じるか。
22 ある動産をXに対して譲渡担保に供した債務者A会社が倒産した場合(破産・会社更生・民事再生)、Xはどういう権利主張ができるか。譲渡担保の法的構成によって答えに違いが生じるか。
23 現在では、譲渡担保権者は、担保権を実行した場合、一般的に清算義務を負うが、その清算方法にはどのようなものがあり、また、譲渡担保権者は清算方式を選択できるのか。
24 譲渡担保設定者の受戻権とはどういう権利で、いつまで受戻権が認められるのか。不動産譲渡担保の場合、仮登記担保法の規定は類推適用されるのか。
- 6月25日 94条2項類推適用
次の事例は、実際に争われた裁判の事実を簡略化したものである。これを読んで、裁判所が下記の【問1】および【問2】にどのように答えたかを考えなさい。
【事例】
病院を経営する財団法人であるXは、その所有する甲地を、その一帯の地上げを計画していたグループの一員であった不動産業者A(代表者B)に売却し、代金3千万円の受領後に移転登記手続をした。この売買契約の交渉や締結には、Xの事務局長Cや理事長Dではなく、Dから依頼を受けたDの従兄弟のEが当たっていた。
Aは、甲地のほか隣接する本件土地(病院の建物に著しく近接した傾斜地)の売却をも希望したが、Eは承諾しなかった。そこで、Bは、Xの所有土地の整理を依頼されていた土地家屋調査士Fを使って、虚偽の理由を示した理由書を示し、「上記売買契約によって買い受けたはずの土地の一部が登記簿上は本件土地に含まれているため、本件土地を分筆して移転登記を行う必要がある」と虚偽の説明を行い、Eや、Eから連絡を受けたCを信用させた。Bは、分筆登記に必要な登記委任状であると称して、Cに再度甲地の登記委任状を交付させた。Cは、当時Fによる近隣土地の分合筆登記が頻繁に行われていたこと、土地家屋調査士としてのFの言動を信用したこと、Eからも登記委任状への署名の依頼があったことなどから、どの土地についての委任状かを厳密に確認しないで、かつ、すでに一度登記委任状を交付していたのを失念して二重に一部空欄の登記委任状を交付してしまった。BとFは、空欄を別のタイプライターを用いて勝手に補充したり文言を付加して登記委任状や念証を変造し、XA間に甲地と本件土地を1億8000万円で売買する契約書があったように見せかけ、Dの名前の三文判を使って移転登記をした。BやFは、本件土地はもちろん、Cに対して甲地についての所有権移転登記を完了した事実も報告しなかった。
さらにその後、Aは、本件土地を不動産業者Y(元は電子部品販売会社であったが不動産業に手を染め、この地域の地上げグループに参加していた)に4億8千万円余で転売し、代金額の約90%を受領した。事情を知らない司法書士の手によって、移転登記が行われた。Y(の代表者)は、訴外仲介者を信頼し、また、XがAに本件土地を売却したことを示すX名義の偽造念証等の写しを渡され、本件土地につきAへの移転登記が既になされていることを確認したため、Aを所有者だと信じた。そのため、Yは、転買契約に際して、本件土地の具体的な現地見分をせず、Bに直接会って所有権移転の事実を確認することもしなかった。
その後、Xは、本件土地がYに移転登記されていることを知り、Yを被告として、本件土地について、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を行うよう求めた(なお、BやFは刑事訴追を受け、Fについては有罪が確定している)。AがY側に補助参加した。
登場人物整理表は略
【問1】 Xには94条2項を類推適用するに足る帰責性があるか。
【問2】 仮にXに帰責性があるとした場合、Yは保護に値する第三者か。
【解答編】
民法94条2項の類推適用についての判示(東京地判平成8年12月26日判タ953号186頁<LEX/DB 28030078>からの抜粋。事例との関係で、一部省略したり、表現を改めた部分がある)
Yは、平成2年10月30日にZへの移転登記が経由されているうえ、念証等に本件土地がAに売却された旨の表示があること、E及びCは、B及びFに対し、右念証等を交付したうえ、本件土地の登記委任状、印鑑証明書、権利証も預けていること、Yは、転買契約締結の際、Zへの移転登記が無効であることを知らなかったうえ、右念証等を見ていたのでZへの移転登記が無効であることにつき無過失であったとして、民法94条2項の類推適用を主張するところ、認定事実によれば、YはZへの移転登記が有効であると信じて転買契約を締結したものであることが認められ、また、他方において、Cは、甲地の所有権移転登記手続のための登記委任状を既に交付していたにもかかわらず、その後Fらからの要請により、どの土地についての委任状であるかを厳密に確認しないまま、Fに二重に登記委任状を交付してしまったものであり、右の点において同人に落ち度があったことは否定できない。
しかしながら、94条2項の類推適用を認めるためには、一方において、虚偽の外形を作出したことにつき当該権利者と相手方との間に通謀があったと認められるのと同視しうるか、又はこれに準じる帰責性が認められなければならず、他において、右外形を信じた者において、右外形が有効なものであると信じたことにつき過失がなかったことが証明される必要があると解されるところ、まず、権利者たるX側の事情につきこれをみるに、Zへの移転登記はFとBに変造された登記委任状と、Xが知らない間に作出されるに至った本件土地の権利証によって経由されたものであるうえ、右念証等も全てFとBに偽造・変造されたものであって、土地家屋調査士の公的資格性とその社会的地位に鑑みれば、Cにおいて、土地家屋調査士であるFが登記委任状や右念証等を偽造・変造することまでを予測して行動すべきであると要求することは酷といわざるを得ない。また、認定のとおり、当時は、Fによる土地の分合筆登記が頻繁に行われており、分筆登記はDの三文判によりXが知らない間に密かに行われていたこと、B又はFが、Cに対して甲地についての所有権移転登記を完了した事実を報告した形跡も認められず、AとXの土地取引においては、CやDではなくEがX側の窓口として具体的な交渉にあたっていたこと、Cが前記の登記委任状を交付するに際しては、虚偽の理由を記した理由書を見せられていたものであること等の事情をも併せ考慮すると、C及びDが登記の具体的内容や経過について錯誤に陥ったのもやむを得ないところであって、前記のとおりCが二重に登記委任状を交付したことをもって、XにAとの通謀に準じる帰責性があるとまで認めることはできない。そして、XがZへの移転登記の存在を知ったのは、Yが本件土地につき本件登記を経由した平成3年1月30日であり、それ以前にZへの移転登記の存在を知ってこれを放置したことを認めるに足りる証拠はないから、結局、Xには、右のごとき通謀に準じる帰責性があったと認めることはできない。
次に、外形を信じたY側の事情についてみるに、Yの代表者は、本件地上げ計画に参加するに際し、地上げ対象地の一部を1回概括的に現地見分したものの、転買契約締結に際しては本件土地の現地見分をせず、売主たるA代表者Bにも会わなかったものであるから、Yが元来不動産業者でなかったことを勘案しても、不動産売買において当然なすべき確認をしていなかったといわざるを得ないうえ、同人が見せられたというXZ間の売買契約成立を証する念証の「なお書き」部分は、タイプライターの印字が「なお」前後で著しく異なっており、一見して真正に成立したか否かを疑って然るべき文書であること、また、本件土地は病院の建物に著しく近接した土地であり、これを真実売却したかどうか一応前主たるXに問い合わせてみるべきであったともいえることに鑑みると、YがZへの移転登記を有効なものと信じたことにつき過失がなかったとはいえない。
したがって、Xの帰責性、Yの無過失のいずれの点においても、Yの民法94条2項類推適用の主張は失当である。
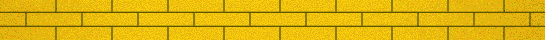
![]()