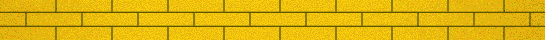
2012年度後期松岡ゼミ検討問題集
-
- 10月1日 物権法定主義
X株式会社は、これまで付近で温泉の出たことがない地域において、Aの許諾の下で、A所有の土地甲を試掘して、温泉を掘り当てた。Xは、甲を5000万円で売って欲しいとAに申し込んだが、Aは先祖伝来の土地なので売れないと拒絶した。
そこで、Xは、甲土地の所有権の取得を諦め、Aとの合意により、Aに対して2000万円を支払うことで、湧出する温泉を永久に利用することができる旨の許諾をAから得たうえ、泉源を含む甲土地の一部を、温泉リゾート施設の建物を建てる目的で年間300万円の地代を払ってAから賃借することになった(賃借権設定登記はされていない)。
Xは、泉源に「温泉リゾート施設建設予定泉源 X株式会社」と書いた看板を設置し、建物の建設計画に着手した。
Xが建物の建設に着手する直前に、Aが経済的に破綻し、Aの債権者Yが甲を差し押さえた。XとYの法律関係はどうなるか。
(平成25年度公共政策大学院入学試験問題「民法」より一部抜粋し修正)
- 10月15日 「相続させる」旨の遺言
配偶者を早くに亡くしたAには、いずれも嫡出の子Y1・B・Cがいた。Aは、「私の所有する甲土地をCに譲る」という趣旨の公正証書遺言を作成していた。ところが、その後Cが死亡し、さらにその後にAが死亡し、Bは相続を放棄した。Aの遺言は、Cの死亡後も修正されることがなかった。Cには一人息子Xがいる。
(1) 登記名義がAのままであった場合、Xは、Y1に対して甲土地の所有権の取得を主張できるか。判例の見解による場合と反対説(遺贈説)による場合で結論が異なるかどうかも検討しなさい。
(2) 無資力状態であったY1は甥のXの権利主張を争うつもりがなかったが、Y1の債権者Y2が、代位してY1名義の単独相続の登記を行い、これを差し押さえた。この場合、XはY2の差押えに対して第三者異議(民執38条)を主張できるか。
(潮見佳男『相続法[第3版]』(弘文堂、2010年)182-183頁のCase197-1、264頁のCase313をかなり修正)
- 10月22日 債権者代位権(転用)
2011年8月1日、XはAに対して、利息年8%を天引きして2000万円を貸し付け、この金銭消費貸借契約から生じる債権を担保するため、同日、同じ契約書に署名捺印する形で、物上保証人B(Aの兄)所有の建物甲(訴外Cの所有地乙に借地権の設定を受けて建てた建物)に抵当権の設定を受け、同月3日に登記を備えた。この契約には、必要最小限のデータ(金額、利率、返済日、利息天引き、担保、物上保証人を含む契約当事者の住所・氏名)しか記載がなかった。
ところが、10月初旬から、暴力団風の怪しい人物が甲建物に頻繁に出入りするようになり、甲の外(乙地上)にゴミが無造作に積み上げられて悪臭が出ていた。Bと連絡が取れなかったため、Bに代わって近隣からの苦情を受けた地主Cが甲を訪ねたところ、そこに居た者はY社の従業員と称する氏名不詳者で、YがBから委託を受けて管理しているとのことであった。悪臭問題に関しては、注意して逆上され恫喝を受けたCが警察に相談したところ、警察からの注意が効いたのか、ゴミの大半はまもなく撤去された。しかし、近隣住民は、怖がって甲には近づかない。
以上のような場合において、次の事情があるとき、Xは、Yに対して、妨害排除請求権の代位行使により明渡しを求めることができるか(抵当権自体に基づく妨害排除請求の可否は余裕があれば検討する程度でよい)。
- [基本設例]弁済期が2012年3月末とされていたがAから返済がなく、Xが同年5月に甲の競売を申し立てたが、買い受ける者がなく、かつ、YがBから甲の管理を委託されているという事実がないと判明したとき
- [変形1]1)の競売等の事情に加えて、建物がこの間の2011年末にBからDに譲渡されて移転登記がされ、YがBからもDからも甲の管理を委託されているという事実がないと判明したとき
- [変形2]1)とは異なり、弁済期は2013年3月末日とされていたため競売に至っておらず、YがBから甲の管理を委託されているという事実がないと判明したとき
- [変形3]1)とは異なり、競売等の事情はあるが、YにはBに対する貸金があり、YがBから甲を賃借して、貸金債権と賃料債務とを相殺処理していることが判明したとき
(完全自作です)
- 10月29日 連帯債務
共同事業を営むAとBは、2004年4月1日、X銀行から事業資金として期間2年、利息年8%・毎月分割払いで1200万円を借り入れ、連帯して債務を負った。その後、2010年4月に、Aの甥であるCが大学卒業を機に共同事業に加わった。その間、Aらの事業運営は堅調に推移し、上記債務の元利金は予定どおり順調に返済され、2年毎に借り換えの形で(利息はその時々の利率に即応して変動)、同額・同期間の融資が繰り返されてきた(以下、利息の問題は省略し、1200万円の元本返還債務を「甲債務」という。)。
2010年3月頃、Aらは、事業拡大のため、X銀行に対して300万円の追加融資を申し込んだ。X銀行は、追加融資を決定したが、今後Aらの事業運営が不調に陥るおそれもないとはいえないと考えた。そこで、①Cを甲債務の連帯債務者に加えること、および、若年で資産の乏しいCには不安が拭えないので、②Cの父親でありAの兄に当たるYをCが負担するすべての債務の連帯保証人とすることを条件として、2010年4月1日に、甲債務の融資期間を従前と同じ条件で延長することに加えて、A・B・Cを連帯債務者として新たに300万円を期間2年、利息年6%で貸し付けた(以下、この元本返還債務を「乙債務」という。)。
ところが、2011年3月、大地震の影響で事業が急速に傾き、Aらは、同年8月に甲乙両債務についての約定利息の支払ができず、取引約定に基づいて期限の利益を喪失した。2012年4月2日、X銀行は、Aから乙債務の全額弁済を受けるとともに、甲債務につき900万円の弁済を受けて、Aに対して残債務300万円を免除する意思表示をした。その後、X銀行は、BやCらに残債務の支払を求めてきたが、支払が得られないため、同年9月3日、
XはYに対して300万円の支払を求める本件訴訟を提起した。
Yは、Xの請求に対してどのような反論が可能か。
千葉恵美子=潮見佳男=片山直也編『Law Plactice 民法Ⅱ 債権編』(商事法務、2009年)175頁[平林美紀]を修正
- 11月12日 瑕疵担保責任
X社は、2008年9月27日にY社から、某国製の靴下を買い入れ、自らは直接商品の引渡しを受けることなく、Yの契約している倉庫業者からXの指示に従って販売先に直接送付するという処理によって転売した(XYとも日本法人であり本件には日本法が適用される)。
しかし、その直後の2008年末から2009年初めにかけて、複数の販売先から、商品に穴あき、染色むら、縫製不良などのあるものが混在し、全体のほぼ半分近くが商品価値のないものであるとのクレームを受けた。しかし、本件靴下は多重に包装してあり、開封検査は物理的には可能であっても、経済的・営業的には不可能であり、XもYも実際に商品の開封検査は行っていなかった。そこで、Xが、1つの販売先から商品の一部の返還を受けて検分したところ、瑕疵のある商品が多数混在していることが確認できた。
そこで、Xは直ちにYに商品の問題について連絡し、2009年2月末頃には製造元にも商品の引取りおよび値引などの交渉をしたが、うまくいかなかった。そのため、Xは、やむなく販売先と交渉して、返品要求は抑えたものの(実際にほとんどの商品が消費者に転売されていて、消費者からの苦情で瑕疵が判明したが必ずしも返品を受けていなかった)、大幅値引きの要求には応じざるを得なかった。また、未売却の品物についても、傷物として安く転売せざるをえず、計5000万円の転売利益を失った。2011年12月7日、XはYを相手どって、損害賠償を求める訴えを起こした。
最判平
- 11月19日 受領遅滞
Xは、YからYが特別に加工した鉄材を買って、スチール製の家具を国内工場数か所で製造している。Yは、2012年8月に新たにXとの間に、この特別な鉄材を100グロス、代金額4320万円、引渡時は10月末日、引渡場所はX指定の工場(複数の可能性有)、配送料は別途清算、代金は納品された商品の速やかな検査・確認の連絡後2か月以内に支払う、とする旨の売買契約を締結した。ところが、10月20日頃にYが納品準備が完了したので配送先を指定するように求めたにもかかわらず、Xは、言を左右して引渡場所を指定しなかった。
そこで、Yは、倉庫に置いておいても費用がかかるので、11月1日に引取りを催告した後、11月15日までに返事がなかったので、同月17日にXに対して契約を解除する旨の書面での通知を行うと共に商品を他に売却した。ところが、同月19日正午頃に解除通知の書面がXに到着した前後に、XがYに対して、商品の配送場所を指定して引渡しを求めるメールを送った。しかし、Yが注文量を納品することができるのは2か月くらい先になってしまう。Xは、それではできた製品の納期に間に合わず、1億円の損害が出ると主張している。
XとYの関係はどうなるか。
遠藤浩=川井健編『ワークブック民法〔新版〕』(有斐閣選書、1983年)183頁[山下末人]を一部改変
[解説]
Yは、債務の弁済の準備ができたことと合わせて配送先を指定するように通知をしており、これは債務の弁済の提供をしたことになる。しかし、Xが配送先の工場を指定しないので、引渡しができない。Xは受領遅滞の責任を負わなければならない(413条)。
この受領遅滞が債権者の受領義務違反による債務不履行責任かどうかについて、従来、判例(大判大4・5・29民録21輯858頁)・(旧)通説は、債権者の受領義務は慣習または特約に基づく場合のほかは、一般的には認められないとして、否定してきた。この考え方(法定責任説)に従うと、受領遅滞は債務者を単に債務不履行責任から免れさせるという消極的な効果を生じるにすぎず、弁済提供の効果と基本的に同じである(492条の弁済提供の効果を参照)。それゆえ、積極的に債務者による契約の解除は認められないのが原則である。
しかし、売買契約や請負契約では、ドイツ民法の定めるように積極的な受領義務を認めるべきだとも考えられ、判例(最判昭46・12・16民集25巻9号1472頁)も、買主に信義則上、目的物の引取義務を認め、その不履行による損害賠償請求を認容した(もっともこの判決の位置づけ自体が争われている)。有力説は、さらに一般的に、債権者の受領義務を肯定し、帰責事由のある違反を一種の債務不履行と考える(債務不履行責任説)。この見解に従えば、Xの受領遅滞を理由にYの契約解除を認めることができよう。
最近の有力説はさらに、契約の趣旨・目的によって債権者の受領義務の有無が定まり、一律に受領義務の有無を決すること自体に批判的である。この見解においても、本件の売買契約では、買主=債権者による引渡場所の指定がない限り、売主は履行することができず、また、代金債務の履行期が商品の検査・確認の2か月後なので、買主に受領義務を認めないと売主に一方的に過酷になるから、本件契約の趣旨に照らして、Xには受領義務が認められることになろう。
ところで、Yが契約を解除しないで目的物を他に売却すると、Yは依然としてXに対して目的物引渡債務を負担し続けるのであるから、あらためてXが引渡しを請求してきた場合には、それに応じなければ債務不履行責任を負うことになる。もっとも、Xはそれまでの受領遅滞の責任(かさんだ倉庫代など)を負うのみならず、損害(それがXの主張どおり1億円の逸失利益だとして)の発生・拡大にはXの行為も寄与しているから、過失相殺(418条)により損害賠償額は相当に減額されることになる。
※以上は、184頁の山下解説の1を基本に置いているが、事例の変形に対応させたほか、誤字や古めかしい表現を修正し、かつ、最近の有力説に関する解説を加えた。さらに、解除の意思表示の到達と解除の成否は大きな問題で、成否どちらの結果もありうる。
- 12月3日 時効制度全般
レジュメの末尾にある時効制度の改正の方向性について、とくに次の点を議論してみて下さい。
1 時効の期間の見直しについて
現在の短期消滅時効の制度は、主として職業別に1~3年の短期期間を定めているが、これは主として中世以来の沿革によるものであって、必ずしも合理性がないとされ、廃止には賛成するものが多い。また、時効期間が民事と商事で倍も違うことや、金融機関でも銀行と信用組合の扱いが異なることには合理性が欠けるとされている。さらに近時のヨーロッパの時効法改正は、人身損害の賠償請求権の時効期間を長期化する例外を伴うものの、おおむね3年程度の時効期間に統一する方向を見せている。こうしたことから時効期間の見直し(短縮化)が提案されているが(不法行為に関する724条も人身損害を除き債権の時効期間の原則と対応させるものとされている)、批判も少なくない。批判としてどういう問題点が考えられるか検討しなさい。一例として、消費者を債務者とする債権については2~3年の短期消滅時効制度を民法もしくは消費者法に例外として置くとの提案があるが、それについてどう考えるか。
2 8の時効完成後の自認行為について
民法の規律の透明性を向上させて国民にわかりやすい民法とするため、条文にない確定判例の準則を条文化する提案がされている。レジュメ13頁の最大判昭41年の時効完成後の自認行為についても、そのような提案がされている。おそらく、判示の①②を抽象化したような例示の下に、自認行為者はもはや時効が援用できないとする趣旨の規定になろう。
こうした提案に対しても、いくつかの問題点が指摘されている。批判としてどういう問題点が考えられるのか検討しなさい。
- 12月10日 債権譲渡と抗弁の切断
個人で雑貨を海外から輸入し、これを販売することを業としている訴外Aは、2012年10月1日、訴外Bから商品甲(原価4万円)を1000個仕入れることを予定し、甲をYに売却する契約をYとの間で締結した。この売買契約によれば、代金は総額5000万円であり、甲は、Aが、10月末日に代金の支払いと引き換えにYに対して引き渡すこととなっていた。
商品の仕入れの資金繰りに窮したAは、10月8日に本件代金債権をXに譲渡し、Xが譲渡を受けた旨をYに電話で知らせたところ、以前からXと取引関係のあったYは、「了解した」旨の返事をした。ところが、10月末日になってもAは甲をBから仕入れることができず、Yは、Aに対して2週間の期間を定めて催告をし、Aがなお履行しなかったため、11月14日にAとの契約を解除した。Dから代金債権5000万円の支払を請求されたYは、Xに対して、売買契約の解除を主張することができるか。
千葉恵美子=潮見佳男=片山直也編『Law Plactice 民法Ⅱ 債権編』(商事法務、2009年)207頁[野澤正充]から問(2)のみを修正のうえ作成
元の問題との違いは、日付や当事者の記号(原告をX、被告をYに改めた)のほか、①AがBから甲を仕入れる契約がYとの転売契約時には未締結であったことにしたこと、②債権譲渡の通知をXが電話で行い、Yが「了解した」旨の返事をしたことである。
①はそれほど大きな問題ではなく、問題文の趣旨を明確にする意図のみである。②には、独自の問題がある。
1) そもそもXは債務者対抗要件を備えたのか。対抗要件を備えていないとすると、抗弁の対抗を持ち出すまでもなく、YはXが債権者であることを否定すればよいのである。
2) 譲受人Xによる通知が対抗要件として有効かどうか問題である。もし、Xが、Aから譲渡通知を行うことを委託されていたとすると、Xの通知はAによる通知と評価できる。債務者対抗要件としての通知は書面による必要はない。電話連絡でも対抗要件としての効力が備わる。
3) Yが「了解した」旨の返事をしたことが、承諾となるかどうか問題であるが、仮に通知で債務者対抗要件が備わったとすると、重ねて承諾を要することはないだろうから、Yの返事はとりたてて意味がないことになる(もっとも、返事をしたことを承諾と解する可能性が残る→5))。
4) 通知で対抗要件が備わって承諾がないとすれば、債務者は通知前に生じた事由に基づく抗弁を譲受人に対抗できる(468条2項)。本件では譲渡通知後のAの債務不履行や解除なので、それが通知前に生じた事由といえるかどうかが問題となるが、後述7)のように、判例・通説はこれを肯定し、Yが抗弁をXに対抗し、解除により支払を拒絶することを認める。
5) XがAから譲渡通知を代行することを委託されていなければ、Xの通知は債権譲渡の通知とはいえない。Yが「了解した」旨の返事をしたことが承諾となるか否かが問われる。承諾とは、債権譲渡があったことを了知したことを示すものと解されており、譲渡の事実をXから知らされて「了解した」旨の返事をすれば、承諾があったと評価される。しかも、判例・通説は、積極的に異議を留めなければ「異議を留めない承諾」をしたものと解して、抗弁が切断されるとする(468条1項)。
6) 他方、「異議を留めない承諾」によって広く抗弁が切断されることは債務者にとって過酷となり、この制度が債権譲受人の信頼や取引の安全を考慮するという趣旨を超えるものとなりかねない。そこで、判例・通説は、抗弁権切断の効果を得るためには、譲受人が善意(公信力説と呼ばれる通説は無過失をも要するとするが判例が無過失まで必要とするか否かは明確でない)であることを要求する。
7) 問題は本問で抗弁が切断されるか否かである。考え方は次のように2通りあるが、おそらくいずれもYの抗弁の対抗を認めるものと思われる。
①判例の見解 譲渡通知の場合と同様、468条1項の「譲渡人に対抗することができた事由」を広く解し、異議を留めない承諾によって抗弁は切断されうると解する。しかし、他方で、本件代金債権が、AY間の売買契約から生じたものであり、甲の引渡しという反対給付の履行との同時履行関係にあり、反対給付が履行されなければ解除によって消滅する運命にあることは、双務契約上の代金債権だと認識して譲受したXは当然知っていて、危険を覚悟すべきであるから、悪意のXに対しては468条1項による抗弁の切断効は生じない。
②通説的見解 判例のように468条1項の事由を広く解すると、譲渡の承諾前に実際には主張できなかった抗弁まで切断されて債務者に過酷なので、468条1項の事由は、承諾前に具体的に主張できた事由に限定される。本件の債務不履行および契約解除は、承諾後に初めて生じた抗弁なので、そもそも切断の対象ではない。
8) なお、契約上の債権の譲受人は、解除の効力から保護される第三者(545条1項ただし書)には該当しないと解されている。
- 1月21日 賃貸借と信頼関係破壊の法理
結論には影響しないと思いますが、ゼミでの討論を経て、微妙な修正を施しました。修正個所は、質問文を含めて5個所のアンダーライン部分(掲示板には4個所と書いてしまいましたが面倒なのでもう掲示板は修正しません)。
Xは、1980年4月からYに賃料月額5万円、敷金・礼金なし、期間2年という条件で一戸建ての甲建物を住居として賃貸してきた。その後、2年毎に契約が自動更新され、賃料額もバブル経済期に高額となり、その後再度下落して、現在では賃料は月額10万円となっている。Xは、甲が相当古びて修繕費等も高くつくし、賃料もこれ以上は値上げできそうもないことから、次回の期間満了時には、賃貸借契約の更新を拒絶し、甲を取り壊して更地にし、ビルを建設することを希望していた。しかし、Yは長年甲に住んでおり、使用の継続を望んでいる。また、Yは、これまで賃料の支払を遅滞したことは何度かあるものの、Xに丁寧に断りを入れてきていてXも支払の遅滞をとがめることはなかった。
2012年12月、Xは、Yが2008年頃からXに無断で従来露天であった甲の北側板塀と家屋との間の空き地部分に屋根をつけ、同部分に旋盤その他鉄工機械類を設置して、その後これを鉄工場として使用しており、これは、賃借家屋の用法違反であるからYの債務不履行に当たるとして、直ちに原状に復するよう催告したうえ、従わない場合には賃貸借契約を解除するという意思表示をして、甲の明渡しを求めた。
これに対して、Yは、Xのいう工場というのは、簡易粗製の仮設的工作物を甲の裏側にそれと接して付置したものにすぎず、甲そのものは賃貸借以来引き続き住居として使っているから、この程度では解除できないという。
Xは建物明渡しを請求することができるか。被告となるYの立場からどういう事実を指摘してどう争えば良いかを考えなさい。
千葉恵美子=潮見佳男=片山直也編『Law Plactice 民法Ⅱ 債権編』(商事法務、2009年)112頁[久保宏之]から問(1)のみに大幅加筆
※今回は答えの用意されていない問題ですので出典を最初から書いておきます。
- 1月28日 過失相殺と素因減額
AはX夫妻の一人っ子でY市立小学校の5年生である。Aは、菓子や果物が大好きな偏食少年であるが、幼い頃から食物アレルギーがあったことから、X夫妻も食べ物についてはAを甘やかして来た。そのせいでもあろうし、X夫妻の体が大きいこともあって、Aは小学5年生にして身長170㎝で体重130キロの巨漢で、太りすぎでスポーツが苦手で俊敏な動きができない。
Aは、学校の遠足において、担任Bほかの引率によりZレジャーランドを訪れ、子供向けのアトラクション施設に入っていた際に同施設の漏電を原因とする火災に巻き込まれた。その際、子供用に作られた施設の非常口からは体が引っかかって避難ができず、煙に巻かれて焦ったAは2階の窓から飛び降りて足を骨折し、全治6か月の大けがを負った。
損害の補填をめぐる交渉が頓挫したため、X夫妻は、引率教員Bらが施設利用に際して安全を確認することを怠ってAに危険な施設を利用させたこと、および、火災の際に適切な避難誘導指示を行わなかったことが過失であるとして、国家賠償法1条に基づきY市に損害賠償を求めると共に、施設が老朽化している瑕疵があったとして民法717条に基づいてZにも同額の損害賠償を求めた。
Yは、義務違反の点は正面からは争わず、事故は予見不可能であったとして義務違反があっても損害との因果関係がないと主張した。他方、Zは、火災の原因自体については争わなかったが、①本件施設は子供用であり、すでに普通の大人以上の体格であったAが使用することは想定できなかった。Aは子供用の施設を利用するべきではなかったし、自ら飛び降りたために骨折したのであって、A自身に損害発生の主たる原因がある。②Xらが食事管理をしなかったためAが普通ではない大きな体になって身動きに不自由を感じていたのであるから、そのための危険に対処するしつけを行うべきだったのであり、Xらにも大きな過失がある。③本件事故は、Bが引率教員として施設利用について適切な指示を行ったり、火災のおりにも適切な誘導避難指示を行えば防ぎえた事故であるから、Yも責任を負うべきであり、Zのみに全責任を追及するのは不当である、と争った。
Aに生じた損害額(たとえば1000万円)には争いがない場合、XのYおよびZに対する損害賠償請求は全額認容されるか。
2012年度最終回を記念した完全オリジナル問題
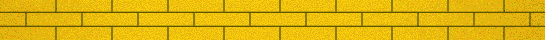
![]()