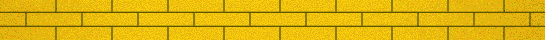
2014年度後期松岡ゼミ検討問題集
- 10月 6日 「時効と登記・再度の時効取得?」
1970年3月、XはAからその所有する本件土地甲を買い受けてその引渡しを受けたが、移転登記を備えないまま、サトウキビの作付けをして占有を開始し、以後、本件訴訟の事実審の口頭弁論終結時現在まで占有を続けていた。
一方、Aは1972年に死亡し、Aの子のBが1982年に相続を原因とする甲の移転登記を行い、次いで、1984年にYに対して本件抵当権を設定しその登記をした。Xは、抵当権の設定等の事実を知らず、抵当権設定登記時において、甲を所有すると信ずるにつき善意かつ無過失であった。
2006年、Yが抵当権の実行として本件土地の競売手続を申し立て、差押えの登記がされたので、Xが執行停止を申し立て、2008年に本件訴訟を提起し、別途Bに対して提起した所有権移転登記手続等請求事件の訴状において本件土地の取得時効を援用した。
1) この場合、後述平成24年判決は、Xの請求は認めているが、どういう理由か。YがXの時効援用を争う根拠とした後述平成15年判決とどこが違うのか。
2) 事例を少し変形して、Xが執行停止の申立てをする前に、競売が実行されて、2007年にZが買い受けて登記名義を備えている場合、XはZに対して、時効取得した所有権に基づいて移転登記の請求をすることができるか。
参照
【平成15年判決:最判平15・10・31判時1846号7頁】
Xが20年間占有を継続したことにより時効取得した土地につき、登記名義人Aに対する勝訴判決を得て時効取得を原因とする所有権移転登記の完了する前にAからBに抵当権の設定登記がされた。Xは、当該抵当権の設定登記の日から更に10年間占有を継続したとして、再度取得時効を援用し、抵当権を譲り受けたYに対し、抵当権設定登記の抹消登記手続きを求めた。
最高裁は、請求を認容した原審判決を破棄し、請求を棄却。
判旨:Xは、当初の取得時効の援用により、本件土地を原始取得し、その旨の登記を有している。「Xは、上記時効の援用により確定的に本件土地の所有権を取得したものであるから、このような場合に、起算点を後の時点にずらせて、再度、取得時効の完成を主張し、これを援用することはできないものというべきである。そうすると、Xは、上記時効の完成後に設定された本件抵当権を譲り受けたYに対し、本件抵当権の設定登記の抹消登記手続を請求することはできない。」
【平成24年判決:最判平24・3・16民集66巻5号2321頁】
設例(1)そのままの事例についてXを勝たせた原審判決を維持し上告を棄却。
判旨:「時効取得者と取得時効の完成後に抵当権の設定を受けてその設定登記をした者との関係が対抗問題となることは、所論のとおりである。しかし、不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において、上記不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは、上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、上記占有者は、上記不動産を時効取得し、その結果、上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。その理由は、以下のとおりである。
ア 取得時効の完成後、所有権移転登記がされないうちに、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了したならば、占有者がその後にいかに長期間占有を継続しても抵当権の負担のない所有権を取得することができないと解することは、長期間にわたる継続的な占有を占有の態様に応じて保護すべきものとする時効制度の趣旨に鑑みれば、是認し難いというべきである。
イ そして、不動産の取得時効の完成後所有権移転登記を了する前に、第三者に上記不動産が譲渡され、その旨の登記がされた場合において、占有者が、上記登記後に、なお引き続き時効取得に要する期間占有を継続したときは、占有者は、上記第三者に対し、登記なくして時効取得を対抗し得るものと解されるところ(最高裁昭和34年(オ)第779号同36年7月20日第一小法廷判決・民集15巻7号1903頁)、不動産の取得時効の完成後所有権移転登記を了する前に、第三者が上記不動産につき抵当権の設定を受け、その登記がされた場合には、占有者は、自らが時効取得した不動産につき抵当権による制限を受け、これが実行されると自らの所有権の取得自体を買受人に対抗することができない地位に立たされるのであって、上記登記がされた時から占有者と抵当権者との間に上記のような権利の対立関係が生ずるものと解され、かかる事態は、上記不動産が第三者に譲渡され、その旨の登記がされた場合に比肩するということができる。また、上記判例によれば、取得時効の完成後に所有権を得た第三者は、占有者が引き続き占有を継続した場合に、所有権を失うことがあり、それと比べて、取得時効の完成後に抵当権の設定を受けた第三者が上記の場合に保護されることとなるのは、不均衡である。
ヒント
【時効の5準則】
①当事者準則1:起算点と完成時で登記名義人に変更がない場合、時効取得は登記なくして登記名義人に対抗できる(177条不適用)。
②当事者準則2:時効完成前に登記名義人から権利を取得した第三者に対しても、時効取得は登記なくしてその第三者に対抗できる(177条不適用)。
③第三者準則:時効完成後に登記名義人から権利を取得した第三者に対しては、時効取得は登記がなければ対抗できない(177条適用)。
④起算点固定準則:時効の起算点を任意に選択することはできない。
⑤敗者復活準則:③の第三者準則によって敗れる占有者は、第三者の登記後に時効取得に必要な期間さらに占有を継続すれば、登記名義人に対して時効取得を登記なくして対抗できる(177条不適用)。
- 相殺
「差押えと相殺の優劣」
A株式会社は、500万円の国税を滞納していたところ、Y株式会社との間の継続的売買契約から生じていた複数の売掛代金債権(総額600万円)を有していたため、X(国)は、2014年5月7日にこのAのYに対するこれらの債権を差し押さえ、Yにその旨の通知をするとともにXに支払うように求めた。これに対して、Yは同日以前にAに対して400万円の貸金債権を有しており、翌8日にこの貸金債権を自働債権として相殺することを理由に、200万円を超える支払を拒絶する旨をXに通知してきた。
そこでXが、同年10月になって、Yに対して差し押さえた債権の支払を求める本件訴訟を提起した。Yは、さらに相殺の主張を追加した。その趣旨は、1月10日にAY間で商品甲の売買契約基本が結ばれて毎月AがYに約定の商品甲を供給しており、5月初めの売掛代金総額が600万円であった(差し押さえられた後は新たな合意により現金取引に切り替えられている)。Aが供給した甲には瑕疵があることが7月末にわかり、Yは甲の複数の転売先からの大量のクレームを受けて転売代金の200万円の減額請求に応じざるを得なかった。Yが転売先全部とのクレーム処理を完了した時点は9月末日で、これによりYのAに対する200万円の損害賠償債権の額が確定した。そこで10月20日にYはこの債権を自働債権とする相殺の意思表示を行い、全額の支払いを拒絶すると主張した。
もうすぐ結審が予定されるが、売掛代金債権と貸金債権の弁済期の組み合わせについて下記の1~4の4つの場合と、損害賠償債権による相殺という5の場合につき、Yは支払を拒絶することができるか検討しなさい。
| |
AのYに対する売掛金債権の弁済期 |
YのAに対する自働債権の弁済期 |
| 1 |
2014年2月10日 |
2014年3月10日 |
| 2 |
2014年9月10日 |
2014年3月10日 |
| 3 |
2014年9月10日 |
2014年6月10日 |
| 4 |
2014年6月10日 |
2014年12月10日 |
| 5 |
2014年9月10日 |
2014年9月30日? |
基本は、千葉恵美子ほか『Law Practice 民法Ⅱ 債権編[第2版]』(商事法務、2014年)178頁[鳥谷部茂]によるが年を改めたほか、5の損害賠償債権について追加した。
- 詐害行為取消権
「金の大仏」事件
個人企業である仏具販売店Aは、工場の建物と敷地(併せて甲と呼ぶ。時価3000万円相当)上にB信用組合に対する根抵当権(極度額2400万円)を設定して運転資金を借りていた。最近、ある寺院から金箔を貼った大型の大仏像乙(売価3000万円)の注文を受けて製作したが、その後その寺が倒産して代金債権が焦げ付いてしまった。そこで、運転資金1000万円をX信用金庫から、500万円を街金(街の金融業者)Yから、いずれも兄弟や親戚を保証人として借り受けたが、経営は行き詰まって、あちこちに債務が増えるばかりであった。
いよいよ店をたたもうと決意したAは、反社会勢力と関係があると噂されるYの強圧的な取立てのおそれがあることを予想し、また、借金をする際にX担当者から受けた酷い扱いに立腹していた。そこで、Yには弁済に代えて乙の所有権を移転することを申し出た。Yは申し出を了解したうえ、乙はそう簡単には換価できない特殊な品物であるとして1600万円程度と評価し(おおむね適正な評価のようである)、貸付元利金を控除した1080万円をAに清算金として支払ってくれた。Aは、それでBに対する債務を弁済して(BはAの危機状況についてまったく知らなかった)甲の根抵当権設定登記を抹消するほか、アルバイトの未払賃金や小口の債務を弁済し、残りを逃亡資金とした。
さらに、Aは、甲を直前に離婚した妻Zに贈与してZ名義に移転登記して、行方をくらませた。
貸金1000万円(+利息・損害金)の回収が見込み薄となったXは、YやZに対して詐害行為取消権を行使して、甲や乙の返還を求めることができるか。
完全自作
- 受領遅滞
「売れない家具」事件
Yは、XからXが特別に加工した鉄材を購入してスチール製家具を製造販売している。Yは2014年3月にXから、新たに鉄材2500個を5000万円で購入し、6月末にYがXの倉庫にトラックを差し向けて引渡しを受ける、支払いは引渡しの2か月後とする売買契約を締結した。しかし、業界が不景気で高級家具の販売が不振に陥ったため、Yは6月末には引取りに行かなかった。
Xは、売約済みの商品を長い間倉庫に入れておいても場所を取るばかりなので、契約を解消して安くでもよいから他に売り、差額を損害としてYに請求しようと考えた。
8月末にXは問題の鉄材のうち1000個をAに1600万円で売却して引き渡し、同時にYに対して契約の一部解除を通告し、残り1500個の引き取りと3000万円の代金の支払い及び400万円の損害の賠償を求めた。倉庫中には1500個しか同種鉄材は存在せず、あらためて製造するには何か月かを要する。Xの請求に対して、Yは、契約通り2500個の引渡しをせよと主張し、相当期間内にそれができないのであれば、こちらから契約を全部解除するという意思表示をした。
XとYの法律関係はどうなるか。
遠藤浩=川井健編『ワークブック民法〔新版〕』(有斐閣、1983年)183頁の第1問を変形
- 債権者代位権
報告班の南部航貴君・櫻井涼太君が作成した問題。基本問題ですが、意外と分岐が多く、事例を分析してきちんと書くには良い練習になります。
絵画収集家Nは、平成26年3月3日、古物商を営む友人Sに対し、著名な画家の絵画を200万円で売却して、引き渡した。その際、Sに請われて、代金の支払は2日後の同月5日とする旨約定した。Sは、同月5日に代金を支払わず、その後は不在がちで連絡すらつかない状況であった。心配になったNがSの資産調査を行ったところ、Sは、平成15年12月20日、同業者のMに利息年5分、返済期限を平成16年12月20日と定めて500万円を貸し付けているが、SはMに対して返済を求めることなく現在(平成26年12月15日)に至っていること、及び、SにはMに対する当該貸金債権以外にみるべき財産はないことが判明した。
Nがなしうる主張を挙げ、検討しなさい。
- 委任
「老後の共生計画」事件
AとYは独身の友達であり、老後は一緒に暮らそうと約束していた。そのため、AとYは毎月一定額をY名義の総合預金口座に共同の資金を積み立て、その額はすでに2000万円を超えていた。Yは、自分自身の別資金を用いて、株式投資等で大きな成功をおさめていた。そこで、Aは共同資金についても1000万円を定期預金とし、それを超える額についてYに同様に運用を任せることを希望した。Yはそれに同意して、1000万円を定期預金とし、当時の総合預金口座の残額1500万円余のうちの1000万円を自己資金と同様の株式投資等で運用してきた。
2014年8月、Aが飛行機事故に遭って行方不明となった。状況からみて生存の可能性はきわめて低く、10月には捜索が打ち切られ、認定死亡の手続が採られた。Yは、預かっていた共同資金の総合預金口座の残額からおおよそ半分強の250万円を支出してAの葬儀を執り行ったが、Aの身内は誰も来なかった。YはAに甥Xがいるとは聞いておらず、XもAとは没交渉で一度もAに会ったことがなかった。
2014年12月、XがAを相続し、2014年8月の事故によるAの死亡時点での投資委任契約の終了を主張して、①共同資金中の定期預金中の500万円、②総合預金口座の葬儀前の残額中の250万円、③投資運用された1000万円の半額の500万円、④その時点までの運用益108万円の半額の54万円の合計1304万円の支払いをYに求めた。
Yは、そもそも法律上の委任契約が成立するとは認識していなかったと主張した。さらに、①の請求は認めるとしても、②についてはAの積立分から葬儀費用を支払ったため残額はゼロである、③④については、投資対象の株式価格が8月以降に急落して運用はトータルでマイナスになっており、返還額は10月末で380万円にすぎない、と主張した。
これに対して、Xは、②について、委任契約は8月のAの死亡時点で終了しており、共生計画の資金を葬儀に用いるべきではないし、葬儀費用の支出はYの好意によるY自身の支出にすぎない、③④について、8月以降の資金運用のリスクをA(したがってその相続人X)は負わない、と反論した。また、12月から1月にかけての株価急騰により現時点で清算すれば、元本と運用益(の半額)で554万円以上になっていると付け加えた。さらに、⑤として、仮に10月の認定死亡まで委任契約が続いていたとしても、その間は、受任者Yは忠実義務や善管注意義務を負うから株価急落による損害が発生すれば、その賠償義務があると主張した。
Yは、②~④のXの主張を争い、とりわけ③④についてAの生死がわからない間は従前の運用を続けるのがむしろ適切であると述べた。また、⑤についても、資金運用の委託は好意により無償で行っており重い義務を負っていないし、義務を負うとしても、Y自身も株価低下により同じ投資で同程度の損失を出しており過失はない、と反論した。Yから相談を受けた諸君は、どう答えるか。
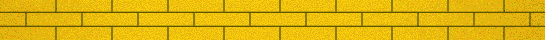
![]()