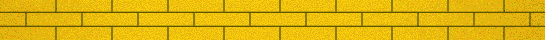
2013年度前期松岡ゼミ検討問題集
- 4月8日 ディベート練習問題「偽の監視装置」
前置き
京大の法経本館にさえ実際の監視ビデオカメラが設置される時代なので、今では成り立たない問題かもしれませんが、そこは目を瞑って、ビデオ監視装置が非常に高額であった時代であることを前提に考えて下さい。
本題
「ビデオ監視装置で犯行現場をきちんと捉えられるのは、宝くじとどっちこっちの確率かもしれない。それにしては、器材といい、ランニングコストといい、相当高くついてしまう。」と考えた自称発明王のYは、スイッチやコードなどを含め外形だけは防犯ビデオカメラにそっくりの空箱商品「MYTEL FREE」を、実物の100分の1の値段で売り出した。Yの商品「MYTEL FREE」は、Xの本物の監視ビデオカメラのデザインや商標や特許権を侵害するものではなかった。買う側も偽物であることはよくわかっていて、経費節減に苦しんでいた企業チェーンなどがこれを大量に購入したため、本物の防犯ビデオカメラメーカーは軒並み売上がダウンし、Xの売上も前期比の半分になって経営危機に陥った。
XがYを相手取って、空箱製品の販売差止と損害賠償を求めることはできるか。民法709条を参考に、請求を認容するにせよ、棄却するにせよ、反対意見を想定して説得力のある理由付けを試みなさい。
対比して考えると良い例
1 百万遍付近では昼食として安くて早い牛丼が学生や一部教職員の人気を集めており、Xは月間売上げ平均300万円を誇っていた。まだ需要があると判断したYがXの真横に新規に牛丼チェーン店を開店したため、Xの平均売上げは200万円に落ちてしまった。
2 百万遍付近では昼食として早くて手軽なハンバーガーが学生や一部教職員の人気を集めており、Xは月間売上げ平均300万円を誇っていた。Xの近隣に開店したYが、「Xのハンバーガーは猫肉100%」というデマを流したため、Xの平均売上げは100万円に落ちてしまった。
※ネタ元は道垣内正人「爆弾装置付き金庫の偽物」(自分で考えるちょっと違った法学入門シリーズ)法学教室117号(1990年)15頁以下です。さらにネタ元のアメリカの類似事件を紹介し、上記の例に近いケースを問題にしています。「MYTEL
FREE」等の詳細は私のオリジナルです。また対比する例はいずれもフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
- 4月15日 抵当権の侵害と妨害排除
「大東亜学生援護会事件」
2010年4月1日、X銀行は、Aに対して賃貸マンション建設のために5億円を融資し、A所有のマンション建設用地に抵当権の設定を受け登記を備えた。2011年4月1日、完成した本件賃貸マンション甲にも共同抵当権の追加設定を受け、登記を備えた。Aは税金対策も兼ねた不動産管理会社Bを設立し、甲をBに一棟貸しし、各住戸の転貸や管理の業務はBにやらせる仕組みをとった(いわゆるサブリース方式)。
Bは2010年中から、甲を交通至便な場所に立つ高級賃貸マンションと売り込み、賃借人を募集したが、甲の完成時にも30戸のうち、賃借人が入ったのは13戸に過ぎず、A(およびB)のマンション経営には最初から暗雲が漂っていた。Yは「大東亜学生援護会」と称する団体で、A(およびB)の経営が怪しくなった2012年8月頃、Bから甲の305号室を借り受けた。同年10月、ついにA(およびB)が完全に破綻し、破産手続が開始された。そこで10月12日にXは、甲とその敷地について本件抵当権の実行を申し立てた。
このころから、305号室には、非常にたくさんの外国人が出入りするようになった。彼らの態度は非常に丁寧であったが、日本語がほとんど通じず、習慣の違いやゴミ出しの問題でマンションの住民や近隣住民とトラブルが生じていた。A・Bが破綻したことや、305号室のこうした状況を嫌って、マンションからは次々に賃借人が退去し、現在の賃借人は305号室を含め6戸にすぎない。甲と敷地の一括売却の価格は8億円とされたが、買受希望者が現れず、売却の目処は立っていない。
Xから相談を受けた弁護士であるあなたが状況を調査したところ、次の事情が判明した。305号室の住人(Zらとする)は、現在のところ、中国・フィリピン・ベトナムなど数カ国から来た外国人学生25人であり一部は氏名も不詳である。Zらは、Yとの間で契約を結び、一定のアルバイトへの従事を条件に各人が非常に安い月額賃料を支払って居住できることになっていたが、月毎に入れ替わりが激しいようである。Yは連絡先が留守番電話になっており、契約書に記載された住所地は存在しなかった。しかし、Bは、Yが契約時に敷金と賃料を一括して支払った(と記録されている)ため、この点に気付いていなかったとBの事務員は証言している。
弁護士であるあなたは、Xは誰を相手にどういう請求をすることが可能かを、Xに説明し、そのうちで一番よい方法を推薦しなさい。
本件はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
- 4月22日 即時取得
「所有権留保侵害事件」
XやAは建設機械等の売買を業とする株式会社であり、Yは建設機械等の輸出入、販売を業とする株式会社であり、いずれも高額の建設機械を多数取引する実績を有していた。平成16年から平成19年にかけて、XはAに対して本件建設機械合計7台(甲6台、乙1台)を順次売却して引き渡したが、いずれも売買代金が完済されるまでの間は、甲・乙の所有権をXに留保する旨の特約が付されていた。しかし所有権留保を示すシール等は貼られていなかった。また、H社製の建設機械乙には機械の位置情報を得ることができる装置があり、その装置は、当該建設機械が一定の範囲外に移動した場合に、当該機械のエンジンを停止させたり、電子メールで異常の発生を自動的に通知したりするなどの盗難防止機能を有していた。
Aの代表者Bは経営状態が悪化して資金繰りに窮し、売買代金を完済していなかったにもかかわらず、Yに対して、甲・乙を平成19年から21年までの間に順次転売した(他社から同様に仕入れた建設機械合計21台も同様に転売した)。
XAY間には従来から多数の中古建設機械の取引があったが、取引対象物件の所有権についてトラブル等が発生した経験は一度もなく、YはこれまでXやメーカーに問い合わせたことがなかった。本件においてYの営業担当者はAの残債務の有無の確認を口頭でも行っていなかった。
Yは平成21年までの間に甲を海外の業者に転売して輸出した(もはや原物の所在はわからない)。乙はまだYの手もとに残っていた。平成21年6月にBの不正転売行為が発覚し、同月24日にAは破産手続の開始決定を受けた。
Xが、甲の所有権侵害を理由とする不法行為責任を追及して相当額の損害賠償を請求したところ、裁判所は、下記に引用する判決(要旨のみ掲載)により損害賠償請求を棄却した。
XがYに対して所有権に基づいて乙の返還請求の訴えを起こしたとすれば、どういう結論になるだろうか。この判決を参考に考えてみてください(判決の考え方に賛成でも反対でも良いです)。
本件はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
(札幌地苫小牧支判平成23・9・27判タ1375号150頁を素材にした自作問題)
�
特定物である中古建設機械を購入するに当たって、その買主には、真の所有者の権利を侵害しないよう、売主が当該建設機械の所有権を有するか否かについて調査及び確認をすべき義務がある。
しかしながら、Yは、Aとの間で、長年にわたって中古建設機械の取引を継続していた。Aは地元においては相当程度の信頼を得ていた業者であった。Aが倒産したのは、代表取締役Bが突然失踪したことによるものであった。さらに、AY間の取引においては、本件以前にトラブル等が発生したことは一度もなかった。これらの事実から、AY間の取引については、Aの経営基盤等に対する信頼や、長年の取引によって培われた互いの信用がその基礎にあったということができ、また、Aの倒産が突然のものであったことからすれば、YがAの経営状況に疑念を差し挟む余地はなかったから、本件各売買契約が締結された当時も、YにおけるAに対する信頼や信用は維持されていたものといえる。そして、かかる状況の下において、Yが、本件各売買契約を締結するに当たって、Aが本件各機械の所有権を有するか否かについての確認をメーカー等への問い合わせを行わず、各機械に係る残債務の有無を担当者間において口頭ですら行わないことがあったのも、無理からぬものであった。
また、建設機械に所有権留保等の担保が設定されているか否かは、当該建設機械の外観からは知り得ないものである上、建設機械については、不動産や自動車とは異なり、登記や登録等の権利公示方法が存しないから、担保権者が自らの権利を第三者から保護しようとするのであれば、担保権の存在を何らかの方法で明示すべきであり、このことは、シール等を貼付するという極めて簡便な方法によって実行することができる。Xは、所有権留保特約付きの割賦販売等で売却した建設機械にシール等を貼付するのは、ユーザーからの抵抗があることから、権利公示方法として定着していないと主張するが、同業他社には、シール等を貼付しているものもある。また、Xは、戸外で使用される建設機械においては、シール等が容易にはがれてしまうことから、シール等を貼付する方法は採りえないと主張するが、運転席内等の場所にシール等を貼付するなどの方法も採りうるから、シール貼付は不可能ではない。要するに、Xは、シール等を貼付することによって、本件各機械が所有権留保物件であることを明示することが容易に可能であったにもかかわらず、これをしなかったのである。
さらに、XはBの不正転売が明るみに出るまで事態を把握していなかったが、このことから、Xが盗難防止装置を適切に作動させていなかった疑いがある。本件甲・乙については、メーカーの売却先への定期巡回サービスも行われていなかった。
Xは、本件各売買契約の締結に当たって、簡易な方法による所有権の有無の確認しかせず、また、かかる方法による確認すらしなかったのであるから、それに伴うリスクを負うべきともいえる。
しかしながら、他方、Yがかかる方法によったのは、本件各売買契約の締結に至るまでに形成されたAに対する信頼等を基礎にしていたものであり、無理からぬ面があったといえる。また、Xは、所有権留保物件である本件各機械について、容易に行うことが可能であったシール等の貼付による権利の明示をしなかったこと、Xがかかる方法を採らなかったのは、ユーザーからの抵抗を避けるためであったこと、これにより、同各機械は、所有権留保物件であるか否かについて、その外観から判別することができない状態にあったことなどの事情にかんがみると、Xは、権利が第三者に対して明示されない動産に対する所有権留保という、極めて脆弱といえる担保の設定を受けたものである上、ユーザーからの抵抗を避けて取引を促進するために、自らかかる状態を作出したといえるから、これに伴うリスクは、X自身が負担すべきものであるといえる。そして、Xが本件各機械の状態等に関する定期的な管理等を怠っていたといわざるを得ないことを併せ考えると、Xがかかる担保を失ったことについては、まずは担保権設定者であるAに対して責任を問うべきであり、これが不可能となった場合には、自らそのリスクを負うべきであって、事情を知らずに取引に入った第三者であるYに対して責任を問うべきではないとするのが、損害の公平な分担という不法行為制度の趣旨に適うというべきである。
したがって、本件においては、本件各機械が高価な建設機械であったことや、Yが中古建設機械の販売等を業とする会社であることなどを考慮しても、Xの甲に対する所有権を侵害したことにつき、Yに過失があったとまではいえないというべきである。
Xは、建設機械の取引においては、メーカー等に問い合わせをする方法により、所有権の有無の確認をすることが可能であると主張する。
しかしながら、本件において、建設機械取引における所有権の有無の確認方法として、メーカー等への問い合わせが一般的な商慣習であるとはいえない。そして、Yの主張するとおり、かかる方法による確認は、取引の横取りや中止を引き起こすおそれがある。そうすると、メーカー等への問合せによる所有権の有無の確認が、建設機械取引における確立した商慣習であるとまでは認められないから、Yがかかる方法をとらなかったからといって、直ちにYに過失があったとまではいえない。
以上によれば、本件において、Yが、本件各機械の所有権がXに留保されていたことを知らずに本件各売買契約を締結した上、同各機械を輸出し、転売したことによって、Xの同各機械に対する所有権を侵害したことにつき、いずれの契約においても、Yに過失があったとはいえない。
- 5月2日 答案練習・代理と錯誤
「代理問題アラカルト」
問題
個人商店を経営するYの店員Aは、ときおり、Yから必要な品物の種類・数量・納品時期・支払日等の決済条件の指示を受けて、商品を発注していた。高齢のYはパソコン等の機器の操作が苦手だったので、ネットショッピングに長けている若いAに、商品の型式・性能比較などの知識や格安販売情報を集めさせ、発注物、発注先などの詳細の決定を任せていた。
2013年5月2日、Aは、X社に対して、Y商店の名前で担当Aと明記して、10グロス*の商品甲をメールで注文した。次の場合、YはXからの納品を受領して代金請求に応じなければならないか。理由をきちんとつけて答えなさい。
*1グロスは、12ダース=144個
小問1 YがAに指示したのは10ダースの甲の発注だったのに、聞き違えたAが10グロスの注文をした場合
小問2 過去にYがAに商品乙を10グロスの発注を指示したことはあったが、商品甲の発注を指示した事実はなく、Aがどういう思惑によってか勝手に商品甲を発注した場合
小問3 YはたしかにAに商品甲を10グロス発注するように指示していた。しかし、Xの見積りは、他に比べて相当に高額であった。にもかかわらず、AがXに発注したのは、かねてからAの友人BがXの販売担当をしていて、Xに発注してくれればYには内緒でバック・マージンをAに払ってくれるというので、Xからの購入を決定した場合
解説
①小問1は、代理人の錯誤の問題であると気づけば簡単な基本問題である。101条1項に該当することは明記して欲しい。
問題文③を反対解釈すれば、①のケースでは、Aに購入先・価格決定等に裁量の余地がなく、単なる使者であったと考える余地もある。そう考えれば、本人の意思伝達の課程での錯誤なので、101条は適用されず、本人自身の錯誤主張の可能性があることになる。
代理人Aが本人Yの指示を聞き間違えるなどして実際の指示とは異なる意思表示をした場合には、代理人Aに表示行為の錯誤があると考えられる。したがって、101条1項によって、その錯誤に重過失がない限り(95条但書)、本人Yは錯誤無効を主張できる。その場合、10グロスの売買契約は無効となり、X社からの代金請求に応じなくても良い。
②小問2は、表見代理の各規定への当てはめがきちんとできるかを問う問題で、後半の重畳適用の議論は少し難しい。110条を一般条項的に広く適用しようとする議論も可能である。
YがAを普段から発注担当者として肩書きなどの使用を認めていた場合には、実際に常に発注のための代理権を与えていたわけではなかったとしても、代理権授与表示(109条)があったとされやすい。この場合には、実際本件の具体的な発注行為につきYがAに代理権を与えていなかったとしても、そのような代理権の外観を過失なく信じたX社は保護される。したがって、上記のような代理権授与表示があると認められ、X社が善意・無過失であれば、YはX社の代金請求に応じなければならない。それ以外の場合には、原則に帰り、無権代理として効果がYには帰属せず、Yは、Aの行為を追認(民法113条)しない限り、代金請求を拒むことができる。
YがAを普段から発注担当者としていたわけではなかった場合にも、仮に代理権授与表示とみられる事実があれば上記と同様であるが、そうでなければ、109条は使えない。可能性があるのは、110条・112条の適用である。AがYから与えられた商品乙の仕入れのための代理権を基礎に権限外の商品甲の仕入れをしたとして権限踰越の表見代理と考える余地もないわけではないが、商品乙の仕入れのための代理権授与は過去の話ですでに取引が終了していて代理権も消滅していたと考えられるので、直接の適用は難しい。一方、Aは商品乙の仕入れのための代理権が消滅後に同じ種類の取引を同じ相手としたわけではないから、112条の典型的な場合でもない(もっとも、同種取引と見て同条の適用を考えることは可能であろう)。しかし、判例・通説は、両条の重畳適用を認めている。すなわち、Aが過去になされた乙商品の発注代理権が消滅したにもかかわらず、その後にその代理権の範囲を超えて甲商品を発注した場合でも、濫用されるような形で代理権授与を伺わせる外形を放置しておいた点につき本人Yに帰責性があり、X社が代理権の欠如や踰越を過失なく知らなかった場合には、YはXに対して有権代理の場合と同じ責任を負い、代金請求に応じなければならない。これらの要件が充たされなければ、Yは、Aの行為を追認(民法113条)しない限り、責任を負わない。
①で述べたように、②のケースでもAが使者だったと考える余地がある。その場合には、使者の行為につき表見代理規定の類推適用の余地があるかを問う必要が出てくる。おおむね代理人として行動した場合と同じ扱いになるだろう。
③小問3は、代理権濫用の場合を問う問題である。無権代理説については論及しなくても良いが、反対説である権利濫用説に立つ場合でも、少なくとも判例・通説の93条類推適用論に触れることは必要。逆に反対説に触れなくても減点せず、むしろきちんと反対説からの問題指摘が書ければ加点するような採点方法を採ることが多い。
Aは現実に与えられた甲商品の発注代理権の範囲内で行動しているから、原則として有権代理だと考えられる。たしかに、委ねられた裁量の範囲を逸脱するAの行為はYが授与した代理権を超えるもので無権代理である、として表見代理による相手方保護を講じる考え方もありえないではないが、代理人の内心の意図次第で代理権の範囲が左右され、相手方が保護されるために自ら善意・無過失などを立証しなければならないなど、相手方に過大な負担となって取引の安全を害するので妥当ではない。
もっとも、原則として有権代理だと考えても、本件のようにXの従業員Bが代理権の濫用につき悪意どころか代理権濫用を誘引した場合にまで、原則を貫くのは妥当ではない。判例・通説は、Aが本人のために本人の計算で行動するという代理行為の外観と、現実には経済上の利益の一部を自己又は第三者に帰属させるという内心の意図が食い違っている点を、心裡留保(民法93条)に類する構造を持つものと捉え、同条(但書)を類推適用する。すなわち、代理権濫用につき悪意もしくは善意でも過失のある相手方に対しては、本人は代理行為の効果帰属を否定することができるとするのである。この考え方に対して有力な反対説は、そもそも93条の適用場面とは異なるので類推の基礎がないとか、相手方にささいな過失があるにすぎない場合に、本来本人が負担すべき代理権濫用の危険を転嫁するのは妥当でないなどと批判し、むしろ相手方が悪意もしくは重過失の場合に限って、権利濫用・信義則という一般条項によって効果帰属を否定すべきだと主張している。もっとも、本件ではBが悪意であると思われるので、いずれの考え方をとっても、YはX社からの代金請求を免れることができるであろう。
-
5月8日 錯誤
「眺めの良い部屋」事件
2011年4月に、Xは、不動産販売等を業とするYから、京都市内にある鉄筋コンクリート造10階建の新築予定マンション甲の8階の801号室を5000万円で購入し(本件売買契約)、2012年3月の甲の完成後、代金を支払ってその引渡しを受けた(Xと金融機関との間で住宅ローン契約が35年間継続するものとされたが、その点は本問では問題にしない)。甲の宣伝用パンフレットには、甲が交通至便の中心街に位置することのほか、6階以上の全室から市内中心部が見渡せるほか、五山の送り火(大文字山)が見えるなど眺望の良好さも大きく謳われていた。Yの販売担当者Aはさらに、建築規制条例の規制強化によってこのマンションの付近には高層建築物は建てられなくなるため、将来も眺望が妨げられるおそれはない、と説明してXに購入を勧めた。そこでXは眺望に惹かれ、近隣の建物の屋上(8階相当)から送り火が見えることを確認したうえで、本件売買契約を締結した。
ところが、購入した次の年2012年の7月に本件甲と大文字山の間に条例の特例を活用した15階建の高層マンション乙が建てられたため、Xの部屋からは、大文字山はまったく見えなくなってしまった。以後、XとYの間で本件紛争が生じ、調停などが試みられたが不調に終わった。調停の中では、乙の建築計画について、販売時点ではYは知らず、知らないことに過失はなかったと認められた。
2013年5月現在、Xは、本件売買契約の効力を否定して、Yに売買代金5000万円の返還を求めることができるか。
なお、消費者契約法4条による契約の取消し(期間制限にかかる可能性がある)、Yの不法行為又は契約締結上の過失による損害賠償責任は、今回は検討しなくてよいものとする。
千葉恵美子=潮見佳男=片山直也編『Law Practice 民法Ⅰ 総則・物権編』(商事法務、2009年)56頁[鹿野菜穂子]より若干変形
- 5月13日 認知
「人気アイドルの隠れた父が出現」事件
XがYとの同棲中にAを生んだが、その後婚姻することなく別れ15年の月日が流れた。
A(15歳)が人気アイドルとして売り出されると、それまで音信不通であったYが、XとAの住居や楽屋を尋ねては金をせびるようになった。
困惑したXは、Yに500万円を渡して、今後は一切の金銭を要求しないこと、及び、Aの認知を行わなわず父と名乗らないことを内容とする念書を書かせ、署名及び拇印を押捺させた(Yは嫌がらせに血判で拇印を捺した)。ところが、この約束に反して、Yは、Aが成人する前に認知届を提出し、週刊誌等にAの父としてのインタビューを売り込むなどの行為を繰り返している。
小問1 Yの認知については、だれがどのように争うか。認知は有効か。
小問2 XはYに対して念書での約束違反を理由に500万円の返還を求めることができるか。
※議論は小問1に重点を置いてください。
明治大学民法研究室編『民法ゼミナール教材 第4版』(有斐閣、1992年)152頁より若干変形
参考 最判昭37年4月10日民集16巻4号693頁:「子の父に対する認知請求権は、その身分法上の権利たる性質およびこれを認めた民法の法意に照らし、放棄することができないものと解するのが相当である」。
- 5月27日 無権代理と相続
「被害者も加害者もいなくなった」事件
病気で意識が朦朧とした寝たきり生活を送っていたA(83歳)には、2007年当時、妻B(82歳)と嫡出の長男C(60歳)と次男D(55歳)がいた。A・Bの身の回りの世話は、A・Bと同居しているDとその妻E(50歳)が面倒をみていた。D・E夫婦には子供はいない。
2007年4月20日、Dは、日頃から付き合いのある不動産業者Xとの間で、Aが所有する甲土地とその地上の乙建物を2800万円で売却する本件契約を結んだ。Dは、この契約にあたって、Aが甲・乙の売却のために代理権をDに授与した旨を記した委任状、実印、印鑑登録証明書、甲・乙の登記済証(当時)*をXに示した。しかし、この委任状はDが偽造したものであり、実印等もDが勝手に持ち出したものであった。
甲・乙の代金の一部800万円はすでにXからDに支払われていたが、甲・乙の引渡しや移転登記は、10月20日に残代金2000万円の支払と引換えに行うという約定であった。
2007年5月7日に、AはDX間の契約のことを知らないまま他界した。さらに、2007年9月30日に、Dが交通事故で突然死亡した。AもDも遺言は残していない。現在、B・Eが甲・乙の占有を続けている。
本件契約は履行されないまま現在(2013年5月27日)に至っている。Xは、誰に対して、どのような請求をすることができるか。
* 全国の登記所でオンライン化が完成した2008年7月14日までは、オンライン庁の指定を受けていない登記所においては、依然登記済証が交付される取り扱いになっていた。また、既に交付された登記済証は、オンライン庁に登記を申請する場合も、そのまま使うことができる(登記済証が提出されたときは登記識別情報が提供されたものとみなされる。不登附則7条)。
千葉恵美子=潮見佳男=片山直也編『Law Practice 民法Ⅰ 総則・物権編』(商事法務、2009年)104頁の事態β[潮見佳男]より若干変形
- 6月3日 民法177条総論
「不動産の所有者は誰」事件
多数の貸家を有するAは、Y1に甲・乙2軒の家を貸していたが、Y1の家族構成の変化で1軒が不要になっていることを知り、そのうちの乙を自分の愛人Y2に手切金代わりに贈与して住まわせることを思いついた。AはY1と交渉し、乙から立ち退いてくれるなら、甲をY1に贈与すると提案した。2008年4月、Y1はこの提案を承諾して乙から立ち退き、乙にはY2が入居した。しかし、Yらは登記の費用を用意できなかったので、登記名義はAのままとなっていた。
その後数年の間、甲・乙両建物の固定資産税を課税され続けたAは、Yらにその償還と移転登記への協力を繰り返し求めたが、Yらは応じなかった。友人に「移転登記をするまでは贈与は不完全で所有権はまだAにある」と教えられたAがX1に相談したところ、X1は同情して、長年優良な賃借人Y1の住んでいる甲なら買ってもよいと言った。
そこで、2013年4月に、Aは、甲をX1に売り、他方、乙を妻X2に贈与し、それぞれ5月に移転登記をした。X1がY1に賃料を請求したところ、Y1は甲は自分の物だと主張して支払を拒んだ。他方、X2は、財産管理に興味がなく、そもそも乙の所在地すら正確に知らず、乙の所有権移転登記手続も言われるままに夫Aに任せていたが、Y2が夫の元愛人と知って怒りを爆発させた。
この間の2012年11月に、Zの運転していたトラックが暴走して甲に突っ込み、その一部を損壊させたという事件が発生したが、Y1の居住には差し支えなく、Y1は損害賠償を求めてZと交渉を重ねている最中だった。一方、X1は、事故による甲の損傷を知ってAに代金を下げさせ、Zに対する損害賠償債権をAから譲り受け、Aが確定日付のある通知で債権譲渡をZに知らせた。
小問1 XらがYらに対してそれぞれ甲・乙からの退去を請求すれば、認められるか。
小問2 Zに対して損害賠償請求権を行使できるのはだれか。
参考判例
①最判昭和40・12・21民集19巻9号2221頁
②神戸地判昭和48・12・19判時749号94頁
③最判平成8・10・29民集50巻9号2506頁
④大判明治41・12・15民録14輯1276頁
千葉恵美子=潮見佳男=片山直也編『Law Practice 民法Ⅰ 総則・物権編』(商事法務、2009年)167頁[松岡久和]より追加・変形
- 6月17日 登記を要する物権変動
Xは老後の生活資金を捻出しようと、所有する土地甲を売却したいと考え、不動産業者Aに買手の紹介を依頼した。Aの照会を受けたBは、X宅に電話をかけ、「弊社が予定する大規模プロジェクトの予定地として、甲をぜひ買い取りたい」と購入に前向きな姿勢をみせた。そこでXはAの事務所でBと商談を進め、6月10日にX・B間で、売買代金を5000万円として甲の売買契約が締結され、同月末日に内金2500万円の支払と引換えに、甲につきX→Bの所有権移転登記を経由すること、7月30日に残代金の支払と引換えに甲をBに明け渡す旨が約定された。6月30日には、約束通りBからXに2500万円が支払われ、甲の登記名義はXからBに移された。
ところが7月30日が到来しても、Bが残代金を支払わないため、Xは8月20日に、1週間以内に支払うよう催告し、同月27日までに支払がないときは契約を解除する旨を内容証明郵便でBに通知した。それでもBが残代金を支払わなかったので、Xは同月30日に売買契約を解除する旨の通知を内容郵便で発送し、翌31日に通知はBに送達された。ところがBは9月2日に自己のYに対する5000万円の債務を担保するため、甲にYのための抵当権を設定し、抵当権設定登記を経由した。
XはYに対してどのような請求ができるか。またYはどのような反論が可能か。
千葉恵美子=潮見佳男=片山直也編『Law Practice 民法Ⅰ 総則・物権編』(商事法務、2009年)145頁[石田剛]より追加・変形
- 6月24日 物上代位
「保険金の行方」事件
2012年1月10日、Xは、Aに対して、AがBから賃借している土地上に建てる建物甲の建築資金5000万円を融資し、同年8月10日に竣工した甲に抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を備えた。AはXとの約定に従って、C生命保険相互会社と間で保険金額6000万円の団体生命保険を、D損害保険株式会社との間で保険金額5000万円の地震保険特約付火災保険を締結した。しかし、将来発生するかもしれないこれらの保険金請求権のうえにXが質権の設定を受けることはなかった。
2013年3月10日、甲が不審火により焼失し、事業に行き詰まったAは行方不明になってしまった。
同年6月10日、Aに無担保高利で6000万円の融資をしていたYが、AのDに対する保険金請求権を差し押さえた。Yは、自らが融資する際に、すでにXが甲に抵当権の設定を受けて貸付を行っていた事実を知っていた(だからこそほかにめぼしい担保財産がなかったAには無担保高利の融資をした)。
問1 Xが6月14日に抵当権に基づく保険金請求権への物上代位による差押えを申し立てて認められたとすると、保険金は誰に払われることになるか。
問2 Xが6月21日に抵当権に基づく保険金請求権への物上代位による差押えを申し立てたところ、すでにYが本件保険金請求権につき転付命令を得ていた。Xの差押えは認められるか。
- 7月1日 時効の援用
「紺屋の白袴」事件
2001年6月20日、法学部生Xは、事業資金が必要だという友人のA(経済学部生で既に企業を立ち上げている)に500万円を無利息で貸し、毎月月末に25万円ずつ20回分割で返してもらう約束をした。しかし、Aの新規事業に不安を感じたXは、1度でもAの弁済が滞ったら全額の返還を直ちに請求できる旨を定めた。さらに、Aの父親Yが所有する土地に抵当権を設定してもらい抵当権設定登記を得た。Aは初めのうちは収益を得て毎月25万円を返済できていたが、2002年1月末の7回目の弁済後、収益が見込めなくなり、弁済が滞ってしまった。Xは友人のことであり気の毒と思い、全額請求は控えていたが、最後の弁済から5年後の2007年3月頃、法科大学院を卒業してまとまったお金が必要になったXは、Aに残額325万円の弁済を請求した。しかし、Aは返すあてがなく行方不明になってしまった。Yに対して抵当権を実行するのも気が引けたXは、抵当権の実行を行うことがなかった。2013年5月末、Xは独立して自分の弁護士事務所を開設する資金が足りなくなったため、Yに残額の支払いを求めたところ、支払を拒まれたので、抵当権の実行を申し立てた。Yは馬鹿息子Aは義絶したし(親子の縁を切ったということ。法律的には不可能)、いまさら責任を追及されても困ると主張している。Yは土地の競売を拒むことができるか。
突っ込みコメント
この問題原案は100万円の貸付けでした。以下は、問題に付したコメント(一部修正)です。これだけ自分の債権管理が下手なXは、残念ながら弁護士として活躍できそうにありません。職人兼商売人であった私の亡き父は、「友達に金を貸すときは、あげたもの(返ってこなくてもあきらめる)という覚悟で貸せ」と常々言っておりましたが、至言です。Xは、友人に友情を基礎に無利息で貸しておきながら、中途半端に債権回収措置(期限の利益喪失特約、抵当権の設定。100万円くらいを20か月で分割返済してもらう契約につき土地への抵当権の設定を求めるのは普通ではなく、費用倒れに終わりそうにも思えます)を採り、かつそれを何年も放置しながら、思い出したように抵当権の実行を申し立てており、人物像としても一貫性がなく、問題にリアリティが欠けています(もっとも、「事実は小説より奇なり」というように、想像を絶するような人が現に居ますけれど……)。
- 7月22日 債務不履行総合問題
巨額営業利益賠償請求事件
(1) X会社はY会社からO市駅前の本件ビルの地下1階部分を居酒屋の店舗として平成12年4月1日に賃借し、平成16年3月末に期間を1年として更新されて以後、契約の更新は行われていない。
(2) 平成17年3月に本件契約の契約期限が切れたが、以後の契約についてXY間には協議が整わなかった。Yは、同年10月に、本件ビルが老朽化し建替えが必要となっていることを理由として解約すること及び明渡し期限を平成18年4月末日とすることをXに通知した。しかし、Xは平成17年11月に本件ビルは補修すれば十分に使えるものであると主張して明渡しに応じる意思がないことをYに通知した。その後も、XはYに賃料を払い続け、Yはそれを受領し、Xから本件建物部分の利用に関する不具合などの相談を受け対応していた。
(3) 平成19年2月12日に大雨で本件建物部分に浸水する事故があり、Xは以後、居酒屋の営業ができなくなった。平成19年1月の調査会社の診断報告書によると、本件ビルは老朽化していて、電気設備や給水設備を更新・改修しないと漏水の懸念があり、継続使用が難しい状態であると判断されていたが、直ちに大規模な改装及び設備の更新をしなければ当面の利用に支障が生じるものではなく、本件建物部分を含めて使用不能の状態にはなっていなかった。
(4) しかし、Yは、平成19年2月18日付け内容証明郵便で、Xに対して、再び、本件ビルの老朽化が決定的となったことを理由として解約するので、6か月以内に本件建物部分を明け渡すことを求める申入書をXに送りつけた。その後、Xの再三の補修請求に対して、Yは本件ビルは取り壊して建て替えるので補修はできないとして補修を行わなかった。逆にYは、一度は300万円の立退料を提示して明渡しを求めたが、Xは被害の賠償や建物の補修の件につきYに誠意がないとして明渡しを拒絶した。Xは、この間の平成19年4月分から平成20年3月分までの賃料は供託したが、交渉が決裂した後、同年4月分からは賃料の供託をしていない。
(5) 平成21年9月13日に、Yは、Xに対して、あらためて、平成20年4月分以降の賃料の不払い及び賃借の意思がないと推断できる状況にあることなどから信頼関係が破壊されたとして、本件賃貸借契約の解除を通知し、同日、本件ビルの地下の電源を遮断し、本件建物部分への立ち入りを不可能とする措置をとった。
(6) Xは、本件浸水事故の3か月後の平成19年5月末日に、本件建物部分内にあった什器備品類のうち本件浸水事故で損傷したものについて保険金を取得したため、その部分の損害賠償はYに求めていない。Xは、本件浸水事故後、本件建物部分での居酒屋の営業をすることができなくなっていたが、前記保険金には、この営業利益損失に対するものは含まれていなかった。
(7) Xは、この浸水事故は貸主であるYの修繕義務違反によるとして、Yに対して、事故後54か月間の逸失利益5400万円の損害賠償を請求した(Xが本件建物部分での居酒屋の営業により、浸水事故当時、少なくとも月額100万円以上の純利益を挙げていたことは認定されている)。
(8) 他方、Yは、浸水事故以前に建替えの必要があり(2)の解約を申し入れ契約が終了していたのにXが居座ったために生じた損害であり、Yは責任を負わないと反論した。のみならず、仮にこの解約の主張が認められないとしても、本件建物部分の賃貸借契約はあらためて(4)で解約の意思表示をした。さらにこれが認められなくても、Xの17か月に及ぶ賃料不払いを理由に(5)の解除をしたとして、本件建物部分の明渡しを求めた。
問い 諸君はY側の弁護士である。逸失した営業利益の賠償を求めるXの損害賠償請求自体が認容されそうである場合、その認容額を制限するとすれば、どのような法的根拠が考えられるか。問題文に示された認定事実を指摘することはもちろん、さらに裁判所に認定してもらう必要がある事実が考えられるならそれをも挙げて、複数の法的根拠の可能性を示しなさい。
(出典:2011年度法科大学院未修者「財産法の基礎Ⅱ」の最終回講義の論文問題の一部)
- 7月22日 問題解説
【出題の狙いと争点】
本問は、最判平21年1月19日民集63巻1号97頁の事案を参考にした問題で、本年度の民事法文書作成第4回にも出題したものから一部を再利用したものである。モデルとなった判決からは、小浜駅前のカラオケ店を居酒屋に変えたうえ、実際の時間の経過もおおむね10年ずらす設定としている。
問いは、賃借人が請求している過大に思われる損害賠償請求(修繕義務の履行遅滞に基づく営業利益4年余等)を制限する複数の法的根拠を問うている。
問題の扱い方として大別すると、因果関係の問題とする方法と、過失相殺の問題とする方法がある。損害賠償法の基本的な考え方について、きちんと理解できていればある程度は書ける。また、「さらに認定する必要がある事実が考えられるならそれをも挙げて」という部分は、そうした判断を基礎づけるために必要な事実は何かという点についての想像力を求めている。
1 本件の浸水事故は、本件建物部分の使用収益に必要な本件ビルの修繕を怠った民法上の修繕義務違反が認められ、これにより浸水事故が発生したと考えられる。また、これによりXが本件建物の部分での居酒屋営業を行うことができず、月額100万円以上の利益を失ったことまでは認められる。問題は、本件浸水事故から54か月(本件訴訟で請求した時以降の分も含まれればそれ以上)に及ぶ逸失利益がすべて、賠償されるべき損害の範囲に含まれるかどうかである。
2 損害賠償の範囲を否定・制限する方法には、以下のように複数のものを考えることができる。以下では4つを挙げたが、この中から2つを書いていただきたい。
(a) 416条(相当因果関係)を否定・制限する方法(その1)
416条1項は、債務不履行によって通常生ずべき損害、伝統的は判例・通説では、債務不履行と相当因果関係がある損害のみを賠償の対象としている。それゆえ、Xの被ったと主張する損害が、通常生ずべきではない異常な経緯で生じたものである場合には、賠償の対象とならない。
Xが老朽化した本件ビルにおいて、54か月にわたり営業を継続して確実に営業収益を挙げることができたかどうかは明確でない。すなわち、老朽化して大規模な改修を必要としていた本件ビルにおいて、Xが本件賃貸借契約をそのまま長期にわたって継続しえたかどうかを、例えば、①本件ビルの他のテナントの入居の期間、を考慮して判断する必要がある。また、収益の継続の確実性についても、②駅周辺の賑わい具合(この○○市の商業圏の変遷の有無)を本件ビルの他のテナントや周辺商店等の収益状況を考慮して判断する必要があるほか、③競合する他の居酒屋等の飲食店の存在なども考慮する必要がある。さらに、④Xが本件ビルでの営業の再開に固執する理由があるか否かを判断し、⑤他地域への移転の可能がある場合には移転先での収益予測(その差額のみが通常生ずべき損害となりうる)を考慮し、その差額を基本として、通常生ずべきと思われる相当な損害の範囲内でのみ賠償を認めることもありうる。
テナントが営業収益を上げることは当然に考えられ、その逸失利益自体は、通常生ずべき損害と考えて良いだろう。また、問1において解説では否定的に解したが、契約が有効に解約・解除されたと考えれば、賠償がその時点までに生じた損害に限られるのは当然である。その時点以後は、Xには本件賃借部分の使用継続を期待できる地位がないからである。問1の答えをふまえた整合性のある解答は評価できる。
(b) 416条の特別損害を否定する方法
Xが本件ビルでの営業の再開に固執するなどの点でXに固有の特別な事情があり(例:経営者の家庭内の事情から居住場所と近い本件ビルでの営業継続が必要である)、それが基礎となって損害が発生している場合には、そのような特別事情についてのYの認識可能性がなければ、たとえそのような特別事情から通常生じると思われる損害であっても、賠償の対象とはならない(416条2項の特別損害)。これは通常生ずべき損害を限定するという意味では(a)に含まれるともいえるが、特別事情の予見可能性を問題にする点で、独立して数えてよい方法となろう。
特別損害を通常では考えられないような損害と理解してはいけない。何を特別事情と解するかは、かなり難しい問題である。漫然と特別損害だから予見可能性が必要で賠償範囲が制限される、と述べても意味がない。そのためには、どういう事実を特別事情と認定するかを考えて具体的に論じて欲しい。
(c) 416条の通常損害を制限する方法(その2)
モデルとして使用した平成21年判決は、次のように述べて、416条の解釈を条理により制限するとの判断を示した。具体的には、営業を別の場所で再開する等により損害を回避又は減少する措置を採ることができた時期とそれ以降に生じた損害を具体的に考慮して賠償すべき範囲を明らかにせよと指示している。
「遅くとも,本件本訴が提起された時点においては,被上告人がカラオケ店の営業を別の場所で再開する等の損害を回避又は減少させる措置を何ら執ることなく,本件店舗部分における営業利益相当の損害が発生するにまかせて,その損害のすべてについての賠償を上告人らに請求することは,条理上認められないというべきであり,民法416条1項にいう通常生ずべき損害の解釈上,本件において,被上告人が上記措置を執ることができたと解される時期以降における上記営業利益相当の損害のすべてについてその賠償を上告人らに請求することはできないというべきである。」
最高裁の条理の援用の趣旨は必ずしも明確ではないが、損害軽減義務を介して通常生ずべき損害を限定する方向と思われ、利益取得の確実性に重点を置く(a)(b)のような方法とは重なる部分もあるが、異質な内容を持っていると思われる(最高裁判決では、上記の④⑤などの事情が重要で、①~③の事情は挙げられていない)。
なお、最高裁判決も指摘しているが、Xが什器備品等について保険金を受領し、買い換える資金をすでに得ていて、他の場所での営業再開が経済的には不可能でないようであるという(6)の事実も考慮されてよい。
(d) 過失相殺を用いる方法
被害者=債権者Xにも信義則上、損害の発生や拡大を防止する義務があり、そのような義務に反して生じた損害は、債務者との間で適切に分配されるべきで、全額の賠償を求めることができないとするのが418条の過失相殺の趣旨である。一種の損害軽減義務を考えるものであり、④の他地域への移転の可能性などが最も重要な事実となろう。この点では(c)と近いが、416条ではなく418条を根拠にするところに特色がある。
答案を書く際には条文はきちんと指摘して欲しい。
以上の論拠のほか、相殺、損益相殺も考えられないではないが、せいぜい補充的な主張であり、本問で問われていることからは外れている、相殺は、賃料債権等の自働債権がYに発生していることを前提とする。使用収益させることができない以上、賃料債権は発生していない可能性があり、相殺の前提自体が成り立たない可能性が高い。かつ、この方法では、長期にわたる損害の賠償責任自体は何ら制限されず、問題で問うている趣旨に適切に答えているとはいえない。損益相殺は、債務不履行によってXが利益を得たことを前提とするが、本問ではそのような利益の存在は明らかでない。また、Xが営業に必要な人件費、光熱費、材料費などは、純利益100万円の算定の中ですでに控除されており(だから営業粗利ではなく純利益なのである)、損益相殺として重ねて控除を主張することはできない。
付言
通常生ずべき損害の範囲につき、被害を被った者の損害回避義務違反等を考慮し決定する場合において、範囲を限定する際の検討において過失による損害義務違反が認められたとき、過失相殺を定めた418条をさらに適用することができるのかが問題になる。
過失の前提となる義務違反が場面によって異なるものであれば、416条の通常生ずべき損害の評価である過失(この事例では、たとえば、他の地域へ移転した営業継続によって損害を回避する義務の違反)を考慮して賠償されるべき損害を算定した上で、別の過失(この事例では明らかではないが、Xが漏電調査等のための立ち入りのYの要請を拒んだとか、修繕作業に非協力的であるなど、逸失利益問題と直接関係のない義務違反)を理由に、さらに418条を用いた過失相殺を行うことは可能である。しかし、同じ過失を416条で考慮して損害額を算定し、さらに過失相殺でその損害額を減額するのは、同一の行為の二重のマイナス評価であり、許されない。416条では考慮されない義務違反が418条で考慮されることになろう。ただ、この判断枠組は、損害軽減義務違反を416条と418条のいずれに割り振るのかという基準を明示できないと、混乱を生じる。
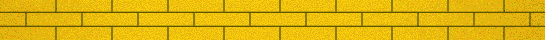
![]()