11月23日(祭)に龍谷大学深草学舎21号館301号教室において、5大学8ゼミの参加を得て、第6回インターカレッジ民法討論会が開催された。13時30分の立論スタートから18時の教員討論の終了まで、200名前後の参加者が熱心に討論に参加した。引き続き、アサヒルネサンスビルのアサヒビアレストランで21時まで成績発表・表彰・懇親を行った。さらに大学・ゼミを超えて親しくなった者が二次会に繰り出したが、後は知らない。
龍谷大学の森山先生および今年から準備連絡・会場設営・進行・会計処理に至るまでたいへんなご尽力をいただいた龍谷大学ゼミナール連合会(http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Labo/5835/ にも結果などを掲載予定だそうです)の学生諸君には、心から御礼申し上げます。
結果
| 順位 |
大学 |
ゼミ名 |
総合得点 |
教員票 |
学生票 |
| 1 |
法政 |
金山ゼミ |
236 |
50 |
186 |
| 2 |
京都 |
松岡ゼミ |
219 |
60 |
159 |
| 3 |
京都産業 |
高嶌ゼミ |
181 |
45 |
136 |
| 4 |
龍谷 |
牛尾ゼミ |
142 |
20 |
122 |
(得点表は上位4チームまで。以下、森山ゼミ・中田ゼミ・坂東ゼミ(龍谷)・坂東ゼミ(京都学園))
得点表の集計に誤りがあったようで12月10日に修正しましたが、順位に変動はありません。
優秀質問者賞
1 藤本君 京都大学 松岡ゼミ 77票
2 樋山君 法政大学 金山ゼミ 41票
3 草野君 京都産業大学 高嶌ゼミ 14票
総評
各立論ともかなり準備して主要論点を検討しており、勉強の成果がうかがえるよい報告であった。ただ、例年同様、立論でどこに重点を置くかを含めたプレゼンテーションや質疑応答の巧拙には、少し差が出た。質問者は質問の要点を明確に示して聞く方がよいし、応答の前提として質問の意図を十分把握し、答えも自説の繰り返しに終わることなく、質問者の意見とかみ合うような討論になるようにいっそう努力して欲しい。学者の間ですらかみ合った討論はなかなかに難しいが(教員討論のおりに諸君も実感されただろう)、ふだんからゼミの時間や友人との討論を通じて、自覚的に鍛えてもらうほかない。
私の評価では、森山ゼミ・松岡ゼミ・金山ゼミ・高嶌ゼミがほぼ横一線だと思われたが、立論に重点を置いて森山ゼミを一位、松岡ゼミを二位、金山ゼミを三位に推した。詳しいことは各ゼミに対する短評を参照して欲しい。
質問者者賞を受賞した藤本君は、5回生の松岡ゼミオブザーバーで今秋の司法試験合格者なので、要点を突いた好質問ができたのはさすがである。草野君は、関連質問の出し方がうまかった。樋山君は報告と同趣旨の質問が多かった印象があるが、報告に欠けている点を鋭く指摘した。賞は逃したが、池田君、丹治君、中村君、加藤君の質問もよかった。
各ゼミ報告の短評
報告順に、各ゼミ報告を短評する。あくまで私の主観的評価なので、ゼミの先生のコメントとあわせて参考にし、今後のゼミ活動や来年のインカレ民法討論会への糧にしていただければ幸いである。
1 松岡ゼミ
各論点について要件充足の判断が丁寧でよかったし、不当利得の効果についても論及し、問題意識を持って検討しようとしたことがうかがえた。質疑応答もまずまずだった。詐欺の肯定にはもう少し慎重さが欲しかったし、なにより報告の時間切れが痛かった。異論が出にくい要件については検討を簡略化し、取締法規違反・公序良俗違反についても論及できれば、さらによい報告となっただろう。この点は練り上げ不足。
2 森山ゼミ
最初に取引の構造的な問題を指摘したことと、法令違反や経済公序論にまで含めて論点をバランスよく論じた立論は最も良かったと思う。ただ、本件のAの言明が簡単に断定的判断の提供に該当するのか、不動産投資の危険についてまで説明義務が生じるのかなどについては判断が甘い。既履行を「がいりこう」と読んだのはご愛敬としても、質問への応対では練習不足が露呈してしまった。惜しい。
3 金山ゼミ
論点を最初に明示したこと、報告者の見解をきわめて鮮明に打ち出し、質疑応答においてもその姿勢を一貫した歯切れの良い答えができたことが、高く評価された理由である。戦略がヒットしたわけだ。しかし、長所と欠点は表裏一体で、損失填補特約の認定や一般的な情報提供義務の根拠は弱く、質問への応答は自己の見解を反復しただけで、質疑が実質的な討論に至らなかった。この点はぜひ反省して欲しい。
4 坂東ゼミ(京都学園)
両当事者の主張を対比する形で論点を煮詰め、責任をすべて否定した立論は異色だったが、判例の流れからすると本問では実はもっとも予想できる結論と合致していて評価できる。ただ、問題文の解釈はやや強引な感があり、責任否定の論拠はいささか弱く、質問に対する答えはすれ違いも目立った。また、報告の仕方には一考を要し、レジュメとは別の原稿を用意した方がよかったと思う。
5 高嶌ゼミ
要点と結論を明示したレジュメが充実しており、詐欺要件の充足が困難だとの指摘は適切だった。ただ、質問で突っ込まれた錯誤無効の否定、損失填補約束の否定については、必ずしも説得力のある反論・説明ができなかった。また、「自己責任の原則が働くことを説明する義務」を一般的に定式化できるとは思えない。総じて、論拠をもう一歩突っ込んで検討しておけば、よりよいものになっただろう。
6 坂東ゼミ(龍谷)
不法行為構成に的を絞って議論し、地価公示法と統計を用いて暴利行為を示唆した点は、いい着眼であり、免責特約否定も適切だった。惜しむらくは、暴利行為をはじめ法律行為法による問題処理にあと一歩踏み込んで欲しかったことである。この点での準備が不足していたために、厳しい質問に立ち往生させられた。また、責任減額の処理では、損害論ではなく過失相殺に言及して欲しかった。
7 中田ゼミ
錯誤・詐欺・不法行為・契約締結上の過失(明示はしていないが)について、要領の良い整理を行っていて、2回生の立論として見ると立派で、好感が持てる。ただ、錯誤の前提として、損失填補特約が成立しないことはもう少し立ち入った検討が必要だったし、何について錯誤したのかが明確ではなかった。また、「錯誤できる」という表現は、簡略化しすぎで慣用的ではない。根拠条文にもレジュメに誤記が目立った。
8 牛尾ゼミ
不法行為構成に絞り、免責条項の問題にも言及して丁寧な検討を行った立論と、質問に対する堂々とした応答は、高く評価できる。ただ、使用者責任の検討に時間を割くよりは、損失填補約束の成否、法律行為法上の諸問題に言及する方が、全体のバランスがとれると思う。なお、義務違反を直ちに権利侵害だとした部分は、義務違反で違法性を判断する過失一元論的な理解なのだろうか。説明不足で疑問が残った。
参考資料
第1〜3回インターカレッジ民法討論会の概要
第1回 松岡久和・法学教室174号61〜63頁(1995年)
第2回 金山直樹・法学教室186号(1996年)
第3回 七戸克彦ほか・法学セミナー515号14〜22頁(1997年)
※いずれも、要旨が業績一覧ページに掲載してあります。
今回の問題に関連する松岡の論文など
「原状回復法と損害賠償法」(1996年)ジュリスト1085号86〜95頁
「変額保険の勧誘と銀行の法的責任」(1996年)金融法務事情1465号17〜29頁
「変額保険の勧誘における説明義務違反と損害賠償責任」(1997年)私法判例リマークス15号60〜64頁
「商品先物取引と不法行為責任−債務不履行構成の再評価」(1999年)ジュリスト1154号10〜20頁
※いずれも、
業績一覧ページに要旨付で掲載しています。
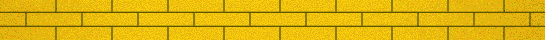
![]()
![]()